 |
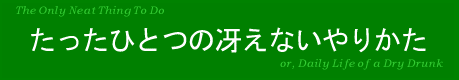 |
ホーム > 日々雑記 「たったひとつの冴えないやりかた」
たったひとつの冴えないやりかた
飲まないアルコール中毒者のドライドランクな日常
もくじ|過去へ|未来へ
2007年07月17日(火) 渇酒症 渇酒症という言葉があります。
僕が入院を繰り返している頃には、「自分は渇酒症だ」と言っているアル中患者さんがある程度いたような気がします。
渇酒症もアルコール依存症の仲間なんでしょうが、酒をなかなかやめられない普通(?)のタイプの依存症者とはずいぶん違った症状だと聞きます。
彼らはふだんはまったく酒を飲みません。ところが例えば年に1回とか2回とか、あるいは数年に1回、バケツの底が抜けたかのように飲み出すことがあり、そうなると数日から数週間、社会生活を放り出して連続飲酒にふけります。ところが、ここから先が違うのです。渇酒症の人は、あるときぴたりと酒をやめ、その後酒を遠ざけるのに何の苦労もありません。しかしいずれ連続飲酒の時期がやってきます。こうして間欠的に大量飲酒を繰り返すのが特徴です。
普段は酒をやめるのに苦労をしないことから、普通のタイプのアル中さんと共感を得るのは難しいようです。
ところで普通のタイプのアル中さんも、症状が進んでいくと山形飲酒サイクルというものが出現する場合があります。これも、大量に飲酒する時期があり、あまり酒を飲まない時期があり、再び大量飲酒の時期がやってくる、というサイクルを繰り返します。
なぜこうなるのかと言いますと、病気の進行の結果です。アルコール依存症は飲酒のコントロールを失う病気、ブレーキの壊れたダンプカーに例えられますが、そのブレーキの壊れ具合がだんだん進行していきます。最初のうちは連続飲酒に突入する(つまりダンプが暴走する)までには、再飲酒からだいぶ間がある(それだけコントロールが効く)のですが、重症になるとコントロールがほとんど失われてしまい、ちょっと酒を飲み過ぎただけですぐに大量飲酒・連続飲酒に結びついてしまうため、ダンプカーもおいそれとは走らせられなくなります。
意志の力による断酒期間・節酒期間と、あっという間に落ち込む連続飲酒期間が繰り返されてるところは、外から見れば渇酒症に似ています。
僕が入院していた頃に渇酒症を主張していた人たちは、やっぱり普通のタイプのアル中さんたちで、自分の山形飲酒サイクルを渇酒症だと思いこむことで、自分は普段酒をやめるのに何の苦労もない、と自分に言い聞かせようとしていただけなのではないか。そんなことを思います。
最近では渇酒症を主張する人には、滅多にお会いしません。
2007年07月16日(月) 笑うしかない 「人生は近くから見れば悲劇だが、遠くから見れば喜劇である」(Life is a tragedy when seen in close-up, but a comedy in long-shot)
とはチャップリンの言葉だそうです。
「そんな時代もあったねと、いつか笑って話せるわ」と歌ったのは中島みゆき。
恥ずかしい過去が、恥ずかしいままでいるのは、自分がそれを笑えていないからでしょうか。
「あまり自分のことで深刻になりすぎるな。笑えるようになれ」
という文章もAAの本のどこかにありましたな。
過去の話を笑ってしているのは、そういうわけです。人をほめ、自分を笑うには練習がいるんだそうです。
2007年07月15日(日) 経済的自立とは(その2) 例えば「誰かからAAミーティング場を紹介してくれとオフィスに電話が来ても、うちのグループは紹介しないでくれ」とか、ミーティング一覧表にも載せないでかまわない、イベントの問い合わせ先にならなくてもかまわない、ラウンドアップその他のAAの催し物も行かないから受付代行も要らない、ミーティングのお休みの案内も『かわらばん』に載せなくて結構・・・というのなら、オフィスも不要かも知れません。
でも、オフィスのサービスは要らないから、うちのグループは献金を届けない・・と言っても、おそらく彼らは献金のあるグループもないグループも、分け隔てなく扱うでしょう。
そういうサービスをしてくれと頼んだ覚えはなくても、知らないことに頼んだことになっているし、現にそのサービスを享受しているわけです。ちょうど、不動産屋に連絡するだけで水道や電気が開通したように。でも、公共サービスと違うのは、お金を払わなくても、AAのオフィスのサービスは止められないということです。
AAオフィスのサービスの中には、なるほど間接的で見えにくいものもあるでしょう。だから、その恩恵を感じにくいのかも知れません。しかしながら真の原因は、水や電気が供給されることが当然に感じられて、止まったときに思わず怒りが出るように、オフィスのサービスも「あって当たり前」に感じていることにあるでしょう。
自分がリクエストしたサービスの経費を支払う、それも誰かの財布を当てにせず、自分の財布から出す。オフィスに献金を送ることによって、オフィスとグループが「霊的につながるのだ」そうです。そのつながりがAAの一体性を維持するひとつの手段なのでしょう。
AAの費用は義務的に集めるわけではないので、僕らが「あって当たり前」のものの意味に気づき、自分の責任を感じられるようになるまで、待っていてはもらえます。確かにオフィスの存在は僕らには大きな経済的負担ですし、「献金を送ってくれ」という声は耳にうるさいものです。でもそれも、僕らの回復を手助けしてくれる存在なのです。
自由に使える金が欲しいからと、焦って仕事に就いたところで、最低限の「経済的自立」という回復がなければ、間違った金の使い方しかできません。結果として、金を稼いでいても、いつも経済的不安にさらされることになるでしょう。
「霊的な回復の前に、経済的な回復はやって来ない」と言いますからね。「経済的不安もなくなる」ってのは、不安を感じないほどたくさん稼げるようになると言ってるわけじゃないですよ。
(とりあえずこの項おしまい)
2007年07月14日(土) AOSMこぼれ話 AOSMの話をはさみます。
AOSMの場合、会議で何を決議しても、それを実行するサービス機関がありませんから、議決は「勧告決議 advisory action」ではなく、recommendation と呼ばれます。
さて最終日の午後の後半は、次回の内容などを決めるビジネスミーティングが行われました。僕が覗いたときには、次回のテーマ(トピック)を決めているところでした。みんな内心暖めてきたアイデアがあったのかどうか知りませんが、テーマ案は10個提出されました。それぞれ提出者の意見を聞いた後で、投票に移りました。
最初の投票では1番〜8番の案は得票が0〜2票で、9番と10番が多くの表を分け合っていました。再度投票が行われましたが、票はあまり動きません。
議長が「第三レガシー手続きで」と表明して、この時点で1/5の得票がなかった1〜8番の候補は全部除外となりました。3回目の投票は9番と10番のみで行われましたが票が割れ、どちらも2/3は獲得できませんでした。4回目の投票でもそれは変わりません。
帽子(hat)という言葉が発せられ、実際用意できたのはcapでしたけど、その中に9と10と書いた紙が入れられ、中立者として日本の理事会議長がそのくじを引きました。彼のNine(9)という言葉は、拍手で迎えられました。
AAの大切な議決は過半数では不十分で、2/3は必要だとされます。実際投票をやってみると分かりますが、意見が分かれているときには、なかなか2/3を取ることができません。投票を繰り返しても2/3に達しないときには、最後は帽子を使ったくじ引きになります。大事なプロセスだと言われていますが、現実に目にする機会はあまりありません。
次は次回の議長の選出で、これも帽子になりそうだと噂されてたんですが、僕は帰る時間になったので、実際どうなったのかは知りません。
AAの議決では2/3という数字を大切にし、それに達しないのならくじ引きの結果の方が良いという民主主義です。
今夜は地区委員会にオブザーバー参加していたのですが、一回目の投票で最大得票のに決めてしまったのは、ちょっとつまらなかった感じです。まあ、決めていたのが地図の紙の色でしたからねぇ、どれでも良いって言えばそうなんですけど。
2007年07月13日(金) 経済的自立とは(その1) AAで言う経済的自立とは、自分で使うお金を自分で稼ぐと言うことではないと思います。あなたの財布にお金を入れる人が誰であるか、つまりあなたの稼ぎだろうが、配偶者の稼ぎだろうが、親や兄弟の援助だろうが、あるいは失業保険・傷病手当・生活保護・障害年金などの公的扶助だろうが、貯金を食いつぶしているだけだろうが、それはこの際問題ではないということです。
問題なのは、あなたが自分にかかる経費を、自分の財布から出しているかどうかです。出所がどこであれ、いったんあなたの財布に入ったからには、あなたのお金です。それをどう使うかは、純粋にあなたの問題です。伝統7が問うているのは、誰が財布に金を入れるかではありません。自分の経費を誰の財布から払うかです。
一人暮らしで酒を飲んでいた頃、水道と電話は良く止まりました。金を払わないからです。幸い電気が止まった経験はありませんし、ガスは契約してなかったのでメーターが取り外されていました。
水道が良く止まったのは、不払いの常習犯になると銀行引き落としにできず、窓口納付になるからです。そもそも払うのが面倒なヤツに、市役所まで来て払えと言うのは無茶な話です。最初は半年ためないと泊まらなかった水道が、そのうち払わないとすぐに止まるようになりました。止水栓が締めてあるだけだったのが、勝手に開けて使っちゃうので鍵が二重三重と増えていったりして・・。
水道が使えないと、トイレが流せないとか、流しに吐いたゲロが始末できないとか、ただでさえ劣悪なアル中の一人暮らし環境が、さらに最悪なものになります。
恨みましたね。何で俺が、こんな目に遭わなきゃなんねーのか。我意でよけいな手間をかけさせてるだけなんですけどね。誰か自分のかわりに水道代を払ってきてくれないかな、とか考えたりしました。面倒なことは全部誰かに任せて、僕は酒を飲んで安楽に暮らしたかったのです。
水道も電気も契約をした覚えはありません。不動産屋に何日に入居と伝えておくと、その日には水も電気も使えるようになっている。それを不思議に思いませんでした。でも、公共サービスは利用者が経費を負担することで成り立っています。
僕は、水道の蛇口をひねることで、また何かのスイッチを入れることで、水や電気という公共サービスをリクエストしていると考えたことはありませんでした。基本料金+使った分というルールは理解していても、金を「取られている」という意識でした。自分が要求しているという意識がないので、誰かがかわりに払ってくれていたらいいのに、と思ってしまったのです。
「自分が要求したサービスの経費を払うのは当然のこと。誰かに払ってもらうのではなく、自分が払う」 伝統7が言っていることは、常識的にすぎません。要求していることすら意識していないこともあるけれど、負担があるのは当たり前です。
AAのオフィスからはいつも、「お金がないんだよー」「献金が足りないんだよー」という声が聞こえてきます。いつも金の話ばっかりという気もして、言う方も言われる方もうんざりって感じもあります。でも、AAのオフィスって「サービスをするためのオフィス」なんです。しかも、「僕ら」がリクエストしたサービスをする機関です。
(たぶん続きます)
2007年07月12日(木) スポンサーのおもいで 人の話をするのもどうかと思いますが、まあスポンサーの話ですからね・・・。
僕のスポンサーは(最初の頃は)見た目が怖かったし、学もあんまりなさそうだったし、話し出すと長かったし、いろいろコンプレックスも感じさせたし、世間的な基準で魅力に溢れる人かどうかは、ちょっと疑問が残る人でした。
でも、人間的な魅力、あるいは愛情といいましょうか、AA的な言葉で言えば「引きつける魅力」に溢れた人でした。何でも自分でどんどんやってしまう割に、「この人ひとりじゃやってけないな、俺たちが付いてなくちゃ」と思わせるところもありましたね。イマドキの言葉で言えば、とっても「濃い」AAメンバーだったわけです。
だから、そのグループが彼を中心とした結束していたのも、当然といえましょう。彼がどんなに「謙虚にしていよう」「口を慎んでいよう」としても、周りの人間がそうはさせませんでした。彼の小さな一言が、グループメンバーの意見を大きく左右してしまいました。そのグループが、AAの魅力よりは、彼個人の魅力によって集まった人たちでできていたのですから、それ以外のありようが無かったのです。
そして、その輪の中にいる僕らも、それがそんなに大きな問題だとは思ってもいませんでした。
スポンサーにもスポンサーがいて、たびたびそのことを指摘されて悩んではいたようですが、事態はあまり変わりませんでした。ある時、事態を大きく動かす一言がグランドスポンサーから発せられました。
「お前のグループはAA○○グループじゃなくて、AA□□グループだな」
(○○はグループの正式な名前、そして□□はスポンサーのニックネームです)。
その言葉で彼は、ここにいる限り、自分がどう望んでも「元老」にはなれず「死にかけの執事」にしかなれないことを知ったのです。それは僕らが「元老」になることを許さなかったということです。そして彼は「後は任せたよ」とだけ言ってグループを出て、別の町でAAミーティングを始めました。
そのころすでに別の場所に移っていた僕には、一見不可解としか思えない彼の行動の理屈がよく分かりました。
ただの普通のAAメンバーであるにも関わらず、グループの創始者は暗黙の権威を帯びてしまうことが往々にしてあります。ある時、他県のメンバーと「グループ創始者がとどまり続けたために成長の限界に達しているグループは多い。出て行くことでしか謙虚を実践できないこともある。それは個人の回復が足りないからで、認めるのは嫌なことだが、現実を見つめなくてはならない」という分かち合いをしました。自分がいなくなっても大丈夫にするのが、最大の貢献という考えです。
僕は「ひいらぎ一派」とかスポンサーピラミッドのようなものを形作らないように、考えて気を配ってきたつもりではいます。それは僕も、権勢欲が強いタイプであり、仲間を支配することに心の痛みを感じないタイプの人間だからです。ちょっと淋しい気もしますが、それはそれで仕方ないことだと思っています。a rolling stone gathers no moss というやつですか。おかげで得られないものもあるということです。
誰かが出て行った後のグループは、ちょっとドタバタするものですが、何年か後になってみればそれが成長の契機だったということになると思います。もちろん、別のやり方もあると思いますし、それが悪いというつもりもありません。僕は単にスポンサーから受け継いだ考え方、やり方を守っているに過ぎないのであり、おそらくそれが僕にとって最善だというだけにすぎません。
そろそろ次の動きがあるのか、まあ未来のことは神様にしか分かりません。
2007年07月11日(水) AOSMみやげ話 4 月・火・水と予定が入っていて早く帰宅できなかったのですが、それも今日でおしまい。明日は早く帰れそうです。体も心もかなり疲れている感じがします。
ソブラエティ1年目に群馬で開かれたラウンドアップに行ったことを思い出します。sその時は2泊3日を終えて帰ってきた午後から、夜まで寝て、翌日月曜日も休んで一日ぐーぐー寝ていました。今は当時より体力が付きましたが、年齢による衰えってものもありますから、疲れは数日引きずってしまいます。
今回わざわざ2泊3日で出かけていったのは、自分の能力を見極めるという目的がありました。AAはミーティングに参加する以外にも、さまざまな活動があって、例えば刑務所を定期的に訪問して話をしている人もいれば、集まってソフトボールやバーベキューをする人もあり、オフィスの運営委員をする人もいます。看護学校や高校で広報活動をする人、12ステップコールの電話を受けている人、定期刊行物の編集やホームページの更新をする人。などなど。もちろん、それに参加するもしないも自由です。
スーパーマンでもなければ、AAの全部の領域に関わることなんてできやしません。だからこそ、自分に何ができて、何ができないか。他の人の方がうまくできるんじゃないか。あるいは、やる人がいないから苦手でもやるしかないか。そういうことを見極めていくことは大切だと思っています。
会場には能力が高い人はたくさんいました。しかし、WSM評議員になるには、能力の他にも、さまざまな「望ましい」をクリアする必要があるので、人材豊富とは言い難いわけですが、みんな回復と成長の途中ですから、先のことを心配することもないでしょう。
AA program is NOT the program for the people who need it, but for the people who want it.
(冠詞の使い方間違ってる?)AAプログラムはそれを必要とする人のためにあるのではない。それを求める人のためにあるのだ。
AAプログラムがあれば、アルコール依存症から回復して酒を飲まない人生を送れる人がたくさんいます。そういう人たちは「AAを必要としている」と言ってもいいでしょう。でもAAは「AAを求める」人のために存在しているのだ、という意見でした。徒労に終わるメッセージ活動に関してのトピックの中の言葉です。AAプログラムを12ステップと読み替えてもよさそうな感じです。
とりあえずAOSMみやげ話は、ここでいったんお終いにします。2泊3日のあいだ、一度も外出せずに自ら缶詰になっていました。それだけ熱中していたわけです。
「こういう場所に来ると、他にも行きたくなりますね」という話をしていた人が今した。それは外国という意味かもしれませんし、他のAAイベントなのかもしれません。あまり行く気はなかったのに、できれば9月に同じ場所で開かれるサービスフォーラムにも来たいと思っている自分を見つけました。
家では妻が「自分ばっかり2泊も遊んできて、おみやげすら買ってこない」とご立腹でありました。やれやれ、これじゃ9月も簡単じゃないぞ。
2007年07月10日(火) AOSMみやげ話 3 場所:
埼玉嵐山の国立女性教育会館(ヌエック)が使われました。オブザーバー費用は2泊6食ぶんで1万2千数百円でした(かな)。会場費用などはゼネラルサービスの会計から出ているので、参加費は取られませんでした。
今回はロシアからの参加がありました。ロシアのウラル山脈から東側はアジアになるので、ロシアAAはAOSMに人を送ることに決めたようです。実際やってきたのは、サハリンのAAグループから英語が少しできる若い人で、結構コミュニケーションにも苦労していましたが、みんな彼を歓迎していました。
モンゴルは今でこそ親日的な国で、AAでもモンゴルと日本はかなり深い関係にあります。しかししばらく前まではソ連の影響下にあり、ロシア語で教育が行われていた国です。もともとモンゴル語には表記文字が無く、キリル文字を使ったりしていて、文化的にはロシアの影響が色濃く残ります。日本の大相撲で、モンゴルやグルジアやバルト諸国出身の力士たちが、ロシア語で会話を交わしている、なんて話もありました。シベリアのAAメンバーは、モンゴルAAのコンベンジョンに訪れていたりするそうで、日本人と違って言葉の壁がないだけに、モンゴルとシベリアのAAの結びつきは、今の日本との関係以上に深まっていくのではないかと思った次第です。
さて、今回のAOSMでは、日本の評議員の発案で、各国の評議員メンバーと日本のAAメンバーとの直接交流の時間が取られました。これはすばらしいアイデアだったと思います。
あるAAメンバーは、「私はスポンサーに従って最初にステップ4の棚卸し表を書いたときに、生まれたときから今までの人生を1年づつたどるライフストーリーを書いたのですが、これはビッグ・ブックに書かれているのとはずいぶん違うやり方です。でも当時はみんなそのやり方をしていたのです。はたしてそれは正しいやり方だったのでしょうか」という質問をしていました。
それに対する香港のAAメンバーの答えは、「あなたのスポンサーは、あなたにはそのやり方が一番良いと思ってそのやり方を勧めたのでしょう。だから、あなたがスポンサーを選んだときに、あなたはステップ4のやり方も自分で選んだのです。それが、あなたのハイヤー・パワーでしょう」というもので、隣にいたオーストラリアのAAメンバーもそれに賛成でした。
「でも当時は、ほんとうにそれしか方法が伝えられていなくて、みんなそうしていたのです」という質問には、「あなたはたった一つしかないやり方を選んだ。それがハイヤー・パワーです」。
またステップ5を書いた後に、棚卸し表を燃やした話も出まして、「それじゃあその表を使ってステップ8の表が書けないじゃないか」という質問に対しては、「古い人生が終わって、新しい人生が始まるんだから燃やしてもかまわないじゃないか」、表はまた書けばいい。しかしあなたのスポンサーが燃やさないように提案したなら、燃やさないのが最善。
ともかくまずスポンサーを選ぶ、そしてスポンサーが最善と思って提案してくれたやり方に従っていく、それがAAプログラムであって、やり方を良い・悪いと比べてみるのは意味がないということであります。
スポンサーとして提案する立場としても、他のやり方の方が良いんじゃないかという不安は常につきまとうもので、「あいつにステップ4を書かせるなんてまだ早いよ」なんて言われると、とたんに自分の提案に自信がなくなったりします。しかし、その時自分が最善と思って提案したのなら、そこにハイヤー・パワーが宿ると信じるしかありません。
少人数のグループに分かれすぎ、通訳の人手が足りなくなったので「ひいらぎさん通訳してよ」なんて言われてしどろもどろでやっていました。別のグループでは下ネタの分かち合いが行われていたそうです。そっちも楽しそうです。
2007年07月09日(月) AOSMみやげ話 2 本社の偉いさんの送別会。会社を大きくするために頑張ってきた人たちが、最後の数年ぐらいは好きにやりたいと退社するのが続いています。それは、前の会社時代から世話になった人たちが会社を去っていくことを意味するので、寂しい気持ちもあります。
週末の疲れも残るだろうからと有給休暇を入れていたのですが、送別会の日取りが他に取れないというので、有休をキャンセルし、送別会の参加者を長野に集めるために行われた会議に出てました。眠い眠い。夕方からの中華料理はおいしかったのですが、会費五千円は痛い、痛すぎるぞ。
さて、AOSM。
参加人数:
議決権を持った参加者が20人ぐらい+通訳の人ふたり。各国の評議員の中には奥さんと来ている人がいて、ひょっとしたら日本のアラノンとコンタクトを取ったかも知れません。host committee(実行委員会)のスタッフが十数人。それから僕らのようなオブザーバーが一番多いときで30人ほど。土曜の夜の集合写真には60人前後が写っています。
さて、AAのプログラムには神とか祈りが出てきます。ただAAは宗教ではないので、こういった要素を spirituality(霊性)と呼んでいます。この霊性に対しては、AAがアメリカで誕生したものだから、キリスト教文化そのものなのではないか、という誤解があり、拒否反応の原因になっています。自分が納得できる神なら、どれでも好きなものを選べばいいということは無視されがちです。
アジアの国々の多くは、(日本のように)現地人だけでAAが維持されるところまで行っておらず、英語を話す国々からやってきた人たちが主になって、自分たちのコミュニティを作り、そこに現地の言葉を話す人を巻き込んでいこうとしている段階です。
そこで「アジアの文化の中でAAを伝えていくのに、このAAの霊性が障害になっていませんか。そうした文化的な壁があるなら、それをどうやって乗り越えていますか」という質問をぶつけてみました。
ニュージーランドは白人と英語の国ですが、人口の十数%はマオリという原住民で、彼らは文化と言葉の壁を越えてAAのメッセージを運ぶことに成功しています。事実、ニュージーランドから二人来ていた評議員の一人はマオリの女性でした。また、オセアニアの島々にメッセージを運ぶ作業も続けています。これはNZ評議員の言葉。
「スピリチュアルなものに対する障壁は、なにもアジア人だけに限ったものでなく、(世界の)すべてのAAニューカマーが体験するものです。成功するAAグループというものは、ハイヤー・パワーについて真正面から取り組んでいるグループです」
AAの神というものはアジア人には似合わないとか、だからそれは脇に置いた方がよいと考えるのではなく、愚直にプログラム通りにやった方が良いってことでしょうか。
しかしタイの評議員は、ビッグ・ブックを翻訳するのにGodという言葉は使えず、supreme(超越者)と訳したものの、その概念はタイの人々が受けてきた教育とは相反するアイデアでなかなか理解されない、と報告していました(それは隣国カンボジアの話か?)。これは暗黙にではありますが、神とかハイヤー・パワーというものを取り除くか薄めたらどうか、という主張を含んでいるように思います。
NYGSO所長のコメントは、アメリカの中でも自分たちのためにビッグブックを変えようという意見もあるが、現在のところビル・Wの文章は変えないことが議決されている。もしビッグブックを変えて欲しいと思うのなら、その国のAAの正式な議決としてニューヨークに送って欲しい。というものでした。
やはりハイヤー・パワーについて、自分のグループや、自分のスポンサーシップの中で真正面から取り組んでいくことが、(少なくとも自分にとっては)ベストであろうと思ったのです。
2007年07月08日(日) AOSMみやげ話 1 時系列に沿って書こうとか、基本的な説明から始めようとすると、筆が進まないので、思いつくままに書いてみようと思います。
英語について:
AAの国際公用語は英語とスペイン語ですが、アジア・オセアニア地域帯ではスペイン語が公用語になっている国は(たぶん)ないので、会議は英語ということになります。
ちなみに僕の英語は、最近ニュースにもなった駅前留学のスクールに1年間通っただけです。職業訓練給付金制度ってのがありまして、その指定のコースに8割以上の出席率で通うと、授業料の8割を補助してくれるという仕組みです。例の報道の後、あそこは給付金制度の指定も取り消されたと聞きますが、受講途中だった人のお金の扱いがどうなるのかはニュースでは伝えていませんでした。
僕の英語はスキルは「ギリギリ最低限の日常生活がこなせるかもしれない」程度です。なので会議や会話の内容は半分ぐらい・・・いや1/3ぐらいしか聞き取れません。もっとも僕は正式な参加者でもなければ、ホスト委員会メンバーでもありません。ただのオブザーバーですから、後ろの席に黙って座っていればいいだけなので、聞き取れないのは個人的問題に過ぎません。分かんなければ分かる人に聞けばいいだけのことです。
現実の世界で話されている英語は、ニュースのアナウンサーや英語の教材のような耳慣れた(?)ものばかりではないという、当たり前の事実を痛感させられました。国によってあまりにも発音が違うのです(英語が母国語の国でさえ)。それは教材だって満足に聞き取れない人間にとっては、あまりにも高いハードルでした。「慣れるしかないよ」と言われたのですが、慣れるチャンスがない生活しかしてませんから。
発言権がないとは言え、休憩時間や食事中、あるいは交流会では別の国の評議員と直接話すチャンスはいくらでもありました。たとえこちらの言葉がたどしくても、そこは忍耐と寛容の精神で接していただいて、こちらとしては相手の回復に甘えるしかありません。ともかく最も高いハードルは、誰かをつかまえて会話を始める自分の勇気の不足なんですが、それは日本人相手の時でも同じことですね。
おかげさまで日頃抱えていた疑問のいくつかには答えやヒントが得られました。サービス会議だからオフトピックもサービス活動関連ばかりってわけでもなく、こちらが尋ねさえすれば、ステップやメッセージ活動やリハビリ施設の話も熱っぽく語ってもらえました。例えばステップ4の棚卸し表の書き方とか、スポンサーシップについてとか、「霊的」ってアジア圏のAAには障害にならないかとか・・・。
もちろん日本人同士でもたくさん話をしたのですが、その中でもある人の言葉がとても印象に残りました。もちろん、正確な言葉ではないですが、
「幅広いバリエーションがあるAAのやり方の中で、ある一部分のやり方だけが日本に伝えられて日本のAAになった。そのやり方が間違っているわけではないが、やはり偏っていることは間違いがない。どれが間違っている・正しいという議論は無用で、やはり様々な方法を持ってくることが日本のAAに必要だと思う」
その言葉を聞いて、僕は自分が漠然と感じていたものが明確な思考になった気がします。僕もそう思うようになった材料や、あまり関係のないことも含めて、思い出せる限りでAOSMの様子をぽつぽつ書いていきたいと思います。
AAの原理はAAの本が伝えてくれる。その原理は時代や国を超えて共通であり、変わることがない。変えようのない本質がそこにある。その一方で、そこに書かれた内容をどう解釈しようが各自の自由であり、メンバー一人ひとりの個人的体験や、スポンサー(や先ゆく仲間)から受け継いだ考え方・やり方も、それぞれ等しく分かち合う価値がある。繰り返し強調されながら、なかなか理解されていないことだと思います。
一つの原理を中心として、メンバーの数だけバリエーションがある。その広がりをそのまま受け入れるのが吉であって、どこかにこだわりを持てば失うものが大きい・・・ということでしょうか。
まあ、具体的な話はおいおい。
もくじ|過去へ|未来へ
