 |
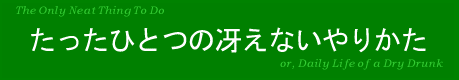 |
ホーム > 日々雑記 「たったひとつの冴えないやりかた」
たったひとつの冴えないやりかた
飲まないアルコール中毒者のドライドランクな日常
もくじ|過去へ|未来へ
2008年02月12日(火) 神さまの種類(掲示板から) 昨年、ソーバー数ヶ月のアメリカ人AAメンバーが2週間ほど長野に滞在し、僕のホームグループのミーティングに出ていました(当然彼は日本語が分からないのですが)。彼のスポンサーは大工さんで、ビル・Wの家の改装の時に床を張り替えたのだそうです。そして古い床材をもらってきて、その切れ端をスポンシーにあげました。
日本に来たそのAAメンバーは、ズボンのポケットから切れ端を出して見せ、「これが俺のハイヤーパワーだ」と言っていました。
もちろん彼の「神の概念」は変わっていくのでしょうが、とりあえず最初は信じられるものなら何でも良いのです。旅を始めるには最初の一歩が必要で、いきなり目的地に達することはできません。
ステップ2は「健康な心に戻してくれると信じるようになった」とあります。決して完全な信仰を持てとは言っていません。何かが「健康な心に戻してくれる」と信じるようになればいいのです。実はステップ2の難しいところは、神の問題ではなく、自分の心が健康(正気)かどうかという自問です。
ともかく、ステップ1の「アルコールに対する無力」と「自分の人生が手に負えない」ということがしっかり認識できていれば、ステップ2で「力のある誰かに何とかして欲しい」と思うでしょうし、そうすればステップ3で「じゃあ、言われた手順でやってみようか」という決心もつくのです。
飲んでいた頃のアル中さんにとっては「酒」が「自分より偉大な力」です。みんな飲んできた酒の種類は違っていたかも知れませんが、アルコールが入っているという本質はどれも変わりがありません。今度は助かる時にも、神さまの種類についてこだわりがあるかもしれませんが、好きな酒を飲んできたように、神さまだって好きずきで良いのです。
ステップ1がきちんとできていれば、神さまの種類なんてなんでもいいから「助けてくれ」という気持ちになるでしょう。神などという言葉が出てこないステップ1をしっかりやることで、神に関するこだわりからは自由になれますよ。
2008年02月11日(月) 違い 去年の10月から、ほぼ月一回ペースでAA関係で上京していたのですが、それもこの週末で一段落です。しばらくはAAイベントにも行かずに目の前のことをこなしていこうと思います。
この3連休はまとまった睡眠時間が取れず、今日こそゆっくり寝たかったのですが、子供の友達が遊びに来ていたので布団をひいて寝ているわけにもいかず、パソコンの前で半覚半睡で過ごしていました。
「経験の話のところでは、それぞれが自分の言葉、自分の見方で、いかに神との関係を打ち立てたかを述べている」第2章
「この本の個人の経験の部では、それぞれの語り手が、自分より偉大な力にどう取り組み、どう理解していったかをさまざまに書いている」第4章
かなり以前のことになりますが、病院メッセージに行って自分の順番が来て話をしたときに、「AAはあなたに何かを信じることを要求しません。神さまがお酒を止めてくれるとは信じていないメンバーもたくさんいます」という話をしました。いつもAAメンバーが話を終えた後は、時間の許す限り患者さんの話を聞くのですが、患者さんの一人が、こんなことをおっしゃいました。
「せっかくAAには神さまがあるのだから、AAは神さまを大事にして欲しい。信じなくてもいいなんて言わないで欲しい」
その人は年配の人だったので、ひょっとした断酒会の人だったのかも知れませんし、単なるひがみっぽい人だったのかも知れません。でも、僕はその言葉に衝撃を受け、深く感じるものがありました。
酒をやめたいという人が集まれば、そこに酒をやめる力が生まれる・・という理屈で集まるのであれば、ステップや神さまは不要です。この世の中には断酒会という素晴らしい組織があります。AAと断酒会を比べれば、確かに顕名・匿名、会費制・献金性、組織化・非組織化などの違いはありますが、それは表面に現れた違いに過ぎないと思います。本質的な違いは、スピリチュアルか、世俗であるかです。そこをあいまいにしてしまえば、AAがAAである意味が消えてしまいます。
霊性を大事にしないのなら、AAという看板を下ろして無名断酒会とでも名前を変えたほうがいいのです。いや、そんなことをすると「経験に始まり経験に終わる」という大原則を守れてないから断酒会という名前を使うな、と怒られてしまうかも知れません。あっちはあっちで厳しいのです。中途半端は何の役にも立たない・・・。
2008年02月09日(土) 餃子を作る人 家路のニュース検索に、餃子の中毒問題ばかりひっかかる状態が続いていました。
騒ぎをさらに加熱する日本のニュースメディアに業を煮やしたのか、中国の官僚が「日本はもう少しメディアを規制したらどうか」と注文をつけた、とこれまたニュースになっていました。
民主主義が機能するためには、報道メディアの存在が欠かせません。それはなるべく権力の受けないよう独立していた方が良いわけです。そうしておけばメディアは、統治機構とは独立した一種の権力を帯びます。とはいえ、報道メディアも単なる営利企業に過ぎなかったりするわけですが・・・、ともかく「独立性」というものは必要です。
アメリカでAAが始まってしばらくすると、ニューヨークに本部のオフィス(GSO)が作られ、そこへグループの献金が集まる仕組みが始まりました。AAのオフィスはサービス(奉仕)の機関であって、統治や支配をする存在ではありません。しかし、それにはある種の権威がありますし、金の集まるところに力も生まれるのは当然です。
GSOを作っていく過程とは別に、やはりニューヨーク在住のAAメンバーが「AAの雑誌」を作り始めました。これが AA Grapevine です。それが第二次大戦と同じ時期で、従軍する兵士たちの依存症問題に手を焼いていた軍が、対策としてこの雑誌を広く配ったのをきっかけとして、グレープバインはAAの雑誌としての地位を築いていきました。
オフィスがメンバーからの献金とビッグブックの売り上げで維持されたのに対し、グレープバインはその雑誌の売り上げで維持されていきました。今でもアメリカ・カナダのサービス機関は、GSOとグレープバインの二つに分かれています。
グレープバインは、AAメンバーからの投稿記事で成り立っています。どんな記事を載せるかという編集方針には、評議会と言えども(そしてオフィスも)口を挟めない仕組みになっています。決して、グレープバインがオフィスの権力(?)を監視するための報道メディアになっているわけではありません。けれど、AAメンバーの声が直接反映され、意見が広められる存在として、オフィスと独立したメディアを持つのは「民主主義の当然の知恵」でした。
日本にも「BOX-916」というAAの雑誌があります。発送やら集金やらの業務はオフィス(JSO)が行っていますが、編集部(編集委員会)はこれとは独立してボランティアのAAメンバーがやっています。そしてその編集権は「評議会といへども犯すべからず」という取り決めがあります。
輪番制とは言え一度引き受ければ2〜3年は毎月編集作業があるわけで、ボランティアの人たちは本当に大変です。だからそれは有給のオフィススタッフがやるべきだ、という意見もでています。しかし「独立した編集権」がAAの健全な民主主義の仕組みの一部であるからには、その編集権限をJSOスタッフや常任理事の人に任せるわけにはいかないのです。
まあ、民主主義なんて気にしない人達もいるみたいですが。餃子を食べながらそんなことを思ったわけです。
2008年02月08日(金) ベティ・フォードの自伝に学ぶ(その1) 「人は自分でできる範囲のことに直面し、明らかにされたことに対処できるようになるにつれ、より多くのことが明らかにされていきます」
〜『依存症から回復した大統領夫人』/ベティ・フォード
初めてAAミーティングに行った人の感想はたいてい「みんなが何の話をしているのかさっぱり理解できなかった」というものです。僕も初めてのミーティングでは、なんだか皆が大げさな話をしているようにしか聞こえませんでした。その部屋にいる人の大半はアルコール中毒者本人らしい、という感想だけを持って帰りました。
僕は最初の頃、ハンドブック第3章の「アルコール中毒者を正常な酒飲みにするようなものはない」という言葉に(内心)猛反発していました。二度と正常に酒を飲めない、という事実を受け止めることができずにいたのです。だから、その段階で「無力」だとか「狂気」だとか「ハイヤー・パワー」なんて聞かされても、受け止め得ない言葉は僕の中を素通りしていくだけでした。
その時点で、僕に分かったことは、ともかく毎週その会場に行く必要だけでした。
例えば、パンツの中にウ○コを漏らしたという話を聞いても、僕の心には何も浮かんできませんでした。自分が過去に同じことをしている事実に直面できなければ、思い出さずにおくしかありません。人の心はそうやって自分を守っているのでしょう。
僕は自分の自由な意志で酒を飲んできたと思っていましたから、酔って布団から起きられない僕を上から母が見下ろしている場面ですら、思い出すまいと努めていました。
自分は(飲んでいても、いなくても)人を傷つけ続けてきた、という事実に直面できるようになるまでは、ステップ4の経験談を聞いても、物好きな人の不思議な修行の話にしか聞こえなかったのです。
あれからずいぶん時間も経って、多少はいろんな事を理解し、事実に直面できている気がしているものの、おそらく「対処できないから見ないふり」していることは、まだまだたくさんあるのでしょう。ともかく「より多くのことが明らかにされる」まで、続けていくしかないのでしょう。
2008年02月07日(木) How to お願い 病院メッセージに行ったのですが、患者さんが誰も来なかったので、ホームグループの仲間4人で1時間雑談をしました。
さて、神さまに「あれやってください。これやってください」とお願いすることは、悪い信仰なのでしょうか? いえ、お願いをしてかまわないと思います。
たとえば、今度の学期末の算数テストで100点満点を取ったらDSを買ってくれる、とお父さんが約束したとします。そこで「どうかテストで100点を取れますように」と神さまにお願いするとします。でも、お願いやらお祈りさえすれば、100点が取れると思っている人は滅多にいないでしょう。
だから自分でも努力します。この場合には算数の勉強をするでしょう。でも、努力すればすべての願いが叶うと思っている人も滅多にいません。この世の中は自分の思うようにはならない、という現実は子供の頃から突きつけられるのです。テストに解けない問題が出ちゃうこともあるし、テスト当日に風邪を引く不運もあるかもしれません。
人は時に「すべては自分の努力次第だ」という幻想を持ってしまうこともありますが、いずれ大きな挫折や、あるいはうつ病などによって、現実的な考えへと修正を強いられる仕組みになっています。だってその考えに固執すると、失敗の原因はすべて自分の努力不足に帰され、もっと頑張らなくてはという悪循環から抜けられなくなり、生きることが苦しくなりますから。
努力という「自分の担当部分」と、努力ではどうにもならない部分(つまり神さま担当部分)が両方揃ったときに、うまく望みが叶う仕組みです。担当部分の比率がどうなっているのか僕にはよく分かりませんが。
お願いをするときには、自分も努力をすること、それと結果が悪くても神さまを恨まないこと、この二つの約束を一緒にすることが大切だと教えられました。
お酒をやめようと努力しても、ふと気が抜けて飲んでしまうことはあります。我慢の断酒には限界があります。だから再飲酒すると、つぎはもっと努力(我慢)してみるのですが、それでも飲むときには飲んでしまいます。失敗を繰り返すうちに、酒をやめられる自信が失われ、問題の否認(やめる必要はない)とか、責任転嫁(飲むのは誰かのせい)とかが始まってしまいます。
断酒という大きな責任を、すべて自分の肩に背負ってしまう(つまりすべてが「自分の担当部分」だと思ってしまう)のは大変です。重い荷物は神さまに預けた方が良いのです。
2008年02月06日(水) 不可收拾 ステップ1:私たちはアルコールに対し無力であり、思い通りに生きていけなくなっていたことを認めた。
歩驟1.我們承認我們無能為力對付酒精,而我們的生活已變得不可收拾。
「酒精」に対して無能為力であり、生活が收拾不可になっていたことを、承認。と言う感じでしょうか。中国語繁字体のステップ1です。
酒を飲んでいても、いなくても「不可收拾」な日々であります。
2008年02月04日(月) 雪かきならず よし、今日は会社の駐車場の雪かきをしてやるぜ! と気合いを入れて、長靴や手袋を持ち、防寒のために服の中にラッシュガードとスパッツも着て出かけたのですが、なかなか職場までたどり着けませんでした。
もう朝も遅い時間なのに、なぜ市内の国道が大渋滞しているのを不思議に思いながら高速の入り口まで行ったのですが、「事故通行止め復旧見込みなし」と言われて追い返されてしまいました。職場に電話してみたものの、誰もでません。雪のせいでまだ誰も来ていないか、みんな雪かきに出払っているのか・・・。
渋滞を避ける道を選んでいるうちに、お腹が痛くなってきました。田んぼの真ん中にあるデパートでトイレを借り、下道で行くのは無理と諦めて、そこで朝ご飯を食べながら事故処理が終わるのを待つことにしました。結局職場に着いたのはお昼過ぎ。雪かきはきれいに終わっていました。
さて、某掲示板で「新婚早々ダンナのアル中に悩まされる」という話を読んだりすると、身につまされることだったりするのです。どうしてあの時に妻が僕と別れなかったかと言えば、別れるのもそれなりに大変だったからなのでしょう。
「昔は断酒会でも、最後までダンナを支えるのが使命という感じの奥さんが多かったのが、最近では旦那さんが再飲酒すると、さっさと諦めて離婚しちゃう人が増えてきて」という話を聞いたのは、もう何年前だったか。
以前のAAホームグループに、旦那さんのアル中問題のために、奥さんが断続的に1年ほど通ってこられたことがありました。ところが旦那さんはいっこうに酒をやめる気配がないし、AAの僕らは「いかに酒がやめられなかったか」という話ばかりしていたのです。ある時その奥さんが、「お酒をやめることの難しさが分かりました。夫はいつかやめてくれるかもしれませんが、それまで彼の人生に付き合うつもりはありません。離婚することに決めました。だから、お医者さんも、AAも、もう用はありません」と言われて、それっきり来なくなりました。
僕ら一同「まさか、そんな結論になるとは」と呆然としたのですが、考えてみれば一番無難な選択なのかも知れません。
飲んでいようが、飲んでいまいが、アル中の旦那と暮らすのは大変なのです。いや、ダンナが酒をやめて、自助グループに通い、たとえステップをやったからって、その大変さが無くなるわけじゃありません。酒をやめた途端に以前の良い性格が戻るわけじゃありませんから。
その大変さにつきあえる能力を持った奥さんでなければ務まらないのが「アル中の妻」なんですかね。年間の結婚数が七十数万件、離婚数が二十数万件、とテレビでやっていました。「あの時あなたがお酒をやめなかったら、こうして夫婦でいることもなかったのに」と言われますが、実現しなかった選択肢と現状を比較されても困るよ。
2008年02月03日(日) 原因探し 統合失調症の家族の人にありがちな考えとして、病気になった原因を考えるのだそうです。この病気は破瓜(はか)の病とも言われ、思春期から20代にかけて発病することが多いのですが、その頃は人生の変動期でもあります。例えば、受験や就職に失敗した、失恋をした、友だち関係や金のトラブルがあった、というようなつまずきを経験する時期でもあります。そして、病気になった後で、受験の失敗や失恋のストレスが病気の原因だったに違いない、という考え方をします。
この考えには、じゃあその原因を取り除けば、病気も治るに違いないという願望が含まれています。もう一度本人が努力して受験や就職に成功したり、恋人や友だちに返ってきてもらえば、悩みも病気も消えてくれるに違いない、という願望です。
実際には、すでに病気が始まっていたからこそのトラブルだったかもしれず、因果関係が逆と言うこともあり得ます。
神経症みたいな心因性の病気では、原因を取り除けばけろりと治ることもあるのだそうです。うつ病でも、例えば会社を辞めたら治ったという話も聞きましたが、全般にはそう単純ではないようです。
アルコール依存症の人の話でも、「あれが原因だったに違いない」という病気の理由探しをする人がいっぱいいます。昇進に伴う仕事のストレスだったり、胃の手術だったり、経済的苦境だったり、家族内のトラブルだったり・・・。
「あれさえなければ、俺の人生はこうでなかったに違いない」
と思うのは勝手ですが、何の解決にもなりません。僕もずいぶんそういう考え方をしてきましたけれど、より飲みたくなるだけでした。もしそれがなかったとしても、別のことがきっかけになったことでしょう。
原因探しより、どうやって治療するかを考えた方がいいわけです。
2008年02月02日(土) 信じる力 人の恋路を邪魔する奴は、犬に喰われてと言われます。いやいやごめんなさい。「配慮の欠如」にチェック印です。月夜の晩ばかりではないので、野犬の群れに襲われないように気をつけますね。
さて、信仰心を持たない人のほうが珍しいと思います。
ついこの前のお正月に初詣に行った人は、おそらくお賽銭を投げて、なにかお願いをしたでしょう。家内安全とか、健康とか、お金とか、恋人ができますようにとか・・・。
で、でですよ。それは誰に向かってお願いしたのですか?
まさか、お願いが虚無の空間に吸い込まれて消えていくとは思っていませんよね。どこかに、あなたの願い事を聞いてくれる存在がいる、いるかもしれないと思うからこそ、お参りをするんじゃないでしょうか。
その存在(たぶん神様)は、あなたの健康運、金運、恋愛運その他を支配できる存在なんですよね。そういう力を持ってなければお願いしても仕方ないですから。それはあなたより「大きな力」、ハイヤー・パワーではありませんか? 信じる能力がないとか、信仰を持っていない人のほうが稀有なんです。自分のこれは信仰ではないと主張する人は、何か特定の宗教の信仰とは違うと言っているに過ぎません。
日本を訪れる外国人から見れば、神社に行くのも宗教にしか見えないそうです。知り合いの牧師さんの一家は神社に初詣には行かないそうです。結婚する二人がどんなに努力しても、それだけでは幸せになれるとは限らない、と思うからこそ、神様の前で三々九度をするのでしょう。
AAでは「自分で理解した」神を信じなさいと言います。それは信じられるものを信じることです。せっかく信じるのだから立派な信仰を持とうと思うと、信じることに失敗します。だって信じてないものを信じようとするから無理があるのです。
確かに、何かを叶えてくださいとお願いするだけの信仰心は、ちょっと子供じみている感じがするかもしれません。でも、それを出発点にして、信じる心を成長させるしかないでしょう。自分が今いるところから旅に出るのです。
自分には神様を信じる能力がある、と分かるだけで、とりあえず最初はそれでいいんじゃないでしょうか。現に信じているんだし。
2008年02月01日(金) 読み比べ ひさしぶりに大型更新をしました。
http://www.ieji.org/archive/warning-signals.html
今のところ最後の入院になっている県立K病院のケースワーカー室には、AAの本が何冊か置いてありました。そこで生まれて初めてビッグブックを見たのです。そのほか、AAのパンフレット類も何冊かありました。それはずいぶん古いもののようでした。
その入院中に「AAをやるんだ」という決意を固めたものの、病院からAAミーティングに行けるのは水曜と土曜日だけしかありません。だから、ワーカー室のAAの本を読んでみることにしました。・・・が、それが全然頭に入ってこなかったのです。
すでにアルコールで記憶力とか、集中力とかがぶっ壊れていたのに違いありません。仕方ないので退院後にゆっくり読めるようにと、AAのオフィスに初めて電話して本を注文しました。その時に、もう売っていない冊子があるということを知りました。もとがオタッキーですから、絶版とか入手不能と言われると、余計に欲しくなります。とはいえ、ワーカー室のAAの本を持ち去るのは、本屋で万引きする以上に悪いことのように思われました(比較の問題ではない?)。
というわけで、病院の事務室で文句を言われながら何十枚もコピーを取り、ホッチキスで製本したのであります。今回の更新ネタもその一つです。
ところで、ビッグブックの旧訳と、新訳を読み比べてみました。
比べてみると、新しい訳はとてもいい訳ですね。分かりやすい。旧訳も悪い訳ではないのですが、「われら不可知論者」「使用者たちに」「ボブ博士の悪夢」あたりは他の章に比べてどうも質が悪く感じられます。章ごとに訳すときの気合いのムラがあったんじゃないか、とか勘ぐってしまいます。3章、5章は名調子なのにね。
新しい訳は、前半にちょっと硬くぎこちない雰囲気があるのですが、後ろに行くにつれて丸さが感じられます。この柔らかさが前半にももっとあったらいいのに・・と思うのは贅沢でしょうか。
ちなみに、病院のケースワーカー室のAA本は、個人が寄贈したらしくその方の名前が書いてありました。まだその本があるか聞いてみたのですが、もう処分されてしまったそうです。
もくじ|過去へ|未来へ
