 |
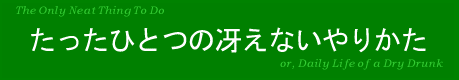 |
ホーム > 日々雑記 「たったひとつの冴えないやりかた」
たったひとつの冴えないやりかた
飲まないアルコール中毒者のドライドランクな日常
もくじ|過去へ|未来へ
2009年10月13日(火) 本人の望む以上には良くならない 人は望む状態と現状とのギャップを埋めようと行動します。
逆に言えば、現状が理想に近ければ、特に行動を起こす動機が発生しません。
前にアルコールで入院した病院に、ある患者さんがいました。
その人は酒の問題もあるのですが、すでに入院が年単位になっているので、アルコールの治療プログラムには入っていませんでした。主な病気は分裂です。が、そちらもかなり寛解していて退院に支障はなさそうでした。でも退院しない(できない)のです。
話を聞いてみると、奥さんと娘さんが「戻ってきてほしくない」という希望で、彼もそれを受けれいたのです。だから彼が退院するとすれば一人暮らししかありません。それは彼の希望ではなく(一人暮らしをいったん始めると家族との同居がさらに難しくなる)、入院し続けたいとすれば、あまり病気が良くなると彼は困ってしまいます。
そんなわけで、彼の病気は良くなりきらないのでした。
「精神の病は本人の望む以上には良くならない」
まるで上昇を拒むガラスの天井があるかのように、本人の願望が治癒を拒むことがあるのです。僕はアルコールをやめてもうつがなかなか改善しなかったときに、「治ることを望んでいない」と言われてずいぶん腹がたったものですが、実際その通りなのです。
病気が治ることは良いことばかりとは限りません。それによって失うこともあります。
例えば依存症が良くなるためには、酒を失わざるを得ません。精神安定剤で、気分が落ち着いてほんのりうっとりするのが好きだとすれば、病気が治ればその薬はもう飲めなくなります(それでも飲めば依存症)。病気だからと免除されていたいろいろなことも再開しなくてはなりません。
良くなろうと思わない依存症の人は、自助グループに行きません(それで周期的に再飲酒する)。他の病気でも、良くなるために医者や治療法や薬をイジってみる気にならなければ、悪い状態が維持されます。
治ることで得るものと失うものを天秤にかけ、治らないことを選択する人がいるのは不思議ではありません。損得勘定ができないのではなく、健康になりたい人とは価値観が違っているだけのことなのです。
2009年10月11日(日) 器質と気質 てんかんの人は統合失調症になりません(実際には少数なるけどこの際それは無視)。これはてんかんの人の脳と、統合失調の人の脳が違うことを示しています。
脳の違いによって、どんな精神病になるかも違ってきます。
病気になる前の性格(気質)にも違いがあって当然で、クレッチマーの分裂気質・循環気質・粘着気質という分類も、脳(器質)の違いが性格(気質)の違いに反映されていると考えてもいいかもしれません。
うつ病の人と、統合失調の人では、当然気質も違ってきます。それはリアルに接していても、ネットを介してでもわかります(つまり気質は演じることができない?) 本人は「うつ」だと言っていても、なんか違うなぁと思うことがあります。
以前に掲示板で「うつ病と統合失調症の比較」というページを紹介しましたが、あれは当を得ていると思います。
うつの人は、良心的というかあまりにも気遣いする感じで、会って別れたあとで「電車には間に合いましたか」とか「雨には降られませんでしたか」というこちらを心配するメールをもらったりします(それより自分のこと優先しろよ)。印象としては「いっぱいいっぱい」な感じで、そんなに頑張らなくてもいいのに思ってしまいます。わりと人間関係は豊富。
統合失調(分裂気質)の人は、気は遣うんだけどそれが「人のため」ではなく、自分がどう思われているか気にしちゃうタイプ。取り越し苦労が多くて、結果的に消極的。ひとりで行動するのが好きで、社交は嫌い。
分裂の人の印象は「固さ」と言う言葉で表現される思考の硬直化。どうして「盗聴されてる」って結論になっちゃうの? という感じで違う考え方ができません。そこまで極端でなくても、ちまちま節約してるのにドバーっと金を使っちゃうとかね。大きなことにこだわるならわかるんだけど、細かいことにこだわる。ひとりを好むのも、この「固さ」ゆえだと思います。
分裂気質の脳を持った人も、うつ症状になり得ます。そんな時に医者はうつの病名を与えます。でも伝統的なうつ病とはメカニズムが違うので、休んでも良くなるとは限りません。もし統合失調の陰性症状だと診断しても告知するとは限らないし、処方を聞いてみると抗精神病薬を飲んでいたりします(それが効くならうつじゃないだろ)。
なぜか世の中には「統合失調よりうつのほうがまし」という風潮(偏見)があるせいで、自分はうつ(あるいは躁うつ)だと思いたい人が増えています。それで不適切な治療をして良くならないのは不幸なことです。自分ではうつだと思っている人に、抗精神病薬を出して良くしちゃう医者は腕利きなのかも。
話は少し変わって、1年前の読売新聞に統合失調だと誤診されたシリーズをやっていました。ボーダーや広汎性発達障害なのに医者が間違えたという話でした。統合失調じゃない人に抗精神病薬を飲ませると副作用が強く出て、それが幻聴(陽性症状)、無気力(陰性症状)という統合失調の症状と似ていたりするので、話はややこしくなります。
それと最近は内因性の病気(伝統的うつ病や統合失調)が減っているという説もあります。代わりに増えているのが広汎性発達障害。なんでそれが増えたのか、食事の変化か、IT化のせいか、晩婚晩産化か。それで大人になった人たちが、うつや統合失調にカテゴライズされているという説です。
2009年10月10日(土) 説得者 「アルコールは偉大な説得者だった。アルコールはとうとう私たちを打ち負かし、正しい状態に叩き込んでくれた。だがそれはうんざりする道のりだった」(第4章)
午後は仲間とビッグブックの分かち合いをしていました。ちょうどここを読んだときに「そうなんだよね〜」とうなずきあった次第です。
AAのプログラムをやってみるように、誰かを説得するのは無理な話です。それは自ら選び取らなければなりません。まだ飲みたいとか、自分のやり方を試したいというのなら、ご自由にどうぞと言うしかありません。
ではなんで強制的にミーティングに通わされている人の中から回復する人が出てくるのか? 強制は意味がないのじゃないのか? このカラクリは単純で、最初は強制されていたものを、やがて自ら選び取るようになる仕組みです。
二ヶ月ほど前に仮スポンシーができました。最初の指示は二つだけです。毎日ミーティングに行くこと(AAがない曜日があるのでその晩は断酒会)、帰ったら電話をくれること。そんなわけで、我が家の電話は毎晩鳴るわけです。実際に彼がミーティングに行っているのかどうかは確認していませんが、電話が来ているうちは大丈夫でしょう。そこまでやっていれば、例え彼が飲んでしまったとしても、スポンサーとしては「それは病気だから仕方ないよ」と慰めの言葉をかけてあげられます。
(それをサボって飲んでしまったのなら、「ほらみろやっぱり」と言うだけです)。
もちろんこれを一生続けるわけにもいかないので、そのうち別のことを始めねばなりませんが、それはその時が来てからのことで、今心配することではありません。
かまやんさんの ブログ に野球の話が出てきて、昔僕も同じ話を聞いたのを思い出しました。
野球はボールをバットで打って、前に飛んだら一塁を目指すスポーツです。一塁に達したら二塁、三塁を目指します。それを、なんでボールを打たなきゃならんのか? なんで一塁に行かねばならんのだ、二塁や三塁をいきなり目指しちゃいけないのか? などと言っていると、みんなと一緒に野球ができず、ひとり淋しく過ごすかないわけです。
理屈はわからなくても全然構いません。本塁と一塁の間がなぜ約27メートルなのか、知っている野球選手がどれだけいるでしょう? あれに理屈はないのですね。それが「ちょうどよい」長さだったからにすぎません。同じように、仮スポンシーの彼にとって毎晩ミーティングに行くのが「ちょうどよい」というだけの話です。素直にミーティングに通っているから見込みがあるわけで、うだうだ言うようなら面倒を見ないだけの話です。
では、うだうだ言っているだけのヤツには、どう対応したらいいのか?
それは冒頭のとおり、説得を試みても時間の無駄です。放っておいて自分の好きにやってもらうしかありません。今飲んでいてもいなくても、いずれ「アルコールに説得され」ますから、その時に僕らが役立てるチャンスが来るかも知れません。飲まずに一生過ごせるなら、僕らの用はないわけですし。
放置プレーも立派な介入技法なんですってば。
2009年10月08日(木) 「自信」について 「ぼくは自分が指導者になったところを空想した。ぼくほどの統率力があれば、巨大な企業のトップでも務まる。絶対の信念を持ってうまくやれるはずだ」
「酔っぱらってくると、いまにきっと勝ってやる、という昔から持っていた固い信念がよみがえってきた」(第1章 ビルの物語)
自信については 以前にも書きました。
世の中の不公平に敏感である(「会社が病気に無理解なのが悪い」とか)、
小さな勝敗にこだわる(「俺だけ酒を飲まないのにワリカンかよ」とか)、
一人前扱いされないと気が済まない(「上から目線で見下されてる感」とか)。
こうした傾向は「自分に対する自信のなさ」から来ています。自信がないから虚勢を張り、虚勢を張り続けるから精神的に疲れ、疲れが無気力を呼び、それを「うつ」症状だと訴えます(でも、本当のうつではないから楽しいことはできる)。
自信のなさは時に人生まで変えてしまいます。例えば、酒のせいで仕事のトラブルを起こし、一時的にマイナスの評価を食らってしまった。努力を続ければ後日失地回復できるのは明らかですが、自信のない人は目の前のことにこだわります。「会社が俺を信用してくれない」とか「この会社にいても一生昇進の見込みがない」などと言って退職してしまいます。
自信がない人の夢は大きい。貧弱な自己像の裏返し(補償作用)です。ビルも大きな夢を描いていますが、誇大妄想狂だったわけではなく、単に自信がなかっただけです。そして、自信のない男にとって、酒の酔いの与えてくれるかりそめの自信、解放感、万能感ほど心地よいものはありません。
ではこういう人間が、酒で惨めになったから、今度は酒をやめれば楽しく生きられるでしょうか? 誰かが書いていましたが、「回復」とはいうものの、元々持っていない能力は取り戻しようがありません。酒をやめても元の虚勢と緊張の状態に戻るだけです。
だから、単に酒をやめるだけでなく、自分を変えることもしなければ、本当の意味で酒をやめたことにはなりません。酒による解放感を必要としているうちは、ガマンの断酒が続きます。元々ガマンができない性格なので、ガマンの断酒は長くは続きません。
では、どうしたら自信が持てるのか? 自分で決心すれば自信が持てる、ってわけにもいかないのです。
いろいろな手法が考えられますが、例えば「失敗したところにとどまって、小さな成功をする」ことは肝心です。テニスで失敗した人が、サッカーで成功しても、テニスに対する苦手意識を克服することはできません。女性が苦手な男が、同性愛に走っても、女性に対する自信を得ることはできません。
元々(テニスや女性が)苦手な分野だったのですから、踏みとどまって努力しても大きな成功は望めません。でも小さな成功(女性とデートできただけでも、テニスのボールが前に飛んだだけでも)を得られれば、それは自信の土台になります。その人にとって失敗の意味合いも変わってきます。
だから、失敗した場所から逃げない、ということは、断酒継続にとって大事なことなのです。仕事で失敗したことは、仕事で取り戻さなければ意味がないし、別の仕事に移ったところで、自分が変わらなければそこで同じことの繰り返しです。
自分を変える(問題を解決する)ことが、断酒の「手段」であることを理解していただきたいのですよ。
「自信が持てない」―現代の「ウツ」に潜む悩み
http://diamond.jp/series/izumiya/10020/"
2009年10月06日(火) 新時代の日本的経営の反省 製造業に関わっていると日々実感するのですが、日本でモノを作ることはとっても高コストです。だからといって、工場を海外に移転するのも簡単ではありません。現地情勢や為替の変動リスクがあるからです。まして、モノではなくサービスを提供する企業は「海外で作って日本で売る」というわけにはいきません。
何が高コストかと言えば、何もかも高コストなのですが、中でも目立ってしまうのが人件費です。例えば日本とアジア諸国では、人件費が30倍、100倍と違います。日本が高すぎると言うより、向こうが安すぎるんですけどね。まあ、それはともかく。
20世紀の日本では終身雇用かつ年功序列が主流でした。1980年代から、アメリカ式の能力主義とか転職がもてはやされていたものの、家族的経営主義はなかなか変化しませんでした。そのように企業が従業員家族の生活保障を背負っている状況では、人件費を下げたくても、なかなか賃金カットはできません。
それを変化させたのが、1993年の平岩レポートでした。これは経団連の会長だった平岩氏が細川首相の諮問に答えて提出したレポートで、バブル崩壊後の経済再建のために旧来の様々な規制の緩和を訴えました。その中に、「参入しやすく、転職しやすい(柔軟な)労働市場を形成する」という一文があります。
さらに1995年には、日経連が悪名高い「新時代の『日本的経営』」というレポートを出し、従業員を三つのグループに分けることを提唱しました。正社員グループ(管理職総合職の終身雇用昇級有り)、契約社員グループ(専門職の年俸制有期契約、昇級なし)、そしてパートや派遣のグループ。従業員カースト制度みたいなものです。
実際1996年頃から、企業は「リストラ」の名の下に人件費の圧縮を進め、政府もこれを後押しする政策(たとえば1999年全業種への派遣解禁)を取りました。小渕内閣の財政出動によって景気は好転し企業は潤ったものの、(民間の)給与所得は減り続け「実感無き景気拡大」がその後も続きます。(最後にはリーマンショックによって「仕事があるだけまだまし」状態になってしまいます)。
こうして、新しい日本的経営によって「労働力の弾力化・流動化」が進められた結果、貧困は拡大し、国内市場はますます冷えてしまいました。結局企業にとってもいいことはなかったのです。
ここまでが前説。戦後の一時期を除き日本の自殺者数はずっと2万人ちょっとでした。これはバブル崩壊の時も増えていません。ところが1998年にぴょこんと3万人を突破し、その後そのまんまです。
また、自殺者数の年齢別グラフを作ると、男性では20代と高齢者が多く、子供と中年が少ない「N字型カーブ」を描いていたのですが、近年では中年男性の自殺が多い山形グラフになっています。完全失業率と自殺率の年次推移グラフには両者の相関が見られます。生活苦で自殺を選ぶのは中年男性ということです。
国民新党の亀井君が、家族殺人が増えているのは企業の責任と言って物議を醸しました。政治の責任のがれという感じもしますけどね。十年ほど前に「これから日本では犯罪が増える」と予言した人がいました。現状は(日本的)持てる人々がノブレス・オブリージュを放棄した結果だとも言えます。
今年の自殺者数のデータは来年にならないと出ませんが、今年から月ごとの数が発表されており、去年より増えたことは間違いなさそうです。
鳩山君の友愛政治に期待しますか。
2009年10月04日(日) 中川君の死に思う 中川元財務大臣が亡くなったニュースが流れています。
脱穀の作業中に、仲間からのメールで知りました。
もうろう会見の後に大臣を辞任、総選挙を迎えるに当たり周囲の勧めもあって断酒宣言。しかし落選後は再び飲むようになり、不眠を訴えて薬をもらっていたそうです。死因は循環器系の異常(アルコール性心筋症)だとか。
彼の死を「酒飲みがまた飲んで死んだ」で片づけるのは簡単です。
アル中は飲めば死ぬのですが、自分は例外だと思っている人は意外と多いものです。
AAメンバーでも「自分がスリップ(再飲酒)することがあっても、その時はもう一度AAでがんばります」なんて真顔で言う人がいます。飲んで生き残れるとは限りませんし、命までは取られなくてもAAに戻ってこられるとは限りません。
今の気持ちが「飲んでも戻ってくる」であっても、飲んでしまえば違うことを考え出すわけですから。
実際、AAで何年かやった後に飲んでしまって戻ってこない人はたくさんいるのですが、自分はそうなるとは思いたくないものです(でも可能性はある)。
今回得ているソブラエティが、自分の優秀の証明のように思うのは間違いです。断酒できたのは運が良かったからで、自分が優れていたからではない、という真実に目を向けるのは嫌なものですが、それをしなければ今のソブラエティを大事に守っていこうという気にはなれないでしょう。
もう10年くらい前のことです。ミーティングで司会を頼まれて、どんなテーマでもかまわないと言われたので「今度飲んだら死ぬかもしれない」というテーマにしたことがあります。その時10年以上のメンバーから「自分の場合にはそれはないと思う」と言われて、驚きました。
今度飲んだらやめられずに死ぬまで飲み続けるかもしれないのです(というか、その可能性の方が高い)。いつでも、何度でも手にはいると思うからこそ、人はソブラエティを粗末に扱います。
アル中には飲んでいる期間と、やめている期間があります。飲んでいる間に起こしたトラブルが自分の人生をダメにしたと思っている人は多いのですが、やめている間にやったこと(ソブラエティを粗末にしたこと)のほうがはるかに影響が大きいわけです。
2009年10月01日(木) 加害者性の獲得(その3) 暴力は被害者意識から発生する。
例えば神戸の震災の後性犯罪が増えました。地震という自然の暴力にさらされた影響が、自分より弱い者への暴力となって表出したのです。もちろん被害者意識が暴力を生むという図式は、暴力の一面をとらえているにすぎないのですが、DVの状況をよく説明してくれます。
人間は自分の理想とする状態と、現状とのギャップを埋めようと行動します。DV夫が妻に対して被害者意識を抱くのは、妻の行動が彼にとって望ましくないからで、その状況を修正するために暴力という手段に訴えるわけです。
それはちょうどアル中が、周りの人の行動が彼にとって望ましくないために、被害者意識から恨みをいだき、状況を修正するために相手を傷つける(迷惑をかける)行動に出ている図式とぴったり重なるわけです。
その行動様式からは想像しがたいことかもしれませんが、DV夫は妻と仲良くできることが理想だと思っており、アル中も周りの人と仲良くやりたいと思っているのです。しかし被害者意識を基盤に行動を決定している以上、彼らは不適切な行動を選択し続けます。
DV加害者プログラムでは、被害者意識の発生する個々の場面を想起し、そこにどんな信念が働いているか明らかにしていきます。被害者意識は彼の理想の実現に何の役にも立っていないことが明らかになっていきます。
AAのステップ4・5における棚卸しでも(ビッグブックのやり方では)、恨みを抱く相手との個々の場面の中で、自分が不当に扱われたと感じる仕組みを探っていきます。自分の満たしたい欲望(社会的、身体精神的、性的)が制限されたときの自分の反応パターン、そして代わりにどんな感情・行動が適切だったかを知っていきます。
どちらも、当人の行動とは裏腹に、心の中では仲良く平和にやりたい願望がある前提です。良くなるためには良くなりたい願望が必要なので、当然の話なのですけど。
被害者意識は不幸な状況の原因を他者に求めます。なぜなら被害者は正義だからです。しかし認知行動療法では、状況修正の責任は自分にあるわけです。
反省、あるいは被害者性を通じた他者の痛みへの共感という、どちらかといえばマイナスの感情を動機とするよりも、幸せになりたいという正の動機に基づく行動が評価を得て強化されたとき、人は(比較的)短期間に変わりうるのだろう、そんなことをシンポジウムのあいだじゅう考えていました。
そして個人的な経験をふまえれば、より深い反省は「変化が起きた後でこそ」可能なのであって、深い反省が深い変化を引き起こすわけではありません。
昔からAAでは言ったものです。「あなたの言葉も信じない、あなたの涙も信じない。ただあなたの行動だけを信じます」。反省の言葉や涙が、本当に心の奥底からのものであっても、それが何のあてにもならないことは、経験的に知られていたのです。
2009年09月30日(水) 加害者性の獲得(その2) 本社に出張だったので、電車の中でアミティの本を読んでいました。
アミティはシナノンの分派です。アメリカの薬物治療施設として時代を築いたシナノンは終盤にはリーダー達が変節してカルト化しました。それを嫌っていろいろな分派ができたのですが、アミティもその一つで、いろいろな依存症だけでなく、習慣的暴力なども扱っています。
アミティのプログラムの根底は、加害者における被害体験です。DV夫、子供を虐待する親、性犯罪者などには、過去に性的被害を受けたり、子供のころに親から虐待された経験があります。すべてのケースではありませんが、何割かにはこの図式が成り立ちます。暴力が伝染病のように伝搬していく図式です。アミティのプログラムでは、その経験を具体的に掘り起こすことで、被害者としての意識をまず確立し、それを基盤に自分の加害による被害者の痛みを追体験し、自分の加害者性を獲得させます。
つまりいったん被害者性を構築し、それを元に自分の行為の加害性認識につなげる方式です。
ところが信田さんの話では、カナダのDV加害者プログラムでは、この方式を採用していないのです。問題点ふたつの指摘がありました。
一つは時間がかかりすぎることです。前にも書いたように、心の痛み(反省)では人は変わらないし、変わるにしても時間がかかります。その間も家庭内で被害者がDVを受け続けるなら、それはDV加害者プログラムの目的を果たしていないことになります。
もう一つは、(これも書きましたが)DV加害者はもともと自分を被害者だと考えています。そんな彼らに「俺も被害者なのだ」という意識を与えると、それをいま自分がやっているDV加害の免責理由にしてしまうからです。そうやって責任を逃れれば、変わろうという動機も失われます。
依存症の場合には、プログラムに時間がかかるとしても、病気の苦しみが本人に変化の動機を与え続けてくれます。飲み続けていれば、仕事や金や信用を失っていきます。ところがDV夫の場合には、(社会で受けたストレスを家庭内で発散しているわけですから)仕事が順調で、社会的な地位も保たれ、人間関係も趣味も充実していたりします。本人が苦しんでいないので、(妻の犠牲のもとに)変化をいつまでも先延ばしし続けることが可能です。
そこで刑事罰を与えることで、強制的に変化の動機を与えることも必要になってくるわけです。ほかの先進国ではDVは親告罪ではなく、現場に踏み込んだ警官がDVだと判断すれば夫は逮捕されます。ところが日本では、妻が親告しなければなりません。夫と同じ家に帰る妻に、それができるかと言えばノーです。
結果として日本では刑罰ではなく、妻が家を出たり、離婚の請求というのが、夫が加害者プログラムにつながる動機になっているとのことでした。DVのある環境の元で、夫が変わるために妻が行動を起こす必要がある・・・酷な話だと思いました。
明日もまだ続くかも。
2009年09月28日(月) 加害者性の獲得 DVの話の続きです。今の僕の目標は、この文章をさっくり30分でまとめることです。
覚醒剤や麻薬の常習者を刑務所に入れて懲役させるだけで、出所後の再犯防止が実現できるでしょうか? 答えはノーです。精神病院に入れても酒をやめないアルコホーリクを、刑務所に入れても酒はとまらない。それと同じことです。のり塩スキャンダルでは警察の取り調べばかりが注目されましたが、本来であればどうやって再発を防止するかが問われなければなりません。(けどまあ、ダルクなどの治療施設の名前が出ただけでも良しとしますか)。
依存症治療の歴史を読んでいて鮮明になったことは、飲むのをやめる(断酒のきっかけ)に必要な動機と、やめ続ける(断酒の維持)に必要な動機は異なる、ということです。
きっかけは心理的な興奮によって実現します。例えばアジ的な演説で人の心を動かすことができます。何らかの強制でも可能です。要するに何かショックなことが起これば、人は過去と我が身を振り返って自分が変わろうと決心をします。
しかし決心に基づいた行動を続けることはなかなかできません(三日坊主)。興奮(あるいはショック)は長続きせず減衰してしまうからです。アル中さんを説教して反省を促し、酒をやめさせることは可能でも、断酒を継続させることは難しい。刑罰的な処置によって薬物の再犯防止が防げないのも同じことです。
真実はシンプルで「人は反省によっては変化しない」というわけです。
信田さんの話でも、DVの加害者プログラムでは、本人と対決的にならず、責めず、動機付けをして肯定的に支援することが大事だと強調されていました。この考え方はカナダのDV加害者プログラムの実績に基づくもので、実はそのプログラムはカナダの性犯罪者の再犯防止プログラムを母体として生まれました。カナダは性犯罪の再発防止では最先端で、信田さんのブログにもカナダに研修に行った話がありました。
過去ではなく、現在やっていることの肯定的側面を強化する。認知行動療法にはそれが有効です。このように加害者がある意味「褒められる」ことに対して、被害者側にはたまらん気分もあるでしょうが、この考えは被害者の安全を確保するために(DVでも性犯罪でも)加害者の変化を最優先した結果だとありました。
12ステップの棚卸しも反省のためにやるわけではなく、そういう興奮から離れて自分の心の動きを冷静に分析することが目的です。棚卸しがうまくいくためには、スポンシーが涙をうるうる流しながらでは困るのです。自分の加害者性とは冷静に向き合ってもらわなくてはね。
もちろんプログラムの目的がアカウンタビリティ(説明責任)、謝罪や賠償、再発の防止である以上、当事者にとって(例え褒められても)プログラムが心地よいなんてことはあり得ません。
週に一回のペースで12回。これを1クールとして、変化を起こすには数クールは必要だそうです。するとDV加害者が変化するには最低でも1〜2年は必要でしょうか。
さて、では刑事的な処罰は必要ないのか? むろん必要であって、加害者意識ゼロの本人をプログラムにつなげるためには、刑罰によって社会的な圧力を加えることが必要で、今の日本ではその法整備が進んでいないことが問題だという話もありました。
日本では加害者プログラムはまだ数カ所でしか行われていません。東京4、名古屋・京都・北九州各1。
まとまらない文章ですが、30分経ったのでこれで終わりにします。
明日は気が向けば、加害者性獲得について、別のことも書いてみたいと思います。
2009年09月27日(日) DV夫と加害者性、依存症と当事者性 渋谷の國學院大學まで、社会病理学会の公開シンポジウムを聴きに行きました。(テーマは「中高年男女の生きにくさ」)
シンポジストのひとりは信田さよ子先生で、これが目当てだったわけですが、残りの二方が学会所属の社会学者でマクロ視点から自殺を取り上げたのに対し、信田さんは臨床家としてDVを論じたのが対照的でした。
参加者の数を数えたら四十数人、これはかなり寂しい数字だと思います。そして人が少ないとネクタイを締めていない僕は目立つので嫌なのです。それはともかくとして。
おそらく社会学者にとってDVは専門外だからという理由で、信田さんの話は前説が長くなりました。おかげで介入手法についての話がざっくり略されたのは残念でした。僕にとってもDVは専門?外なのですが、話を聞いて依存症との類似点をいくつか思いついたので、メモ代わりに書いておきたいと思います。それは、DV加害者更正プログラムと、依存症の回復プログラムの類似性とも言えます。
DVには加害者(夫)と被害者(妻)がいます。
ところが暴力をふるう側は「妻のせいでこうなった」という被害者意識に満ちています。妻が「でもだって……」と口答えばかりして、夫の気に入ったようにしてくれない。あげくに具合が悪いと言って家事をサボる。夫として「妻にきちんとしてほしい」という愛情ゆえに、つい暴力に訴えてしまう。だから悪いのは妻だという理屈です。
一方妻の方は、私が至らないから殴られるのだと、自分の責任だと思う=加害者意識があるわけです。こうして支配の仕組みは深まっていきます。
このように加害者と被害者が意識の上で逆転している状態で、DVの原因(というか発端)を探っても問題の解決になりません。自分は被害者だと思っている夫が、加害者であることに気づくことが大事です。そのためにはDVそのものに焦点をあてる必要があるという話でした。
発端ではなく現状に焦点を当てる必要があるのは依存症も同じです。依存症の本では、この病気が primary disease だということが繰り返し強調されます。日本語では「原疾患」。
例えば糖尿病を治療しないでおくと、視力が低下し最後には失明します(糖尿病網膜症)。ここで網膜症の治療だけで、糖尿病の治療をしなければ、いつまでたっても良くなりません。原疾患の治療が大切です。
依存症はそのものが原疾患で、「依存症になった原因探し」をしても意味がありません。発端ではなく現状を解決することが大切だからです。しかし本人は酒が primary な問題だと認めたがりません。
例えば親がアル中で(AC)本人もアル中という場合です。その生きづらさが親に源を発していることは疑いがありません。だからこそ酒を飲むことも必要だったのでしょう。でも結果として親と同じアル中になってしまった。
ここで人は、アルコールの問題ではなくACの問題に焦点を当てたがります。まるでACが糖尿病で、アル中が網膜症であるかのようです。でも原因探しをしてもアルコールの問題は解決しません。もはや依存症そのものが primary な問題になっちゃったからです。
だから酒の回復を3年ぐらいやって、安定してからACの問題に取り組むのが基本です。それには「親のせいでこうなった」という被害者意識を一時凍結して、アルコールでの自分の加害者性に取り組んもらうしかないのですが、なかなかそういきません。被害者意識というお茶は甘くておいしいのです。
そして、いくらACの問題に金と時間をつぎ込んでも、途中で酒を飲んだら台無しだということに気づいてはもらえません。
フロイトに端を発する精神分析は、20世紀のアメリカで大流行しました。当然それを依存症に応用する試みがなされました。でも成功することはなく、1960年ごろに精神分析医は「反抗的な」アル中の相手をすることをやめてしまいます。彼らの敗因は依存症になった「原因」を探して解決すれば、酒の問題も解決すると信じたことでした。
仕事のストレスで酒を大量に飲んでアル中になったとします。仕事を辞めれば、酒の問題も収まると考えがちです。でも、最初は確かにストレスのせいで酒を飲んでいたかもしれませんが、途中から「依存症だから」酒を飲むようになっていたのですから、仕事を辞めても酒は止まりません。かえって経済的に困ってしまうだけです(困った方がいい場合もあるけど)。
うつ病から依存症に移行した場合にうつを治療しても酒が止まらないのも同じ理屈です。
DV夫が加害者性に目覚めることの難しさ。これは依存症本人が、12ステップでいうところの「性格上の欠点」とか「自分の側の問題」に気づくことの難しさに通じると思います。どちらも被害者意識を捨てることが必要だからです。
AC、依存症、DV、いずれでも原因探しをして他者の責任を追及することは、解決につながりません。ACでも親の影響を直視することはとても大事です(アル中が酒のことを直視するのと同様に)。が、その上でさらに、その結果自分がどんなに「困ったちゃん」になってトラブルを作ってきたか、そういう加害者性を見なければ、「そんな自分を変えていきたい」という動機が生まれず、回復につながりません。
そんなふうに、AC、依存症、DVはお互いよく似ているのです。まあ親戚みたいなもんだし。たいてい同居していますしね。
(つづくかも)
もくじ|過去へ|未来へ
