
「俺大卒ニートだけど 本当に社会は相手にしてくれないし欠陥品だよ。」
「普通に全国のニートに向かって名誉毀損だろ。 」
「有無を言わさず正論だろ・・・ 常識的に考えて……」
「なんとかなったけど、どうなんだこの大学は奴隷になれと?」
「じゃあ、フリーター、ニートになれと??」
「新卒逃すとそうそうチャンスは来ない。ってか暗闇。後で苦労するし」
「働くのがえらい?バカも休み休み言って欲しいですね。」
「 金が無いから働く。これだろ。」
ご存知の方もいるかもしれません。
近畿大学HPの
「就職活動は君一人の《孤独な》戦いです。
勝利を得るまで、人知れず何度も何度も立ち上がって挑戦です。
幼稚園-小学校-中学-高校-大学…何度も苦しいことがありました。
そして、いよいよ仕上げです。
最後です。
人生の方向を決めるのです。
『新卒』のやり直しはできません。
浪人はありません。
2度とチャンスはありません。
フリータやニートになっては、人生台無しです。
復帰できません。」
という記載に対する2ちゃんでのスレッドです。
20年前ならどういった反応があったのか気になるところ。
音楽:『Dark Horse.m』(Amanda Marshall)
写真:『中身なし』(東京都豊島区北大塚2丁目にて)

ジェームス・ヒルトン『失われた地平線』に出てくる理想卿。
中国では香各里拉という表記。
チャットモンチーの曲も有名ですね。
PVがめちゃかわいい。
元気になれます。
音楽:『Time of the season』(Ben Taylor Band)
写真:『ここにいるよ』(長野県松本市大字入山にて)

パソコンを整理していたら出てきた。
いつ保存しておいたかもわからない誰かの執筆。
今後のために貼り付けて読み返そう。
以下転載
高齢者は75歳を境に前期と後期に分断する。
いかにも機械的な発想である。
お役所流のご都合主義としかいいようがない。
現実にこの年代を生きている人たちの実感とは、かならずしも一致しない。いうまでもなく、それぞれの人生の生き方は別の問題である。
美術家の横尾忠則は、古稀を迎えてひとつの決断をした。
それは新著のタイトル通り『隠居宣言』(平凡社新書)であった。
「自由を獲得するための自己革命である」
わざわざ宣言しなくても、だれでも老人になる。
隠居は違う。
覚悟をきめて嫌なことはせず、好きなことだけをする。
そのためには、自分の限界を知らねばならない。
いわゆる「生涯現役」よりはるかに前向きで、
勇気のいる生き方なのである。
隠居と聞いて私は、落語の登場人物を思い浮かべる。
横丁の長屋あたりに住んで、悠々と暮らしている。
熊さんや八っつぁんの話相手にもなる。
隠居はヒマとは限らない。
江戸の広重や北斎は会心作を描いた。
伊能忠敬は隠居後に全国を歩いて正確な日本地図を完成させた。
こうした日本人の伝統的な価値観を評価したのは小林秀雄である。
還暦の60歳を迎えたとき、名著『考えるヒント2』で語った。
「還暦といえば、昔はもう隠居である」
隠居は隠遁ではない。世間を捨てて田舎に引きこもることではない。
古人の言葉の通り「大隠は市に隠れる」のである。
小林の自覚は、横尾より10歳早かった。
この差こそ昭和と平成という二つの時代のギャップを映し出している。
現代では隠居になりたくても、なかなか念願をかなえられない。
加藤秀俊は大学の公務から解放されたとき、75歳になっていた。
「やっと夢に見た自由な立場になった」
解放感からまず執筆した著書が『隠居学』(講談社)である。
隠居についての学問ではない。
隠居による自由な学問のはじまりであった。
「某月某日。知り合いから〈韃靼そば茶〉というお茶をいただいた」
お茶をすすりながら、知的な好奇心が湧いてくる。
司馬遼太郎の小説を思い出し、そこに登場する武人について調べ、
内藤湖南の歴史書をひもとく。
このように、つぎからつぎへと連想をひろげていくのは楽しい。
その気になれば、森羅万象、世の中は面白いことだらけである。
実は隠居学には極意がある。
著書のあとがきで、加藤は手の内を明かした。
「誰か目の前にいる人に、お喋りをしているような気分で筆をすすめた」
そういえば、横尾の宣言本はインタビューに応じた対話集である。
小林の場合も、あのエッセイと同じ内容を講演で語っていた。
ご隠居さんには、やはり聞き役が欠かせないらしい。
おかげで、私たちは愉快に熊さんや八っつぁんになれる。
音楽:『The Reason』(Hoobastank)
写真:『佇まい』(京都市南区吉祥院石原堂ノ後町にて)

川俣正という人の講演会みたいなんを聴きに行きました。
色々メモ取ったんやけどずっとそのままで。
だから備忘録として書いておきます。
芸術を学問しない
これは講演会前に同志社大学のセンター長か誰かが、
「芸術の歴史はうんぬんかんぬん」言ってたので、
始めからこんなんかよって思って書いた僕の心の嘆きです
「足すことも引くこともできない」
ある方が日本の伝統文化についてこう言ってはりました。
たしかにそうやし、そうでもない。
それよりの進歩はもうないってこと?
「場所から成立するART」
リボンの似合う風景→方法論
「西洋はシンメトリック、日本はさにあらず」
襖一つで芸術→目の動線を考えて閉める部分と開ける部分
「問題提起だけなら小学生」
自分なりの答えや考えをもつという権利と義務
京都=日本 日本=京都
個人的にはそういったステレオタイプな考えを風刺したい
京都人の京都らしくないところ
京都人が京都人ぶってるところ
「もっと長く見て欲しいから座布団を置いた」
「立って見える景色と、座って見える景色の違い」
「特別な場所や時間を作り出す」
「観客はそれをどうみるんだろう?」を考える
すごいシンプルなアイデア
でも斬新やし本質を捉えてると思う。
「ブリューゲルは200年忘れられ、時代がその時彼を求めた」
作品とはその人ではなく何を作って残したのか
→人間として見た場合はそれと全く逆だと僕は思う。
自分の言葉に責任を持つことと固執することは違う
ある方の発言がすごく耳に残った。
それは嫌悪感に結びつくものだったけど。
「言葉を解体する」
同じように音楽も分解することができる。
音楽:『There will be love there』(The Brilliant Green)
写真:『なぜならば』(東京都中央区銀座6丁目にて)

「今日はやめとく?」
っていう言葉にどんな裏側があるのか。
自分の意思がないために相手に決断を委ねるのか?
自分が乗り気でないので相手の賛同を導く問いかけなのか?
自分の意思は別にして、相手の状況を心配しての言葉なのか?
自分から嫌われものになれる人はすごいと思う。
でもそれを自分で気付いていてやるのも違うと思う。
知らんフリしてんのもずれてる。
音楽:『cancer for the cure』(The Eels)
写真:『今日はやめとく?』(北海道札幌市中央区南四条西4丁目にて)
| 2008年11月15日(土) |
鉛筆振りながら残り時間を削る |

システマティックにおもしろいことを考える。
Aという事象に対して
Bをひっつけてみて
Cとの共通項を
Dという観点からまとめる
そんな方程式を考えています。
俳句も同じ。
まずは5を分解する。
1・1・1・1・1
1・1・1・2
1・1・3
1・4
2・1・1・1
2・1・2
2・2・1
2・3
3・1・1
3・2
4・1
5
一番上の1・1・1・1・1なんかは
「手と手と手」とか「陽を芽と枝」など。
そんな90度の積み木みたいな試みです。
出てきた素敵な答えや建物が同じような顔にならないように。
それが一番大事な部分だと思います。
音楽:『You're beautiful』(James Blunt)
写真:『そのまま通過』(東京都港区新橋2丁目にて)

コ←п←C
音楽:『Monochrime』(Lush)
写真:『回れ』(香川県香川郡直島町積浦にて)

今まで老いを感じたことがなかった。
いつかやってくるものだろうと思っていた。
それは年を重ねるにつれゆっくりと。
ぼんやりと30歳くらいから近づいてくるものだと。
いや、近づいていくものだと考えていた。
それが突然やってきた。
ある日突然。
その日は、年老いた気分を感じる目覚めだった。
小学校4年生くらいに一度同じような経験をした。
それはたしか日曜日の朝で。
昨日の夜から10時間くらい寝た次の朝だった。
天井が昨晩に比べてうんと近くなっていた。
その一回だけ。
おそらく身長も変わってなかったと思う。
ただ、そんな思いを抱いたのはたしか。
何かきっかけがあったわけでない。
心の問題だと思う。
危険信号とも取れるし、実際にそうだと思う。
とりあえず書き留めておきたかった。
音楽:『Time to pretend』(MGMT)
写真:『黒い猫』(福井県あわら市温泉4丁目にて)

絵描きにとっての白色と黒色。
白に向かうたくさんのチューブは空っぽになって。
黒に向かうほんの少しのチューブはまだまだ使える。
僕は黒い絵の具しかもっていないから、夜の絵ばかりを描いてる。
それしかできない。
明るい絵を描いてみたい。
音楽:『The magic position』(Patrick wolf)
写真:『黎明』(大阪府高槻市大手町にて)
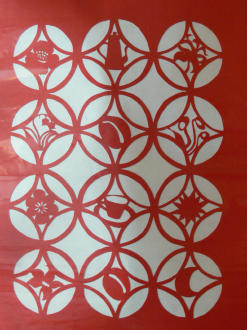
11月11日ということでポッキーの日。
今年は買いませんでした。
それどころか和菓子について書きます。
京銘菓とは季節感を和菓子で表現したもの。
以前サークルK限定で販促物もありました。
鳴海餅の三色団子
出町ふたばの名代豆餅
鍵善良房のくずきり
中村軒の麦代餅
甘春堂の茶壽器
麩嘉饅頭
すいません。用を足してきます。
また今度。
で、これがほんとの御用達。
ちゃんちゃん。
音楽:『Wave goodbye』(Steadman)
写真:『粋』(北海道札幌市中央区北一条西1丁目にて)
|