| 2019年09月02日(月) |
「週末の寝だめ」は医学的にNG |
昨日の続きです♪
──「サザエさん症候群」とよく言われますが、日曜夜に憂鬱にならないために、週末はどうやって過ごすのがよいですか?
よくやるのは、週末に寝だめする、という方法ですが、実は寝だめに効果が乏しいことは、医学的にもわかっているんです。
まあ、人によっては月曜くらいまで多少効いても、火曜日以降はほとんど期待できません。
だから、実は週末にまとめて寝てしまうことは、とてももったいないことなんです。
だから、さっきの昼食の話ではないですが、やはり逆算方式で、週末に趣味や家族・仲間との時間を「あらかじめ」捻出しておく。
そうすることで週末を寝だめに費やさないようにする。
平日、無理な仕事の仕方をして睡眠を削り、その結果、週末を寝て過ごすよりも、土日も平日と同じくらいの時間に起きて規則正しく過ごす。
そうすれば、日曜の夜も平常心で過ごせるはずなんです。
──大学を卒業されて以降、産業医として長く、企業で働く人たちを見て来られました。
相談内容は、どのように変化しているのでしょう?
産業医仲間の間で、最近は、職場以外での部下の様子を知らない上司が増えているという話がありました。
個人情報に厳しいご時勢も手伝って、仕事以外の話、たとえば美味しいお店、スポーツやファッションのことなど、僕はそれを「ムダ話」と言っていますが、そういう話をする機会が少なくなってしまったのでしょう。
みんな仕事の話はとことんするのですが。円滑なコミュニケーションのために、知っておいたほうがいい場合もあると思っています。
アマゾンには「コネクション」というフィードバックシステムがあります。
毎朝PCを開くと、職場環境に関する質問が画面にポップアップするシステムで、匿名で回答を選ぶ仕組みになっています。
回答は集計されて上司が見ることができます。
この「働き心地のデータ化」は、巡りめぐって、回答した本人のプラスになっていると思いますね。
──鈴木先生ご自身に「心が折れた」ご経験はありますか?
そういう時に、どうしたらよいでしょう?
ありますよ(笑)。
忙しくて鬱になりかけたこともあります。
そんな時も、最初の自己肯定感の話ではないですが、やはり自分をよく見て、大事にする。
だって、できないものはできない。
そんな時は上手にあきらめる、逃げてもよいのです。
もうダメだと思ったら、とりあえずその状況から離れる、ということを心がけます。
そして、安全な環境で自分を立て直して、現実的な問題解決を模索するんです。
体調や気持ちの具合が悪くなると、僕なら、ああ、教科書に書いてある通りだな、と思いますが、医学の知識がなくても、体からの「おかしいぞ」というサインに気づくことは可能です。
朝の3時頃に必ず目が覚めてしまう、頭がぼうっとして人の「話」が「音」のようにしか聞こえないとかね。
それを「おかしいな」とすぐに感じ取れる力をつける。
繰り返しますが、とにかく自分のココロとカラダに関心を持つことが大事です。
明日に続きます♪
| 2019年09月01日(日) |
歯磨きの時に鏡の中の自分をよく見る |
Forbes JAPAN 編集部 によると・・・
優秀で真面目な人ほど心が折れやすい──。
これは、免疫学の大家である安保徹教授に著書『まじめをやめれば病気にならない』があるほか、多くの専門家が指摘していることだ。
厚生労働省によれば、精神障害による労災補償の請求件数は2018年が1732件で過去最多、1586件の前年度と比べ9.2%増で、5年連続の増加を記録した。
認定件数も2年連続で増加している。
2000年の労災請求件数「212件」の実に7倍以上だ。
また、労働安全衛生調査(厚生労働省)によれば、6割近い労働者が、職場あるいは仕事に対する不安や悩みといった強いストレスを感じているとのことだ。
ジェフ・ベゾス率いる、シアトルに本社を構えるアマゾンでは、仕事と生活を「調和」させる「ワークライフハーモニー(Work Life Harmony)」という考え方を実践しているという。
この世界最高峰の企業で働く人たちはどのように多忙やプレッシャーから心を守り、ハイパフォーマンスを発揮しているのか。
 アマゾンジャパン産業医の鈴木英孝先生 → アマゾンジャパン産業医の鈴木英孝先生 →
人事部・ジャパンコーポレートディレクターの上田セシリアさんに、「心を守りながら仕事で成果を上げる秘訣」について話を伺った。
「歯磨きの時に鏡の中の自分をよく見る」が、自己肯定感を高める
──鈴木先生、毎日の仕事に追われ、心身が疲れてくると、仕事で成果を上げても「今回は偶然だ、次は同じようにいかないかもしれない」と思ってしまいがちです。
自己肯定感を高く持つには何をすればよいでしょう?
自己肯定感の高い人は、不安耐性が高い。
つまり、心が折れにくい、ということは確かだと思います。
そして、自己肯定感を高めるには、なんと言っても、自分を大切に扱うこと、ですね。
では、自分を大切に扱うにはどうしたらいいか。それは、自分のココロとカラダに関心を持つことだと思います。
まずは朝、歯磨きの時に顔を見る。
鏡の中の自分をよく見る。
そこで顔色、肌のツヤなどの確認から始めてみてください。それが、メンタルな状態も含めて自分の健康状態に敏感になるための習慣の第一歩です。
それから、たとえば僕自身はランニングをしているんですが、体調が悪いと走り始めてすぐにわかる。
でも、辛くても行けるところまで行こう、と思ってがんばって走っていると、意外と調子が戻ってきて走れたりする。
仕事でも、無理だと思うポイントを知って、がんばってそこをちょっと越えてみる。
その小さな成功体験を重ねることで、自己肯定感は高まって行くと思います。
ランニングなどの運動は、そのためのイメージトレーニングにすこぶる効果的だと感じています。
あとは、食事の時間をしっかり取る。業務に忙殺されると、つい食事もデスクで仕事をしながらになりがちです。
食事をちゃんと取る、運動をする時間を捻出するためには、1日のスケジュールを逆算して、時間を確保することが大事です。
そうそう、忙しい人ほど運動はするべきですね。
そうすれば時間管理も上手になってゆく。
ちなみにアマゾンには、上司との「ワン・オン・ワン(1対1の面談)」のカルチャーがあります。
頻度は週に1度だったり隔週だったり色々ですが、定期的にこれを行うことが強く推奨されている。
その場で上司が部下の肯定感を確認できることもあるし、自分で確認することもできますね。
以上、原文のまま転記しました。
明日&明後日も続きます♪
| 2019年08月31日(土) |
放っておけない口の中の病気 |
今夜放映のNHKチョイス@病気になったときでは、、、
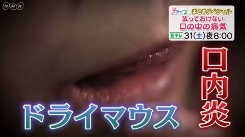 過去の放送をコンパクトにまとめてエッセンスを届ける「まとめスペシャル」。 過去の放送をコンパクトにまとめてエッセンスを届ける「まとめスペシャル」。
今回は口の中の病気。
誰もが経験のある口内炎だが、原因はさまざま。
カンジダ菌というカビの仲間が原因の場合も。
また、舌がんにつながる危険な口内炎に注意。
口の中が乾くドライマウスはストレスや薬の副作用で起こることもあります。
入れ歯が合っていないと、うまくかめないため、唾液が出にくくなります。
口の中のトラブルの対策のチョイスを詳しく紹介していました。
昨日の『身元確認合同訓練』で、渋谷区にお願いされたこと。。。
およろしければ、お持ちのスマートフォンにインストールしてくださいとのことでした。
※ アプリは無料でご使用いただけますが、ダウンロードや各種ページの閲覧等による通信費は利用者の負担となります。
※ 通信環境や機種、OSの種類、バージョンなどにより、正常に動作しない場合があります。
お問い合わせは、渋谷区防災課災害対策推進係(03−3463−4475)まで♪
午後は休診させていただき、渋谷区の3警察(渋谷・原宿・代々木)署と渋谷区歯科医師会との大規模災害時における身元確認合同訓練に参加させていただきました。
事件なのか、事故なのかといった判断も含めいかに正確に、いかにスピーディーにご遺体をご家族の元にお返しするかといったことについて、その使命感をヒシヒシと感じた一時でした。
「マグニチュード7.3の直下地震なのに死亡数5名という行政の想定」は大丈夫なのでしょうかね???
一昨日&昨日にかけての富士山の下山のついで!?に、↑ に登りました。
宝永山は、1707(宝永4)年の宝永大噴火で誕生した、富士山最大で最新の側火山です。
左上が山頂(標高2693m)、右下が3つの火口のうち最も大きい第1火口と称される地点。
 リフレッシュ休暇を頂戴し、富士山に登っています。 リフレッシュ休暇を頂戴し、富士山に登っています。
上は、7合9勺から拝んだ“ご来光”です。
この写真をご覧の皆さまに幸せが訪れますように♪
右は、日本最高地点“剣ケ峰”での記念写真です。
下山してから知ったのですが、ちょうど山頂での写真を撮っていた頃、お鉢の反対側では、落石に依る死亡事故が起きてしまったようでした。
ご冥福をお祈り申し上げます。
 富士山に登る先生方からお誘いいただき、参加させていただきました。 富士山に登る先生方からお誘いいただき、参加させていただきました。
写真は5合目から出発するシーンですが、ぬぁんと麓から自転車で登っていらっしゃった方も!
とても真似ができません♪
| 2019年08月23日(金) |
定期検診を受けているのに歯周病が悪化した なぜ?−3 |
一昨日&昨日の続きです。
● 歯周病をちゃんと診療している歯科医を見分けるポイント
歯科診療所の数は約6万8500軒(今年3月末)とコンビニの数よりもずっと多く、競争は厳しいでしょう。
その中で予防歯科への関心が高まり、ホームページを見ると、「予防」をうたう診療所も目につきます。
ですが、歯周病をきちんと診療していない“なんちゃって予防歯科”もあるわけです。それでは、歯周病もきちんと診ている歯科医かどうか患者はどうすれば見分けることができるのでしょうか。
Tさんは、「定期的なプロービングやエックス線検査、それにカメラで口の中の写真を撮影しているということでしょうか。口の中の写真からも、治療による変化がわかりますから」と言います。予防歯科の基本的な手順をちゃんと行っているということですね。
Nさんは、歯周病治療ができる歯科医かどうかを見分けるポイントを指摘しています。
「重度」の歯周病に当たる6ミリ以上の歯周ポケットがあった時、麻酔を使ったクリーニングを行っているかどうか。
「その深さの歯石を取るにはどうしても痛みが出るので、麻酔が必要になります。麻酔を使っていないとすれば、根の奥の歯石のクリーニングが行われていない可能性があるので、その歯科医は要注意です」
冒頭で触れた、定期検診を受けながら歯周病を悪化させた患者は、麻酔を使ったクリーニングを受けたことはありませんでした。
そして歯科医からこう言われていたそうです。
「かみにくくなってきたらインプラントにしましょう」。
歯周病の治療を知らなかったのか、歯周病を治療するつもりがなかったのか。
3か月に1度の定期検診の案内のはがきは、患者を囲い込んで次の高額治療につなぐのが目的だったのでしょうか。
● PMTCを受けていれば大丈夫、ではない
「PMTC」という言葉をご存じですか。Professional Mechanical Tooth Cleaning(プロによる機械的歯面清掃)と言って、歯科のメンテナンスのために定期受診をすると、ぐるぐる回る器具で歯を磨いてくれます。
これで歯に付着した歯垢が固まったバイオフィルムを壊してきれいにします。
歯を虫歯から守る効果があり、歯はツルツルになって気持ちいいですよね。
「メンテナンスを受けた」と実感するかもしれません。しかし、ここで注意点。
Nさんは「PMTCを受けているという患者さんもおいでになりますが、歯周病で重要なのは、歯茎の縁の下です。そこが見過ごされていると、PMTCですっきりしても、歯周病は進んでしまいますよ」とクギを刺しています。
● 歯科衛生士の役割も重要
歯周病の診療では、歯科医の管理の下とは言え、歯科衛生士が進行度合いを検査し、歯垢や歯石をクリーニングすることが多いので、その役割は大変に重要です。
歯肉の内部についた歯石は見えないので、器具を使って手探りで調べ、取り除く作業になります。歯科衛生士にとっても実践的な学習は不可欠です。
「歯周病の検査や治療は、臨床の現場に入って、身につけてきたんですよ。初めは歯茎を見ても状態の良しあしさえ、判断がつきませんでした」と、筆者がお世話になっているキャリア15年の歯科衛生士は話しています。
歯周病診療に習熟した歯科衛生士を育成するため、日本歯周病学会と日本臨床歯周病学会は認定歯科衛生士の制度を設けています。
自分で処置して、回復する経過をフォローしてきた治療例5人の報告などが認定の要件です。
予防歯科の診療をきっちりと実践するには、歯科医自身のスキルだけではなく、意欲的な歯科衛生士を雇用し、指導できる才覚や環境も必要なわけです。
患者としては、歯科医と歯科衛生士の連携がうまくいっている歯科と巡り合いたいものだと思います。
● 日本人の8割は歯周病だが、その9割は基本治療で良くなる
国の歯科調査の結果から、日本人の7〜8割が歯周病とされています。
また、海外の調査で、歯周病の病態を詳しく見ると、81%の方はゆるやかに進行し、8%は歯周病に弱い体質で急速に悪化し、一方で幸運な11%の方は余り進まないことを示すデータがあるそうです。
Nさんは、「歯周病があっても9割の方は、基本治療をして、歯磨きやフロスの方法を身につければ治るのです。その後に定期受診をしてメンテナンスしていけば、歯周病で歯を失う危険を避けることができます」。
20歳代から進んでしまうなど体質的に悪化しやすいタイプの人は、専門医の一層ていねいな治療や管理が必要だと言います。
歯周病で歯を失わないためには、早期発見して対処するのが基本戦略です。
歯が揺れていれば歯周病が進んだ状態ですが、それでも改善し歯を守ることができないわけではありません。
定期検診に通っていない人はもちろん、定期検診に通っていても、歯科医の説明に疑問を感じた時は、セカンドオピニオンのつもりで歯周病の専門家への相談を考えてもいいかもしれません。
※ 固有名詞以外は、原文のまま転記しています。
| 2019年08月22日(木) |
定期検診を受けているのに歯周病が悪化した なぜ?−2 |
昨日の続きです。
● 長年、歯科医の間でも歯周病への関心は低かった
Tさんは30年ほど前に開業しましたが、「大学を卒業しただけでは歯周病の診療は知識がなくてできませんでした」と振り返ります。
自腹を切って、国内外の研修に参加して技術を身につけてきたそうです。
当時は、歯科と言えば虫歯の治療が中心で、歯科医の歯周病への関心は低かったと言います。
「歯周病は歯ブラシをやっておけばいいんだよ」と口にする先輩歯科医も多かったそうです。
歯ブラシだけでは歯石は除去できず、歯周病は悪化してしまいます。
「社会的にも歯周病への関心が高まってきたのはここ4、5年のことですね。
私が歯周病の専門医と知って受診されたり、他の歯科医から患者さんを紹介されたりするようになりました」と話しています。
先に挙げたN歯科医院院長のNさんは、アメリカの大学院に留学して歯周病治療を学びました。
歯科大学卒業後の1980年代初め、当時の自分の知識や技術で歯周病を治療しても改善しないことに疑問を感じ、留学して歯周病治療の専門教育を受けたのです。
「歯の根の歯石を取る治療をしている時も、指導教員が横について、『もっときれいに』と指導されるわけです。歯周病は歯の根を徹底清掃してこそ改善することをアメリカで学びました」と振り返ります。
2人の話をおうかがいすると、日本の歯科の世界では、長い間、全般に歯周病への関心が低かったことがうかがわれます。
● 歯周病があっても、見て見ぬふりの歯科医も
その結果、「歯周病治療に関しては、歯科医の温度差は大きくて、積極的な歯科医もいれば、見て見ぬふりのところもあるのです」とNさんは言います。
意欲の乏しい診療所を定期受診しても、ある日、歯茎が腫れて、歯が揺れているのに気づくことになりかねません。
筆者も1年余りの間に体験取材のつもりで、3軒の歯科診療所で歯周病の検査を受けてみました。
プロービングの結果、3ミリから5ミリの歯周ポケットがいくつか見つかり、エックス線検査では少し歯槽骨が減っている所がありました。
歯周病です。
「歯磨きとフロスをちゃんと身につけて、歯茎の中の歯石を取れば良くなります」と検査後の説明で、今後の治療の手順の説明を受けた診療所もあれば、「歯周病はだいたい大丈夫です」の一言で終わったところもありました。
いずれの歯科医院もホームページでは「予防歯科」に触れていたのですから、歯周病への温度差の違いを実体験しました。
明日に続きます♪
※ 固有名詞以外は、原文のまま転記しています。
|