最近、痛感しているのは、人間はただ生きているというだけですごいのだ――ということです。
私は人間の価値というものを、これまでのように、その人間が人と生まれて努力をしたりがんばったりしてどれだけのことを成し遂げたか――そういう足し算、引き算をして、その人間たちに成功した人生、ほどほどの一生、あるいは失敗した駄目な生涯、というふうに、区分けをすることに疑問をもつようになりました。(略)
生きているというだけでもいかに大切かとぼくが思うようになったエピソードを紹介しましょう。前にもエッセイのなかで書いた話ですが、アメリカのアイオワ州立大学の、生物学者のディットマーという博士がおもしろい実験をされました。
それは三十センチ四方の木箱、深さ五十六センチぐらいでしょうか、そのなかに砂を入れて、一本のライ麦の苗を植え、そして水をやりながら数ヵ月育てるのです。すると、その限られた砂を入れた木箱のなかで四ヵ月のあいだに、ひょろひょろとしたライ麦の苗が育ってきます。これはもう当然のことながら色つやもそんなによろしくないし、実もたくさんついていない、貧弱なライ麦の苗が育つ。そのあと箱を壊し、そのライ麦の根の部分にたくさんついている砂をきれいにふるい落とします。
そして、その貧弱なライ麦の苗を数ヵ月生かし、それをささえるために、いったいどれほどの長さの根が三十センチ四方、深さ五十六センチの木箱のなかに張りめぐらされていたか、ということを物理的に計測するのです。目に見える根の部分は全部ものさしで測って、足していきます。根の先には根毛とかいう目に見えないじつに細かなものがたくさん生えているのですが、そういうものは顕微鏡で細かく調べ、その長さもみんな調査して、それを足していく。
その結果、一本の貧弱なライ麦の苗が数ヵ月命を育てていく、命をささえていくために、その三十センチ四方、五十六センチという狭い箱の砂のなかにびっしり張りめぐらしていた根の長さの総延長数が出てくる。その数字を見て、ぼくはちょっと目を疑いました。誤植じゃないかと思ったぐらいなのです。
なんと、その根の長さの総計、総延長数は一万一千二百キロメートルに達したというのです。一万一千二百キロメートル、これはシベリア鉄道の一・五倍ぐらいになります。
一本の麦が数ヵ月、自分の命をかろうじてささえる。そのためびっしりと木箱の砂のなかに一万一千二百キロメートルの根を張りめぐらし、そこから日々、水とかカリ分とか窒素とかリン酸その他の養分を休みなく努力して吸いあげながら、それによってようやく一本の貧弱なライ麦の苗がそこに命をながらえる。命をささえるというのは、じつにそのような大変な営みなのです。
そうだとすれば、そこに育った、たいした実もついてない、色つやもそんなによくないであろう貧弱なライ麦の苗に対して、おまえ、実が少ないじゃないかとか、背丈が低いじゃないかとか、色つやもよくないじゃないかとか、非難したり悪口を言ったりする気になれません。よくがんばってそこまでのびてきたな、よくその命をささえてきたな、と、そのライ麦の根に対する賛嘆の言葉を述べるしかないような気がするのです。
2004年06月23日(水)
| 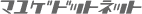 diary/column “mayuge の視点”
diary/column “mayuge の視点”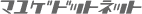 diary/column “mayuge の視点”
diary/column “mayuge の視点”