第六章 決断
◇
人生の転機
その後、社会人三年目を終えようとするマユゲにとって、ひとつの転機が訪れる。
会社の規定上、ちょうど三年目の終わりの時期から受けることができる、社内転局試験の受験資格が得られたのだ。「石の上にも三年。何ごともある程度の期間やってみなければ分からないはず。辛いのは何処へいっても同じ。今やっていることの辛さから逃げ出すことだけは止めよう」。そう思って営業の仕事をやってきて、また逆に言えばそう考えることで将来のことを考えるのを後回しにしていたフシのあったマユゲも、ここを転機と捉え、この試験にエントリーすることにした。
希望異動先は、クリエイティブ・セクションである。なんとなくであっても、もともとこの業界への就職を考えたのは、CFをつくるというクリエイティブの部分に魅力を感じていたわけで、この試験を受けることはマユゲにとって、ごく自然な選択だった。
しかし結果はNG。今、振り返ってもあのときの課題に対して自分が提出した案はつまらないものだったと思う。しかし、この後死ぬ気になって再チャレンジしたかというと、そうではない。この会社の営業としてクリエイティブの仕事を見てきたのだが、何としてもそこに移って仕事がしたいという思いは結局最後まで持てなかったのだ。ここが自分の中途半端なところであり、「自分は逃げているのではないか」と何度も自分自身に問い掛ける原因となった出来事だった。
時を同じくして、また異動の話が持ち上がる。当時の局長は、マユゲ的には何処にいきたいかを一応聞いてくれたのだが、マユゲは「営業ならば自分の中ではどこでも変わりはありません」と答えた。そしてフタを開いてみれば、マユゲの配属先は、社内でも忙しさナンバーワンの呼び声高い、某化粧品会社S担当のチームであった。
実際異動してみると、さすがに当社メインクライアントのひとつであるこの化粧品会社S担当チーム、大人数で、しかも優秀な人物揃い。そのうえ現場・管理職を問わず、超ド深夜まで皆さん本当によく働くのだ。当初は、よりによってとんでもないところに来てしまったものだと内心思った。ここの部署で、結果的には二年近くに渡って仕事をすることになるのだが、ここでの経験は、マユゲにとってさらに貴重なものだったと思う。
「きっと、もの凄く大変に違いない」と覚悟していたが、本当に大変で、もう笑うしかなかった。特に最初の一年間は、飛ぶように過ぎた。その中で、自分的にはその前の三年間分以上成長できたのではないかと感じる。何より、ここへ来る前に営業から出ようとしたことをカミングアウトしていたことで、自分的にそれなりに吹っ切れるものがあったからなのだろう。
ペアを組む上司にも恵まれた。仕事の面で求められる諸要素を見事に備えているタイプの人なのだ。頭の回転が速く、恐ろしいほどの行動力。そして几帳面で、忍耐強く、冷静で、クライアントにもしっかり主張を通しつつ、相手の機嫌を損ねないコミュニケーション上手。マユゲに足りない部分をことごとく見せられているかのようで、とても刺激になり、勉強になった。怒らない人なのだが、逆にそれが怖くてこっちも一生懸命頭を回したものだ。マユゲの、気遣いの足りない、時に少々生意気な言動も、全然気にせず面倒をみてくれた。
◇
神様がいま考えろと言った
Sチームでの嵐のような一年間が過ぎたころ突然、入社以来初めて、忙しさの波が退いた。
早く帰ることに慣れていないマユゲは当初少々困惑したが、ちょうど自分について考える時間を持つことができたわけだ。これも神様の計らいだったのかと今になって思う。自分はどういう人間なんだ? 自分はどう生きたいんだ? 自分が大切だと思うことがおろそかにされる生活に流されていないか? 本来の自分は、そんなこと別に大事と思わないと感じることに躍起になってないか? このままでいいのか? いやなら、一体いつ行動を起こすんだ? その行動とは一体何なんだ?
おぼろげながら考えついたプランについて、男女を問わずいろいろな年代の友人に相談をした。カズンドしかり、新田祥司しかり、麻生哲朗しかり、フジモトしかり、そのとき惹かれていた尊敬できる素敵な女性しかり……。この少し前だったかと思うが、ホームページでこの「mayugeの視点」を始めたのがちょうどこの頃であった。いろいろなことを話し、書き、そして考えた。
湯屋泰宏と多摩川河川敷グランドで仰向けになりながら話し(4月27日)、映画『ルディ』を見て感動し、麻生の勧めで見たドラマ『白線流し』に「激しく感情移入」し(6月11日)、高校時代の友人と会い、当時を振り返り(6月21日)、女の子のスカートをきっかけに自分を諌め(6月23日)、会社外の同級生女子ご意見番フジモトにプランをぶちまけ意見をもらい(7月5日)、自分でやりたいと意志を持ったことを、一人の力で成し遂げられるかをまず試すべく、キナバル登山を計画し(8月13日〜)、その準備として富士山頂を単独行で極め(7月16日)、二十代最後?の恋をし(7月26日)、大学アメフト時代の友人の近況に思いを馳せ(8月28日)、シドニー五輪で「意志の力」というものを改めて認識し(10月5日)、アニキの応援歌に勇気をもらった(10月22日)わけである。
こうして様々なきっかけで自分を見つめなおし、将来を考え、その中で、会社員生活からの「卒業」を決意するに至ったのだった。人生、生きられる時間には当然限りがある。その人生の中で、毎日を生活していく以上、その糧を支えることになる「仕事」にかける時間は大きなものとなるだろう。そして自分は社会人五年目。これからはどれだけ仕事に「意志」をもって取り組めるかが、残された人生の充実度に直接影響を与えることとなるだろう。だったらこのままでは駄目だ。このまま毎日に流されて「これは自分がやるべき仕事ではない」という中途半端な考えを抱えながらやっていくことは、まわりに迷惑をかけるだけでなく、他でもない自分に対して裏切りをはたらくこととなる。このまま行ってしまえば、いつか後悔するときが来る。幸い自分は結婚もしていないし、節目と考える三十歳までに残された時間があと三年ある。今しかない。そう考えたわけである。
そこでマユゲの今の「意志」を大切にできる、これからのプランに行き着いたのだ。そのプランというのは、ただ聞くと、とても安易で無計画で甘えたものに聞こえる代物。実際きっとそうなのかもしれないとも思うが、しかしそれは、9月5日をもって二十七歳となったマユゲが、それまでの人生経験をすべて踏まえた上で、会社を辞め収入を失う上に借金までするというリスクを犯してでも、今やりたいという「意志」の持てることであったのだ。これまで夢は何かと問われても何も答えられなかった自分が、初めて夢を持てたと自信をもって言えるものだった。
誕生日を少し過ぎたある週末、マユゲの考えを両親に説明するため、実家に帰った。意外に冷静に、そして思いを込めて、ほぼ正確に自分が考えるプランと、それに至るまでの思考の流れの全てを話せたのではないかと思う。母親はショックを隠しながら、その後の人生や体のことをしきりに心配してくれた。マユゲはそのとき母親の顔に否定しようのない老いを認めてしまった。今まで散々苦労をかけてきた挙げ句、この歳になってまた心配をかけてしまう自分を責めずにはいられなくなった。一方、父親は一言。「お前の話を聞いて、お前が逃げているのではないということが分かった。俺は全面的にお前のやろうとしていることを応援する」。
若くして子供を持ち、ある面では自分を犠牲にしながらも、教師というひとつの職業を勤めあげてきた父親から、この言葉がでてくるとは正直驚いたが、同時にその懐の深さに改めて尊敬の思いを強くした。自分の職業に誇りを持ち、世間がなんと言おうと自分が正しいと信じた道を突き進む父。俺もそうなりたいよ。立派な両親に対して、このだらしのない子。本当に頭が上がらないが、これが最後だ、やらせてくれ……。
その夜はかつて自分が使っていた部屋に寝たのだが、その壁には、父が貼ったのだろうか、いつの間にか見慣れない大きなポスターがあった。それは、雄大な南アルプスの山々を遠くに望むどこか片田舎の駅の風景写真を一面に使った、旅情を誘うJRのポスターだった……。
◇
意志伝達
両親への報告を終え、次は会社への意志伝達が大きな問題であった。くしくもこのタイミングというのが、マユゲが所属するSチームが、参加していた大型のプレゼンを立て続けに落したり、長年Sチームの頭脳として活躍してきたベテランの転出が決まったりと、部長にとってはまさに厄年となっていたときだった。明らかに気力体力限界のところで仕事をし、それでも前向きに頑張っている部長に、事前の相談もなく突然退職の意向を告げるのは、非常に躊躇われた。
まず、ペアを組んでいる上司に意志を伝えた。これでも精神的には一苦労だったが、次は部長に話さねば……。諸処の状況を鑑み、後になればなるほど、かける迷惑が大きくなると思い、断腸の思いでその数日後、部長に切り出した。部長は、相当面食らっていた様子であった。だがそのあと、とても温かい言葉を返してくれた。「それはお前の人生。個人的には応援してやりたい。でも、すぐにというのは勘弁してくれ……」。
意志を伝えたのは9月であったが、これまた業務上の諸処の都合により、結局、退職日は世紀を越し、2001年1月末日ということで落ち着いたのだった。当初は12月いっぱいでの退職を希望していたマユゲとしても、納得しての決着だった。
そして何よりも寂しい思いだったのが、リベンジャーズを離れること。こんな自分だって、何かやれるに違いないという自信を持てたのは、リベンジャーズ・ディフェンスキャプテンとしての経験によるところが大きかったと思う。リベンジャーズを離れることを決心し、より一層の気合で取り組んだ2000年秋のシーズンが残念な結果に終わったことは、本当に、本当に悔しい。でもこれは、神様がまだまだと言っているのだ、と捉えよう。帰って来てからも参加できる体でいられるだろうか? 自分の後に続く「ヤング・リベンジャーズ」の面々に、自分のハートは伝わっただろうか? リベンジャーズの遺伝子は受け継がれただろうか? その答えは今後のリベンジャーズの活躍にみることとしよう。
◇
夢
こうして考えてみると、自分は実に多くの人に支えられて生きてきたんだと、つくづく思う。本当に感謝している。そのひとり一人に今の自分が抱えている思い、「プラン=夢」を正確に伝えることは難しい。ただ、できる限り伝えてから、次の一歩を進めたいと思っている。
そのプラン=夢とは、世界放浪の旅、である。
約二年間かけてアジア、ヨーロッパ、アフリカ、オセアニア、アメリカ大陸を旅する。その一連の旅程の中に、ワーキングホリデーというかたちで海外に住むというチャレンジを織込むつもりだ。その間に達成しようと思っているのは、語学のブラッシュアップだけ。敢えて、帰って来てからどんな仕事に就くかは決めずに旅する。その中で、こんな人に会った、こんな物をみた、こんなこと考えた、というような自分なりのフィルターを通して吸収したことを誰かに伝えて、そこから何かを感じてもらいたい。これが、今やりたいことの全てなのだ。
ささやかな、ドキュメンタリー。そこには文があり、絵が必要となるだろう。このホームページでやってきたことの延長で世界に飛び出す、そんなイメージだ。この旅をする中で、農業をやりたいと思ったり、教師になりたいと思ったり、はたまた坊さんになりたいと思ったり、やっぱりまた会社員になりたいと思ったりするかもしれない。
今これだけの、時間的にも経済的にも贅沢なときを過ごそうとしているわけであって、この先どの道を思うにしても、三十歳を目前にするマユゲにとってその道は相当に厳しいものになるに違いない。ただその道は、「意志」を持って人生を賭けられるものにしたいと思っている。そしてその責任は、すべて自分にあるのだ。再び果てしなく広がる自分の将来の可能性と、同時に感じる「後の無さ」に身震いする思いだが、今、言えるのは、自分のこれからの人生が「楽しみ」だと思える、そして、初めてしっかりと前を向いて生きていると思えるということ。「楽しみ」とは困難とセットになって存在する、ということは、短いながらも今までの人生で勉強したつもりだ。
先日、クライアントに通う地下鉄の駅のホームで、日経新聞の看板広告が目に留まった。そこには、こんなコピーがあった。
「あなたは何を見て21世紀を生きますか?」
その看板を前に、スーツ姿のマユゲは心の中でこう言い返してやった。
「世界を見て生きてやるぜ!」
(おわり)
※12月31日をもって「mayugeの視点」2000年版を終了しました。
2000年12月31日(日)
第五章 様々な出会い
◇
会社員生活始まる
1996年4月。やや後ろ髪を引かれる思いを抱えながらも社会人となったマユゲは、「会社に勤め、お給料をいただいて生活していく以上、生半可な気持ちは絶対に駄目だ」と気合を入れなおし、会社員生活に突入した。
就職大氷河期であった96年は、同期がたったの八人。マユゲも含め、冴えない男五人とわりと元気な女三人。この代に共通しているのか、大きな期待を抱いて社会に飛び込んできたらしい輩も見受けられない。現在(2000年)に至っても未だ「影の薄い代」だと自分ながら思う。ただ人数が少ないこともあってかすぐに仲良くなり、新人研修合宿終えるころには、なにか家族のような絆が生まれていた。余談だが、そのおかげでマユゲの同期内では、「ビバヒル(ビバリーヒルズ青春白書)的」グチャグチャ男女関係は微塵も起こらなかった。研修を終了し、それぞれの現場に散っていってからも、年に何度かは集まって飲んでいる。
新入社員のマユゲは、コンピュータ・メーカーとファストフード・チェーンのクライアントを担当する営業の部署に配属となった。次の年以降も異動などにより、スポーツ用品小売チェーン、ゴルフ用品メーカー、エンターテイメント産業など、様々なジャンルのクライアントを担当する。その中で、テレビやラジオ、新聞、雑誌などマス媒体のセールスから、テレビCFの制作・全国キャンペーンの実施など、いかにも広告代理店らしい仕事に恵まれ、毎日が飛ぶように過ぎていった。一年目、二年目の間は、将来のことを考えるというより、その日その日のやるべきことで"いっぱいいっぱい"だった。
より帰りが遅くなった二年目の秋からは、会社から遠い実家を出て一人暮らしも開始。おかげで帰りはますます遅くなっていったわけだが、そんな毎日の中で、小さな失敗や成功を繰り返し、まわりにいるオトナの仕事ぶりを目にし、自分でも「学生のときは本当に甘ちゃんだった」と思うような厳しい場面にも出会った。人間、そのときそのときは「今が人生で一番辛い」と思っても、後になって振り返るとそんなの全然平和だったと思うもの。中高のときは小学生のときを、大学生のときは高校時代を、新入社員なら大学時代を、社会人二年目なら一年目を、それぞれ振り返って「あの時の悩みなんて、今では大したことないや」と思う。そうやって少しずつ自分のキャパシティを広げていくものなんだろうな。
連日、昼はクライアントに顔を出し、会社に戻ってからは遅くまでデスクに向かう生活が繰り返されたが、もともと「社会人たるもの、相当キツい毎日が待っているに違いない」と覚悟していたマユゲは、常に「まだまだ全然イケる」と思って仕事をしていた(実際、あのときはまだまだだったと思う日が、次々にやってくる訳だが……)。まあ、そんなふうにして、体力だけではなく「腹の座り度」も少しずつ成長していたのだろうか。
そしてそれに伴って、仕事でも仕事以外でも、それまでの自分ではできなかったことができるようになり、もっと刺激的なものを求めるようになっていった。
◇
リベンジャーズとの出会い
しかし会社では、このまま自分は営業としてやっていくんだとは、やはりどうしても考えられず、自分の将来を考えたとき、間違っても営業部長になんかなりたくない、という思いを常に抱えていた(今、本当に大変な状況の中で頑張っていらっしゃる営業部長の下にいるので、こんな言い方すると申し訳ないのだが、でも自分は本当にそう思うのだ)。そして、現在やっていることとは裏腹な思いを秘めていただけに、毎日の営業の仕事に対しては余計に「決して手を抜いてはならない」という逆プレッシャーを強く感じていた。
そんな地に足がついていないような毎日の中で唯一、自分の意志のもとに暴れまわれるところがあった。それがリベンジャーズだった。いろいろな会社の人間が集まる、社会人のタッチフットボール・クラブチームである。リベンジャーズとの出会いは、新入社員のOJT時、お使いでいった別セクションの先輩、飯塚健二のデスク上に飾ってあった一枚の写真だった。聞けば、千葉マリンスタジアムで全国優勝したときに記念撮影したものとのこと。
「なんだお前、タッチフット知ってるのか? 何? アメフト経験者? よし、じゃあ今度の土曜、練習見に来いよ」
この一言からその後のリベンジャーズ生活の全ては始まったわけだ。そしてその週末には、「一応、持って来い」と言われていたTシャツ短パン姿で春のリーグ戦に出場、アメフト時代のクセで相手を引きずり倒し、イエローフラッグを投げられていた。しかしこのとき、怪我で「未」完全燃焼で終わっていた何かに再び火が点き始めていたのだった……。
◇
カズンドの涙
リベンジャーズでの一年目は、結果だけでいえば残念なものだった。春は横浜スタジアム、秋は千葉マリンスタジアム、それぞれ全国大会に駒を進めたわけだが、同じ相手に敗れたのである。
その相手とは、関西学院大学のチーム「レッドクロス」。彼らは関学高校時代にアメフトで全国を制覇した連中だけに、アスリートであると同時にフットボールたるものを頭と体でよく理解しているチームであった。一方、タッチフットの世界で全国優勝を何度も達成して来ているリベンジャーズとしては、関学の主力である四年生が卒業してしまう前手のこの96年秋になんとしても春の借りを返すんだと、主将でQBを務める岡康道を筆頭に、力が入っていた。
中でも一番燃えていたのは、マユゲの会社の先輩でもある清水一人(かずひと)だった。通称、カズンド。彼もまたアメフトの経験者。そしてその類希なアスリート能力で、オフェンスに、ディフェンスに引っ張り凧のチームのエースである。特にこのシーズンは、QB岡が信頼するレシーバーとして大車輪の活躍だった。この日の試合でも、誰よりも熱い闘志を最後まで燃やしていたのが彼だった。
ギリギリの闘いに敗れた試合後、そのカズンドが千葉マリンのダグアウトで泣いているではないか。当時カズンドは28歳くらいだったであろうか。その大の男が、悔しいと言って涙を流しているのだ。正直、驚いた。同時にその姿に感動した。
アメフトをやってきた人間として、そして何よりもタックルを生きがいとしてやってきた者として、マユゲは「タッチ」でプレーが終了してしまうこのスポーツに、思い切りハマりきれないでいたのだが、カズンドのその姿を目にしたとき、男がプライドを賭けて闘うスポーツとして、アメフトもタッチフットも何ら変わりはないんだと思った。そして同時に、社会人として忙しい仕事を抱えながら、スポーツに対してここまで本気で取り組めるということは文句なく素晴らしいと思った。
このときを境に、このスポーツに対する、そして熱い思いで皆が取り組むこのチームに対する愛着が強固なものとなり、同時にマユゲの中の火が、一層強く燃え始めたのだった。油ではなく、涙という水で火が燃え広がるとは皮肉なものである。
◇
考え方が変わった?
一方で、マユゲの広告代理店営業マン生活は続く。
「広告代理店」というとまず、「チャラい」というイメージがあるだろう。実際そういう人もいるが、まわりを見ていて思ったのが、したたかにそういうふうに見せている人もいるということ。この仕事、クライアントにとって我々は、言ってみれば「世の中的には……」のスペシャリストなわけで、クラインアトの製品・サービスのターゲットである各年代・属性の人たちがどんなふうに生活しているのかを語れなくてはならないのだ。そのためには「俺は、流行り物は軽薄で嫌い」などとは言っていられない。流行のプレイ・スポットやお店にはいち早く足を運び、話題の映画はすぐに見る。よく言う「アンテナを張る」というやつだ。そして実際に自分で体験してみるということがまず大切であり、その上でターゲットたちが何故それに群がるのかを考える。
優秀な先輩たちは、どう考えても忙しい毎日の中で、それを苦もなくこなしていた。そしてその体験が彼らの血となり肉となっているのだ。彼らにとってそれが決して嫌なことではなく、むしろ好きであるということがここで重要なポイント。会社に言われるから、という理由なんかではなく、自分の意志でやっているのだ。
こういう考え方を受け容れられるようになると、流行りものに対する「食わず嫌い」がなくなっていく。マユゲの同期は自分も含めパッとしないのだが、当然この業界なので後輩の中にはおしゃれな奴も結構いる。そういう感度が高めの後輩を見ると、「コイツ、なかなかデキる奴かも?」と思ったりするようになった。これが昔の自分なら、おしゃれに気をつかう先輩や後輩に対して「なんだ、こいつら、チャラチャラしやがって」と、「古代の体育会系」的な思いを持っていたかも知れない。変われば変わるものだ。
自分が全て正しいと固執するのではなく、他人の考え方も認められるということ。これは裏返せば、自分という存在に対して少しずつ自信を持ち始めているということなのかも知れない。謙虚を旨とし、自分の枠を飛び越さず、常に自分に自信が持てずに、何処かでコンプレックスを抱えながら生きてきた自分が、「変化してきている」という事実は、自分的には「よし」だと素直に思った。
それともうひとつ、会社に入ってみて感じたこと。それは、頭のいい人ほど物事を分かりやすくシンプルに考えるということ。そしてそこに説得力が生まれてくるのだ。ついつい物事を難しく考えがちなマユゲは、そんな優秀な人たちとの出会いによって目からウロコを少しずつ剥がしていったのだった。
そんなマユゲの変化にいち早く気付いたのが、付き合って三年以上になっていた、当時の彼女だった。それまではうまくいっていた、ちょっとしたことから歯車が狂い始める。自分が変わっていき、それを良い方向への成長と考え、よしとする男。そしてそんな男の身勝手に耐えられなくなってゆく女。二人の間には何も問題なんてないと思い、楽しく過ごしてきた彼女との関係も、結局は破局を迎えることになる。いつだったか、彼女が口にした、「あなたは変わった」という言葉が、今も印象に残る……。
◇
日本一
リベンジャーズ二年目になると、アメフト時代の経験を買われディフェンスキャプテンに指名された。アクの強い年長者たちの中で自分に務まるかと自信がなかったが、いい機会だと考え挑戦してみることにした。そして1997年春、カズンドの涙から半年、横浜スタジアムで西の新興勢力、立命館大学を破り全国制覇を果たした。
マユゲにとっても、「日本一」というのは生まれて初めての経験であり、このときの感動は忘れられないものとなっている。そしてそれが、全国で百チームにも満たないマイナースポーツのものであれ、この「自分が日本一になる」という経験は、その後のマユゲの人生の大きな自信となったと言える。
そしてこのとき同時に、プライベートでもマユゲに春が訪れていた。自分を慕ってくれる人が再び現れたのだ。一つ年上のその彼女は、考え方や行動がマユゲにとってとても刺激的で、男と女の関係論の面でも目からウロコが落ちる思いだった。
決して何から何まで男と同じものを求めず、女らしく女としての幸せを純粋に求め、それを堂々と主張できる潔さを持った人だった。彼女とは結局約半年という短い時間で別れを迎えてしまうのだが、その半年間のことはマユゲの脳裏でとても強烈な彩を放っている。恥ずかしげもなく言ってしまえば、それだけ真っ直ぐにお互いを慕い合えていた、ということだと思う。
そしてリベンジャーズは97年秋、チーム創設以来初の関東選手権での敗退という危機を乗り越え、翌1998年春、日本一奪回を果たした。マユゲにとっても二度目の全国制覇。しかしこの試合をもって、主将でQBの岡が引退を表明した。リベンジャーズの代名詞であり、その強烈なカリスマでこのチームを率いてきた岡康道の引退は、リベンジャーズにとっても一時代の終焉を意味することとなった。
一方でこの年を前後して、現在のリベンジャーズの中心となっている若い世代のプレーヤーも多数入団。ある意味、世代交代を象徴するかのような出来事だった。そしてその後、我々「ヤング・リベンジャーズ」にとっては、日本一挑戦を何度も跳ね返されるという、不遇の時代が始まったのである。
一方、仕事の面でもマユゲにとってのひとつの転機が訪れようとしていた。
(つづく)
2000年12月28日(木)
第四章 学生(コドモ)から社会人(オトナ)へ
◇
神様と暮らす人々
間違いなく日本とは違う常識が支配するインドの日常。そこに身を投じることの衝撃。そして固定観念からの解放。そんな、この旅行の醍醐味とも言える感覚を徐々に味わいながら、夜行列車の二等寝台でインド人と一緒に揺られること数時間、マユゲたちは、明け方のヴァーラナーシーに到着。
この街はヒンドゥ教の聖地。インド各地から巡礼の人たちが集まってくる場所なのだ。彼らは、この街を流れる聖なる大河ガンガー(ガンジス川)のほとりにある、「ガート」と呼ばれる沐浴場に早朝から集い、それぞれ思い思いに神への祈りを捧げ、そして聖なる水をその体に浴びる。それを最大の喜びとして生きているのだ。
ガートからはダサーシュワメードロードと呼ばれるメインストリートが街の中心に向かって伸びる。メインストリートと言っても、土埃が舞い、其処此処に牛の糞が落ちているような汚い道なのだが。このあたり一帯がいわゆるバザールとなっていて、道を挟むように定食屋(ターリと呼ばれるインド風定食が食べられる)、ゲストハウス等の店が軒を連ねる。そこからはさらに細い路地が迷路のように伸びていて、そこにもまた店があるのだ。
この路地を歩くのが結構面白い。薄暗く、人がやっとすれ違える程度の細々とした道。衣料を売る店があると思えば、その隣は生鮮食料品の店。さらにその隣ではオヤジが髪を切ってもらっている。その次は店ではなく普通の民家。開けっぴろげな窓からは昼寝を決め込むオバちゃんの姿が。そしてまた店が続く……といったような、なんとも無秩序なレイアウト。
マユゲが店に気をとられつつ歩いていたとき、誰かと肩がぶつかった。反射的に「Oh,sorry...」と謝りながら振り向く。するとそこにいたのは、なんと牛。そう、ヒンドゥ教においては、牛は「神」であり、人間と交じって堂々と街中を闊歩しているのだ。どうりで道中に糞が多いわけだ。なるほどね、と変なところで納得してしまった。
このとき以外にも事件はあった。バイク型リキシャに乗って、ある程度広い大通りを走っているときのこと。インドも日本と同じ左側通行。なんてことはないポイントで何故か渋滞が始まる。まわりの渋滞慣れしていないインドの運転手たちは、即行キレて右に膨らみつつ追い越しをかけ始める。これにまた皆がどんどん続いていっちゃうもんだから大変。同じ方向を向いた車両だけで、対向車線までの道全体をふさいでしまうかたちになってしまった。反対側から来る車が鳴らすクラクションと、それにまた応戦する逆ギレクラクションで、プープー、パーパーと、街はもう大パニック。30分かけてようやくそれが解消され、渋滞の先頭に達したとき、そういうことかと、これまた納得してしまった。そう、このときも道のど真ん中に在らせられたのは、牛の親子。うららかな二月の陽光を浴びて気持ちよさそうにお昼寝していたのだった……。
◇
神様に召された老人と神様を売る少年
ヴァーラナーシー何日目かのこと。ガート付近の道端におじいさんがうつ伏せに倒れていた。おいおい大丈夫かよ、と思いながら近づいてみると、顔を横に向けた彼の鼻の穴から、何匹かの蝿が出てきては飛んでいくではないか。どうやら、聖地を目指し辿り着いたものの力尽きた、敬虔な巡礼者の最期であったらしい。こんなにリアルな死体を見たのはほとんど初めての経験であったマユゲは、激しく動揺した。そしてその死体なんて全く目に入らないかのように平気で横を行き交うこの街の人々にまたショックを受けた。ここではきっとよくあることなのだろう。翌日同じ場所に行ってみると、そこにはもうおじいさんの姿はなかった。しかるべき人がしかるべき処理をし、また何ごともなかったかのように日常が繰り返されるのだ。
また別の日。ガート近くを歩いていると、ひとりの少年が声をかけてきた。小学校高学年くらいだろうか。始めは何を言っているのか分からなかったが、よく聞いてみると日本語ではないか。「カミサマ、カウカ?カミサマ、カウカ?」。手にもっているのは、日本でいう七福神のような、何種類かのインドの神様の小さな人形たちだった。どうやら自分で木を彫って色付けしたらしい。マユゲたちを日本人と見るや商売を持ちかけてきたのだ。「神様は買わないよ」と言って断るものの、向こうも生活の糧がかかっているのか、必死に食い下がってくる。旅行者たちと交渉するうちに身につけたのだろう、日本語・英語が入り混じってはいるものの立派にコミュニケーションが成立する言語を話す。正直、恐れ入った。しかし、悪いがそれとこれとは別。神様は買わないよ。
歩き続けるマユゲに必死について来ていた少年も、30分ほど粘ったもののさすがにあきらめたようだ。すると今度はこっちがすまない気分になってしまう。代わりに、というわけではないが、ガンガーの手漕ぎボートに誘った。商売の関係がなくなった少年とマユゲは、ボートの上でしばし歓談。その時計はジャパン製か?その靴は?そのサングラス、かけさせてくれない?好奇心旺盛な少年、マユゲの身につけているものが気になってしょうがないらしい。そこで、少年にサングラスをかけさせて船上で記念撮影。思い出の一枚だ。
その後、ガンガーの向こう岸まで行ってみようかと誘ったが、どうやら対岸はここの人たちの間では「死の世界」と考えられているらしく、断られた。その国の文化を知らないと、悪気はなくとも現地の人にとってはとんでもないことをしてしまいがちなんだな、と少年から教えられるマユゲであった……。
◇
死を待つ家
ヴァーラナーシー、またまた別の日。この街にあるという「死を待つ家」に行ってみることにした。聖地で安らかに神に召されることを願って余生を過ごす、おじいさんやおばあさんたちが住まう家――。
死ぬために集まる家。まずそれだけでショックである。そしてガンガー沿いにあるその家の真横は火葬場となっており、「生を全うした者」から順々に焼かれていくのだ。白い布で巻かれた人型の物体が運び込まれては煙となっていく。それが休みなく目の前で行われているのだ。もう、言葉が出なかった。宗教というものに身を捧げ、あるものを信じ、そのリズムの中で生きていくことはその人の自由だと思うが、どんな生き方を選ぶせよ、いつか死んでいくときには皆同じように骨となり、同じように大地に帰ってゆくのね……。
聞くところによると、何らかの理由で指が一本ないとか、成人せずに死んでしまった赤ちゃんとか、「生を全うした」とみなされない者は、ここでは焼いてもらえないらしい。焼かれずにガンガーに流されるのだ。のんきにボートを漕いでいた我々旅行者の横を流れていたかもしれない、と思うと背筋がゾッとした。また、インドには未だにカースト制度の名残がいまだあると聞く。低いカーストの者もまた、このような立派な火葬場では焼いてもらえないとのこと。
このカースト制度といい、南アの人種差別といい、日本の部落差別といい、映画「ミシシッピー・バーニング」のアメリカ南部といい……、人間というのは自分より弱い立場の者を無理矢理にでもつくらないと怖くてしょうがないらしい。日本のガキどもの「いじめ」問題の心理も、きっとそういうことなんだろう。これに限らず、人間にはそういう「弱い」面が生まれ持ってある。これは神様が敢えて人間を不完全に造ったんだろうから、きっとしょうがないんだろう。でも、「それじゃダメなんだ」と、いい方向に努力できるのもまた、人間が与えられた能力。自分はどうだ?その能力を生かせているのか???
次々に焼かれていく人々、そしてその横で無邪気にクリケットに興じるインドの子供たち、という強烈な対比の場面を目にし、動くこともままならなくなってしまったマユゲ、長い間その風景の中で考え込んでしまうのであった……。
◇
混沌の街
ヴァーラナーシーを発ち、今回のインド紀行最後の都市カルカッタへ。英国調の大建造物やそれなりに整備された大通りなど、植民地時代の名残を色濃く残す街。しかしそのインフラ的なものとは対照的なほど、そこに住まう人々の「生活臭」が最も強烈に感じられる街。一連の旅のなかでも、最も強烈な「カオス」がそこにはあった。
何処へ行っても、とにかく人が多い。そして一歩路地に入れば、道端でただ手を差し出し、その日の糧とするためのバクシーシ(施し)を求める不具の男たちがごろごろ。そして幼い弟を連れ、我々旅行者を見つけると片っ端から手を差し出しながら見上げてくる少女も。かと思えば、レストランではきちんとした身なりのインド人の家族が割と豪勢なディナーを楽しんでいる。最下層の人からトップカーストの者までがごっちゃになって生活しているのだ。新宿西口のビジネスマンとホームレスどころではない。その差がもっともっと強烈なのだ。日本と何ら変わらないような場面と、そのすぐ隣にある信じられないような正反対の場面。そのギャップはすぐには消化しきれるものではなく、インド旅行の初心者はカルカッタではなく、まずデリーから入国するのが無難といわれるのが分かる気がした。
そんなカルカッタでのこと。メーターのないタクシーで、例によって事前の料金交渉。たまたま経済力のある国に生まれたからといって何でもかんでも金をばらまけばいいというものではない。労働とそれに対する正当な対価。これは大切にしなければ。ガイドブックの情報と、これまでの行程での体験でだいたいの相場感は身についている。勝負は開始された。
運ちゃんに目的地を告げると、
「そこまでなら50Rs(ルピー)だ」とふっかけてくる。これはもう挨拶のようなもの。
「うっそ言え、高いよ。25Rsでしょ?」と半額でこちらも"挨拶"を返せば、
「いや、せめて40Rsですな」
「じゃあ、いい。バスで行く」
「あーいや待った!35Rsでどうだ?」
「30Rs!」
そこで運ちゃんも折れる。頭をちょっとだけ横にかしげるインド特有の「OK」のサイン。
「いいね、30Rsしか払わないよ」
「OK、30Rs」
一応、念押しし乗り込むものの、これでも戦いは終わらない。目的地に着いてみると40Rsよこせと言う。事前交渉どおりでない金額を請求されたのは初めてであったマユゲ、真剣にキレてしまった。怒り顔で、
「30Rsって言ったよな? あん?」
「でも道が混んでたから・・・・・40Rs」
「どこがじゃ、コラ。全然空いとったやないかい!」
さすがに関西弁ではなかったが、熱くなって応戦する。しかしさすがは非暴力主義を貫いたマハトマ・ガンジーの国。運ちゃんは腰の銃を抜いてズドン、というアメリカのような反応ではなく、一応言ってみただけだったのか、すまなそうな顔で、
「OK、30Rs」
こうなると今度はこっちが悪いことしたようで、「ごめん。俺も言い過ぎたよ」という気分になってしまった。温室育ちで世間知らずの東方の小僧を、こういうかたちで諭すとは、さすがはガンジーの国。おそるべし、インド魂。
そして、ここカルカッタでそんな「生活臭」や「インド魂」に触れたマユゲたちも、いよいよ帰国のときを迎えたのであった……。
◇
卒業
この旅を通してマユゲの頭の根っこの部分に、ある思いが芽生え始めていた。
日本で通用している価値観だけが全てではない。何を大切と思うかは、自分で見つけるべきもの……。そしてそう思ってしまったのが、他でもなく、日本における価値観を疑うことが必要とされない(むしろそう考え実行に移すことが即ちドロップアウトを意味する)、「ニッポンのサラリーマン」としての生活を始める直前のことであったのだ。
就職を考えたときには、「自分には別に世界志向なんてないし、世界を股にかけるビジネスマンなんて興味なし」と思っていたのだが、『世界』というのはそんなに一面的なものではなかった。知らずにほざいていただけだったと、今になって思う。いろいろな物や人、暮らし、考え方、宗教観など様々なものを見、体験して初めて、自分は何者なのか、そして何をしたいと思うのかが見つかってくるものなのだろう。今はそう思う。当時のマユゲの頭の片隅にも、きっとそんな思いが生まれ始めていたのではないかと思う。少しずつ自分が変わり始めていたのだ。
帰国後、卒業試験はほぼ全てパス、結果として四年間のうちで最多単位を取得というかたちで、無事「卒業」という運びになった。卒業式の日も、それからの未来に思いを巡らすというよりもむしろ、「本当にもう卒業なの?」というやや後ろ向きな思いを抱えつつ学長の送辞を聞いたのを覚えている。
そして1996年4月、後ろ髪を引かれながらも、マユゲの会社員生活が始まることとなった。
(つづく)
2000年12月27日(水)
第三章 マユゲ、新世界を踏む
◇
「未」完全燃焼
マユゲ大学四年、アメリカンフットボール生活最後の1995年秋リーグ戦。会心のスタート、突然の負傷と絶望、そして復帰・・・といったいくつかのドラマを乗越え、マユゲも宿敵K大との優勝を賭けたリーグ最終戦のサイドラインに裏方として立つ。
前半は味方のペースで折り返したものの、後半が開始されてしばらく、試合に変化があった。それまでギリギリのところで緊張感を保ち、相手強力ラインのブロックに対しなんとか持ちこたえたていた味方ディフェンスのフロント勢にも疲れの色が見えはじめていたときだった。敵の大型ランニングバックがブロックで空いた穴をすり抜けて走り出る。セカンダリーの対応にも遅れがあった。ボールを持った敵ランニングバックは、フィールドの左側を駆け上がり、エンドゾーンに迫る。逆サイドのコーナーバック佐藤がギリギリの所で止めるも、その後のランプレーで中央付近を押し込まれ、タッチダウンを許してしまう。
ここを境とするように勢いが相手に移った。再びモメンタムを引き戻したい味方オフェンスにも、焦りからミスが生まれる。投げ急いだパスをインターセプトされてしまう。その後逆転のタッチダウンを奪われた我々は、終了間際に最後の反撃を試みるものの、再度インターセプトを喫し万事休す。すべてを賭けた試合で、敗れた。
マユゲのポジションを引き継いだ後輩は、ただただ謝りながら泣いていた。サイドラインに立って見ることしかできなかったマユゲは、確かにやりきれない思いではあったものの、意外にも静かな心境だった。フィールドで闘った四年生も概ね、悔しさとともにすがすがしさをその表情にたたえているように見えた。
こうして、マユゲが高校時代から生活の第一においてきたアメリカンフットボールは、終わった。
◇
インド人、ウソつかない?
残りの学生生活といえば、卒業試験と卒業旅行。この四年後期の試験は、生まれて以来一番しっかり勉強した、といえるほど準備をした。それは単に、就職が決まっていて尻に火が点いていたから、だけのことであったのだが。そしてその結果がでるまでの二週間、卒業旅行に出る。
行き先はタイ、インド。小学校四年生の夏休みにサマースクールでスイスに行かせてもらったとき以来の海外旅行。はじめは、アフリカのサバンナで野生動物でも見ようかなとも思っていたのだが、当時アフリカでは「エボラ出血熱」という奇病が流行しており、同じ大学の学生で命を失った者も出たということもあり、行き先をインドに変更したのだった。ヨーロッパやアメリカは全く候補に入らなかった。日本と同じような文明国には興味を感じなかったのだ。今だからこそ行ける、発展途上の別世界に身を投じたかった。
バンコクのカオサンストリートでデリー行のエアチケットをとったものの、一番早くて四日後。その結果、計画ではインドの帰りに寄るはずだったリゾート地プーケットに先に行くこととなる、などのハプニングもあった。
プーケットでのビーチリゾートを満喫、象にも乗ってゴキゲンのマユゲたち一行は、バンコクからデリーに乗り込む。まず、空港内で警官が気の弱そうなインド人を捕まえてカツアゲしているのには驚いた。
空港内でデリー駅までのタクシーを手配、乗り込むと連れて行かれたのは何やら怪しい事務所。中にいたボスが言うには、「デリーからアーグラーまでの列車は今日はもう終わり。俺が宿を手配するからそこに泊まれ」とのこと。ガイドブックにある時刻表によれば、まだ列車はあるはず。明らかに怪しいと察知した我々は、事務所を飛び出し街中へ逃げる。
そこは、なんのことはない、デリー駅の裏だった。助かったと思って切符を買おうとすると、今度はインド人が群がってくる。皆、同じように浅黒く焼けた顔、鼻の下にはひげ、そして人を圧倒するような大きな瞳。「何処に行くんだい?俺が手配するよ」。皆、口々に同じようなことを言う。もう誰を信じていいのか分からない。ややパニック状態のマユゲ、「もう放っといてくれ。自分で手配する。いいかい?」と人差し指を立てる。しかし窓口の列に並んでも、まだ寄ってくる。マユゲの番が来てやっと切符を買い、仲間のものと見比べるとどうやら違う種類。仲間は断りきれずあるインド人に頼んだらしい。それは貨物車のチケットだった。
間違えられたチケットを窓口で取り替え、冷たいものでも飲もうと駅近くのダウンタウンをうろつく。汚い。とにかくあちこちがゴミの山。対インド人のストレスと、街の汚さ、そして照り付ける陽の暑さもあり、刺々しい精神状態となったマユゲは、インド到着初日にして「こんな国、二度と来るもんか」と真剣に思った。
◇
自分の胸に手を当ててみよう
その日のうちに、タージマハールで有名な街、アーグラーに入る。ここで泊まったホテルでまた軽いハプニング。
同部屋の仲間がシャワーを浴びているバスルームから悲鳴が聞こえる。何が起こったかと思い覗いてみる。シャワーが水しかでないのは、タイでもそうだった。安宿だから仕方ないよ。「いや、違うんだ。なんか、しびれるんだよ、このシャワー」。どうやら漏電しているらしかった……。
翌朝早く目が覚めてしまったマユゲ、地階に降りてホテルの前庭に出てみる。インドといえども、ここは北部で、時は二月。朝はそれなりに冷え込む。庭の端に座り一服していると、ホテルの主(あるじ)がゆっくりと歩いて来て横に座る。「おはよう。結構寒いんだね」のようなことをきっかけに少しおしゃべりをする。すると主は使用人を呼んで何やら話しかけた。ヒンドゥ語らしくマユゲには分からない。主は物静かで口数のすくない男だったが、その話し振りから決して悪い人ではないことが伺えた。
しばらくするとさっきの使用人が両手に湯気が立ち上るカップを持って帰ってきた。「チャイだよ。飲むかい?」。主の粋なサービスだった。マユゲが日本から来たというと、このホテルにはかつても日本人が泊まったことがあるらしく、喜んで宿帳を持って来て見せてくれた。デリーではインド人に対して片っ端から「こいつらは俺をだまそうとしている」と思ってしまっていたが、こうして落ち着いてみると、「駅で寄ってきた奴らのほとんどは、親切心からだったのかも知れないな」とも思える。昨日の自分を少し恥ずかしく思った。
◇
インドに入りては……
チェックアウトし主に別れを告げた後は、名所を見て回る。夜には次の都市ヴァーラナーシーへ向かう予定だ。
ヴァーラナーシー行の列車に乗る駅までは約20キロほど離れている。バスターミナルで運転手たちに尋ねてまわるも、皆、首を横に振るばかり。時計をみると列車の発車時刻は刻一刻と迫る。そこで、リキシャ(人力車。50ccバイクの後ろに二〜三人乗れるよう改造したタイプもある)の運転手をつかまえ、地図を片手に「この駅まで、○時○分までに行けるか」と尋ねる。こちらの慌てようが分からない運転手は、あっさりOKと答える。ホントに大丈夫か?とは思ったが、この男に賭けてみることにした。
真っ暗なインドの国道。照明はほとんどなく、リキシャに申し訳程度でついているヘッドランプが照らすところ以外は全く見えない。エンジンの音からすると全開で走っているらしい。しかし遅い。時折、物凄い音量でクラクションを鳴らしながらトラックが追い抜いていく。インドの大型車には大抵「目」がついている。車体の前面を顔になぞらえて、「目」をペイントするのだ。追い抜いていったトラックには、象の鼻まで書いてあった。なんとかっていう神様だな、この象は。
しばらくすると、エンジン全開で走っていたリキシャのスピードが突然落ちた。どうしたのかと思っていると……、
「ガタン」
道路にある舗装の継ぎ目が出っ張っているのだ。運転手はまたスピードを上げる。おいおい、いちいちいいよー。そのくらいの衝撃我慢するよー。のんびり屋でおとなしそうな運転手もそこは譲らない。彼等にしてみれば大事な商売道具であるタイヤと車体を守らなければならないのだ。
次第にマユゲたちも、これで間に合わなくったとしてもいいや、と思えるようになった。こうして、夜風吹くインドの闇の中を、今日初めて会ったインド人が運転するポンコツに乗ってぶっ飛ばしている。これが面白いんじゃない。列車なんて明日だってあるさ。間に合わなかったら駅で寝ればいいさ。そう思った。
そして駅に無事到着。結局一時間以上走っただろうか。時計を見るとギリギリ間に合いそうだった。運転手に料金を支払い、礼を言ってホームへ急ぐ。列車はいなかった。駄目だったか。仕方ないなと思いながら駅員に尋ねると、まだ到着もしていないと言うではないか。列車は結局は30分ちかく遅れて到着。世界一正確と言われる日本の電車に慣れているだけに、インド国鉄のオトコ前ぶりにはビックリしたものだ。
列車に乗り込み、チケットを見ながら自分達の寝台を探す。確かにマユゲの席であるはずの、一番上の寝台にはすでにインド人が七人くらい折り重なるように乗っていた。もうこれぐらいでは驚かない。そこは自分の席であることを主張すると、意外にすんなり三々五々散っていった。まったくまいるよな、と思いながら寝台によじ登り、バックパックをチェーンで手摺に巻きつけて枕がわりにする。ふと横を見ると、向かいの寝台はムスリムの二人連れ。ターバンを巻いたひげ男だ。軽く目で挨拶だけして、マユゲは横になり、眠るために目を閉じる。
しばらくして、うつらうつらした状態のときに足元になにか邪魔なものが当たるのに気付く。目をこすりながら起き上がると、なんとさっき散っていったうちの三人が戻って来てマユゲの足元に座っているではないか。これにはさすがに驚いた。一瞬、怒ろうかと思ったが、でも座れるんだからいいか、と思いなおし放っておいた。そして自分の足元にインド人が腰掛ける寝台でマユゲは眠りについた。
徐々に日本にいるときの価値観から解き放たれるのが心地よくなってきていた――。
(つづく)
2000年12月22日(金)
第二章 最後のシーズン
◇
奢れる者は久しからず
大学生活の総決算であるアメリカンフットボール関東秋のリーグ戦。もともとアメフトをやるには体が小さかったマユゲは、「会社に入ったら毎日トレーニングなんてできないだろうし、プレーヤーとしての生命線である得意のタックルに自信をもてなくなるんだろうな」と感じていた。この"でかい奴を倒すときの痺れるような快感"(実際しょっちゅう脳震盪で記憶が飛んでいたんだが)を味わえるのはこれで最後なんだと、うすうす考え始めていた。それだけにこのシーズンは相当に気合が入っていた。同級四年生のみんなもそれぞれ胸に記するところがあったようで、皆自分なりにチームに対し身を捧げた。そこで皆に共通していたのは、最終戦で宿敵K大を倒し、1年生時以来のリーグ優勝を勝ち取る、という思いだった。
初戦T大戦は大差で圧勝。マユゲ自身も、一試合三インターセプトと会心のスタートを切った。続くM大戦も豪雨の中、辛勝、着実に白星を重ねる。次は古豪N大戦である。しかし、最終目標は、あくまで「打倒K大」。ここで足元をすくわれるようなっことがあっては、今までやってきたことへのチームとしての自信が、崩れ始めてしまう。チームに油断が生まれることを何よりも恐れたマユゲは、ここで頭を坊主にしたのだった。
そしてむかえたN大戦。天然芝のきれいなグラウンド。秋のぬけるような晴天のもとで、試合は行われた。心配していた油断も見られず、オフェンスは第1クォーターからタッチダウンを重ね、ディフェンスも負けじとQBサック、インターセプトといったビッグプレーを連発。前半終了時点で既に大差がついていた。本来なら、マユゲのポジションの控えプレーヤーである三年生に後半を託し、実戦経験を積ませるべきシチュエーションであった。しかし、このときのマユゲは、四年間で一番体調もよく、とにかく学生生活最後のプレーを少しでも多く楽しみたい、そう思っていた。リーグのインターセプトリーダーを突っ走るなど記録の面でもプレーがしたかった。マユゲはここで、後半も引き続き出場するという判断をしたのだった。
そこで「事件」は起こった。
後半開始早々のプレー。ボールを持った敵ランニングバックが中央を突破し走り抜けてくる。それに対し、マユゲの前に位置する味方ラインバッカーが左右からタックルに向かう。正面からフォロータックルをかぶせに向かうマユゲ。いつもなら、倒れかかった相手にも容赦なく「かぶせ」を喰らわすところなのだが、味方のタックルで既に倒れかかった相手ランニングバックに対し何故かそのとき「かぶせずに許してやるか」的な思いが頭をよぎり、駆け寄るスピードを緩めたのだ。敵ランニングバックと味方二人が折り重なってこちらに倒れかかってくる。結果的に三人分の体重がマユゲの右太ももに集中するようなかたちになった。こらえきれず三人とともに倒れる。
その時、確かに痛みはあったが、「よくある『ももかん』(ももの前面を打撲すること)だ。別になんともない。」と思った。しかし、立ち上がろうとして、足が動かない。味方に肩を借りてサイドラインへ出る。すぐにアイシングを施し、しばらくの間、ゆっくりとストレッチをしながら、様子をみる。ひざは曲がる。立ち上がれる。走れる。大丈夫だ。そこでマユゲは致命的な判断ミスを犯したのだった。プレーしたい。ただその思いで再びフィールドに戻った……。
今思えば、これがその後の悲劇のはじまりであった。その試合後も、テーピングを巻いて練習を続け、次の試合にも出場。その中でまた腿に異常を感じたマユゲは、その段階になって初めて整形外科を訪れたのだった。診断結果は「骨化性筋炎」。聞いたこともない症名で、医者に詳しく尋ねると、外部からの強い衝撃によって圧迫を受けた骨に傷のようなものができ、そこから、接している筋肉に骨のカルシウムが溶け出す、という病気との説明。レントゲン写真には確かに骨から煙のようなものが広がっている様子がはっきりと写っていた。医者は続けて言う。このままでは筋肉が伸縮しなくなり、結果、ひざ関節が曲がらなくなってしまい、日常生活にも支障をきたすおそれがある。とにかく安静が必要であり、走れるのには少なくとも半年は必要…………。
ん、半年?嘘だろ?
そう思った。
何でなんだよ。何で俺なんだよ。何で今なんだよ……。
そして、頭が真っ白になった。
結果的には、負傷後プレーを続けてしまったことが炎症の悪化を招いたようだ。自分にとって公式戦唯一のパントリターンタッチダウンが、負傷直後のN大戦で生まれたことが皮肉であった。
思えばあのとき、一番恐れていた「奢り」が、他でもない自分にあったんだ。一瞬の気の迷いを生む、「弱さ」が自分の中にあったんだ。
◇
外に立って、見る
しばらくは絶望で自暴自棄になっていたが、当時の彼女やチームの仲間の支えもあり、その後チームに復帰した。プレーヤーとしてではなく、裏方として。その後、学園祭中の休みを利用した秋合宿をはさんで、I大戦、D大戦と続いたが、チームは厳しい試合を鬼気迫る気合で勝ち進み、全勝を守った。
そしてむかえた宿命の対決、K大戦。当然むこうも全勝で駒を進めてきた。勝ったほうがリーグ優勝を手にする。秋も深まり、落ち葉が散見される三鷹のグラウンドでその試合は行われた。
裏方として戦術や技術の指導にまわっていたマユゲも久々にユニフォームをまとってサイドラインに立った。皆のヘルメットには負傷で出場できないメンバーの背番号と同じステッカーが貼られていた。そこに、マユゲの「3」を見つけたとき、熱い思いがこみ上げたのを今でも覚えている。ともに戦っているんだ、という思いで皆がいてくれたのだ。大丈夫だ。絶対勝てる。ここ二年間、K大の壁に跳ね返されてきたけれど、客観的に見ても今年はいける。あとは気持ちだ。絶対に守るな。勝てると信じて攻めつづけろ。マユゲの気持ちはみんなにも伝わったと信じている。「やっぱり駄目なのか」とだけは一瞬たりとも思って欲しくない。一人でもそう思ったらそこから崩れていってしまうものだから。
試合は味方がタッチダウンで先制、反撃のタッチダウンを許すも、またオフェンスが取り返す、というこちらのペースで進む。モメンタムはこちらにあった。
しかし後半、敵ランニングバックの独走という、ひとつのプレーから歯車が徐々に狂いはじめる――。
(つづく)
2000年12月21日(木)
突然ですがわたくし、21世紀を前に、約五年勤めた会社を退職することを決心しました。
会社でもほぼ公表されたし、バッカスやリベンジャーズのみんなにもほぼ伝えられたので、ここで一度、「何故、今、辞めるのか」についてお話しておこうかと思い、久々にペンをとった次第。この間は余裕がなくてなかなか書けなかったからな。
まあ、随分前から考えていたことではあるんだが、年の瀬の今、「そもそも俺はどんな奴で、何に興味を持ち、何を良しとし、実際には何をして生きてきたのか?」、そして「21世紀を目前に控え、20代をあと3年残した今、俺は何をしようとしているのか?」なんてことを、自分の頭の整理も含め、つらつらーっと書いちゃおっかな。「わたくしごと」で恐縮ですが……。
◇
第一章 マユゲ幼少期〜大学時代
◇
マユゲ、生える
昭和48年9月5日、神奈川県川崎市にて、「正直」という名の父親と「良子」という名の母親の間に、二男として生を受ける。
AB型の両親から生まれた生粋のAB型、乙女座。後に立派に成長する眉毛は、母親ゆずりであったようだ。二人揃ってあまりにストレートな名前、そしてともに「センセイ」と呼ばれる職業に就く共働きの両親のもと、「間違っても悪いことはできない」というプレッシャーを潜在意識で抱えつつ、同時に、やんちゃを繰り返す三つ上の兄を見て育ち、「こーすると、こんなに怒られるのね」なんて涼しい顔して学習し、あまり怒られることを知らずに幼少期を過ごす。
小さい頃は今と違って、とても積極的・開放的な性格であったらしく、デパートなぞに連れて行こうものなら一瞬にして姿をくらます、迷子の常習犯であったとのことである。当時は広島カープの野球帽をこよなく愛し常に着用していたため、毎回のように「赤い帽子をかぶった四歳くらいの男の子が……」という館内放送にお世話になっていたとのこと。くしくも当時『とこちゃんはどこ?』とかいう幼児向け「ウォーリーを探せ!」系絵本が一部で流通していたらしいが、それは、大勢の人垣の中から、赤い帽子をかぶった主人公「とこちゃん」を探し出すというもの。両親曰く、当時のマユゲは、彼とかなりキャラがかぶっていたらしい。
◇
NOT「お受験」
小学校に入ると徐々に「おりこうさんキャラ」へのシフトがなされ、高学年になると四谷大塚に通い出すことになる。世の中は受験戦争真っ只中。そして我々の世代は、典型的な第二次ベビーブーマー。世間一般の親は、「有名私立中高→有名大学→一流企業」という、いわゆる"エリートコース"のレールに、競って自分の子を乗せようと必死になっていたときである。一見その世間の趨勢と同じように見えるが、正直と良子は、ちと違った。
子供の幸せを考えてくれるという点では共通するが、彼らの場合、そこには見栄的なものは皆無で、あくまで「今の日本はこんな世の中。この子が将来自分でやりたいことが見つかったときに、大学に行っていなかったことでハンデとならないようにしてやりたい」という思いのもと、実際決して裕福とは言えない状況の中、教育に資金を注いでくれたのである。
そんなわけで、当時のマユゲとしても、やらされている感覚はなく、すんなり、そして客観的にそのレールに乗ることを選択できたのである。四谷大塚では全国トップ賞を獲得するなど、一瞬は「俺は秀才なのか?」と血迷ったこともあったが、第一志望の中学にはあっさりと落とされ、第二志望の私立男子校に入学することとなる。そして同時に、マユゲの青春時代の舞台が、ベイブリッジ建設前の横浜になることが、このときに決まったわけだ。
◇
たぶんこの頃からが「青春」
中高一貫教育で高校入試がないことに加え、集まっている連中のほとんどが一流中学を落ちた奴らばかりであったこともあり、学園の雰囲気は実にのんびりとしたものであった。ガリ勉が少々、フツーがボリュームゾーンで、ワルがまた少々、といった構成比と言えば分かりやすいか。東大・京大に行く奴もいれば、プータローになっちゃう奴もいるような、教師からの押し付けのない、自由な校風だった。
このなかでのマユゲといえば、ワルのカテゴリーに属しつつ、中学時代はブラスバンドに入部。これはドラムをマスターしたかったという理由からだったわけだが、ここでクラシック、ジャズ、ポップスなど様々なジャンルの音楽に触れることとなった。
中学三年になると、兄の影響で小学五年生の頃から聞き始めた洋楽のコピーバンドを結成。「イカテン」に象徴されるバンドブームによって学園内にも多数あったロックバンドの中でも、一、二を争うイケてるバンドのドラマーとして精力的なライブ活動などを展開した。
高校に進むと、友人の勧誘にサクっとひっかかりブラスバンドを退部、突然アメリカンフットボール部に入部。一見、文科系から体育会系に180度鞍替えしたようだが、もともとマユゲはスポーツ好きでり、体育の授業時間には運動部の連中にまじり即席チームをつくって、体育教官チームとバレーボールの試合をしたりしていたものだ。親は、「これから大学受験に向かっていくときに、こんな危険なスポーツを始めて大丈夫なのだろうか?」と面食らっていたが、潜在的な"運動欲"があったのか、自分的にはこれまた、すんなり、であった。そしてこの後、このスポーツの魅力にずるずると引き込まれ、十年以上続けていくことになる。
あっちのほうはと言えば、恋という恋の思い出は特になく、仲良しだった女子高の子たちとの清いグループ交際を楽しんでいた。そのなかで、三枚目キャラの快感に目覚め、現在に至っているわけである。当時は渋谷チーマーのはしりの頃であったが、当校の生徒はファッションだけ。やってもパーティー(ドラッグなしだった)程度であり、ナイフを持っている奴がいても、それを使って実際にケンカする者はほとんどいなかったと思う。
付き合っていた女の子たちはと言えば、制服のスカートをやや短くはきこなし、ややルーズなソックスを愛用していた頃である。現在のような下品な女子高生ではなかった。みんなちゃんとソフィスティケイトされたセンスを持っていたし、知っている限りではセックスに関してもきちんと自分を大切にしていたと思う。振り返ってもとてもいい時代だったと思う。
学業的には「成績トップが集まるクラス」に出たり入ったりを繰り返しながら学年をあがっていった。高校一年時には、物理のテストで生まれて初めて「0点」というものを経験し、徐々に「俺って文系?」との認識を深め、最終的には「私立文系コース」を選択、予備校も行かず、のほほんと受験をむかえることとなる。しかし、三年の春の大会をもって部活を引退したあとは、運動部の連中は持ち前の集中力を発揮するもの。結局は受けた大学はほとんど合格し、大した苦労もせず現役で意中の大学に入れていただくことになった。そしてこの時、合格体験記などにえらそうなことを書かせていただくなど、人生二度目の有頂天を味わう。
◇
大学生活、そして卒業後の道は?
大学入学後は、学業には目もくれず(父上、母上、本当にごめんなさい)、再びアメフト漬けの日々。一年時には、合コンも精力的にセッティングし、無事「大学デビュー」を済ませた後は、次々とその面での「悪行」を繰り返す。いざというときになって相手に「どういうつもりなの?」と聞かれ、思わず目をそらしてしまうような、そんな恋愛とも呼べない男女関係がいくつか続いたものだ(その度に、「女の子を泣かせるようなことしては絶対駄目だよ」という良子の声が耳元から聞こえてくるようだった……)。
二年時にはレギュラーポジションを獲得、以後得意の必殺タックルを武器に「ディフェンスの最後の砦」的なポジションで地味な活躍を続けた。ちょうどこの頃、女子大から参加していた同学年のチームのマネージャーと恋に落ち、それまでの悪行を悔い改め、一途な男に変貌を遂げる。以後、社会人2年目頃まで、約3年半に渡って愛を育んだわけである。
三年時にはディフェンス・キャプテンに選ばれ、初めて組織の運営という難題を経験する。しかし、ライバル校にはどうしても勝てなかった……。
四年になると春は就職活動である。景気ドン底、就職大氷河期であったときだけに早々と動き出した周囲に流されながらも、卒業後の「行く先」探しを開始した。それなりの歳になってはいたものの、精神的にはとても子供であったマユゲはこのとき結果的に、単なる「次に行くところ探し」をしてしまったのである。
自分を見つめなおし、将来像を描く、という人生において誰もが一度は経験しなければならない、とても大切な作業を、マユゲは浅く捉えてしまったのだ。ここで人生を俯瞰して見れなかったことが後に大きな問題となるわけだが、当時は高校時代から「なんとなく」頭にあった広告業界に絞った就職活動を展開。志望動機もうすっぺらく、しっかりとした『意志』に基づく自分のビジョンを語ることができなかったマユゲは、電通・博報堂でボコボコ落とされ、ここで再び人生の挫折を味わうことになる。職種については、そう言うともっとも入りやすいといわれていた「営業志望です」と嘘をついて活動を進めた。
しかし縁あって、八月初旬、残っていた「そこそこ大手代理店」の内定をゲット、就職活動の精神的疲労もあり早々に入社を決め、活動をそこで終える決断をした。根底には「まだ社会に出る心の準備ができていない」という思いがずっとあったように思う。今思えば、つくづく甘チャンだったよな。でもそれは自分が蒔いた種。責任は自分でとらなければならない。
そしてすぐに夏のシーズンイン。チームに合流後は猛暑の中、就職活動でなまった体に鞭を入れまくる毎日。一年間務めたディフェンス・キャプテンをはずれ、一プレーヤーとして新鮮な気分で取り組む。役職をはずれると、それまでのプレッシャーから開放され、「プレーに集中できるとこんなにも楽しいものか」とさらにこのスポーツに傾注、学生時代最後となる秋のリーグ戦初戦では、一試合三インターセプトを記録するなど絶好調で走り回った。今年こそ、ライバル校をぶっ潰す。今年の戦力ならそれができる。そう信じていた――。
(つづく)
2000年12月20日(水)
| 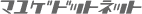 diary/column “mayuge の視点”
diary/column “mayuge の視点”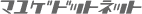 diary/column “mayuge の視点”
diary/column “mayuge の視点”