| 2010年05月07日(金) |
ドン・アスレット『そうじの達人』★★★☆☆ |
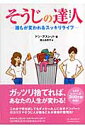
『そうじの達人』
ドン・アスレット
トランスワールドジャパン
こころに残ったところ。
「誰もあなたの手を取ってガラクタ屋に連れて行ったりしていない。ガラクタを取っておいたり、捨てたりするのはあなたなのだ。現在のガラクタ問題は、あなた自身が招いたものであり、あなたが黙認してしまったものだ。」(p31)
「ゴミの山があなた自身を物語る」(p40)
アメリカ先住民と白人の堤防決壊事故からの教訓。
「『でもどれもこれも価値があるんだよ』だって?蓄えたり、きれいにしたり、保険をかけたり、運んだり、守ったりするのに費やす時間や、人生の価値はどうなるのか?どれくらいの価値があるのか?」(p43)
「暮らすということは、あなたが最大の楽しみであり、最も刺激を与えてくれるものだと考えると、間違いなくガラクタは暮らしを邪魔しているのだ。」(p57)
「『もったいなくて使えない』モノは、一番バカバカしいガラクタである。」(p57)
もったいなくて使えないモノリストを作ってみよう,と言う提案は面白い!
使わないのももったいないけれど、
「どこにあるかも覚えていないガラクタがあるなんて、恥ずかしすぎる!」(p59)
「モノは、使う場所の近くに置くようにするとよい。(略)
自分の暮らし方や、一番よく使うものを考えてみよう。それはたんすの手前や手が届きやすい棚に置くべきだ」(p59)
「本当に必要で使うものの置き場所を正確に決める
使い終わったらすぐに、必ずその場所へ戻す」(p60-61)
「見たり、触ったりするたびに、心が和み、わくわくするというのなら捨てる必要はない。」(p66-67)
「食器セットなんかより、旅行や教育にお金をかけた方がよっぽど自分の成長のためになるだろうに。」(p76)
「一番道具をそろえて、準備している人に限って、一番何もやらない。」(p80)
「贈り物の意味と贈り物自体とを混同しないよう気をつけなければならない。」(p83)
「必要のないモノや使わないモノに手を出せば、以前は価値のあるモノだったとしても、新しい時間や達成感を求める能力を台無しにしてしまう。」(p92)
「形見の場合は、1つ質問するだけでいい。誰のために取ってあるのか?」(p93)
思い出は、最小にするというアイデア。
ミニチュアにする、厳選する、スクラップブックにする。
「人は誰しもこの世を去るが、魂は永遠だ。精神や遺産、伝説、影響は生き続ける!だから、家族にガラクタを残すことは不必要なだけではなく、不親切なのだ。」(p96)
不親切どころか、「愛情というより復讐行為だ。」(p97)とまで言う。
実際にガラクタのために家族がバラバラになったり訴訟を起こしたりといったトラブルを見ているから。
「写真の持つ価値は、見られることにある。それが不可能なら、なんのためにあるのだろうか?」(p123)
クローゼットの服整理の判別法法。
・自分が素敵に見えない
・身体に合わない、快適ではない
・複雑すぎる
・汚しやすい
・痛んでいる
・修繕が必要
・全く、めったに着ない
「モノが永遠であることはめったにないし、使わなければ価値はない。健康や才能や友情や経験や興奮は、私たちの中に蓄積し、いつもくっついていて、私たちをまた元気にしてくれ、新鮮にしてくれるのだ。」(p151)
「捨てるべきか、取っておくべきか?判断するときに考えや手が止まってしまったら、もしくは理論や感情でも決心がつかなければ、自分に問いかけてみよう。
『これがなかったら私の人生はどうなるだろう?』と。モノについて考えてはいけない。自分自身や人生、自由について考えることだ。」(p164)
ガラクタを処分するごとに、光がさしこんでくる。
力がわいてくる。
新しい自分になっていく。
そのために、ガラクタを手放すのは、今。
『そうじの達人』(楽天)
『そうじの達人―誰もが変われるスッキリライフ』(Amazon)
|