the HIATUS@zepp tokyo
2010年05月31日(月)
まあ色々ありつつ行ってきました久々のzepp。去年の彼らぶり。

内容はと言えばいつも通りの彼らで、気になることなんてしきりがクリエイティブマンなぐらい。
客は完全にHIATUSの客だった様子。
zeppは横長のバーでブロックを仕切っているので、その一番前方から攻めるのは鉄則。
客電が落ちて、一斉に前に進む人々と、後ろ側に残る人の間を見極め、そのギャップを利用して中央付近まで移動、始まってから前に進むのが一番賢いやり方。
こんなもみくちゃになるようなライブはもう彼らのライブくらいしか行っていないけど、やり方は全部覚えている。
今回で1stメインのセットリストはラストらしく、そこメイン。とは言えワンマンよりは短いセットリストなので全部をやるというわけにも行かなかった様子。
細美氏は髪がのびていて、逆にマサ氏は短くなっていた。気がする。
ライブ中の事はあんまり覚えておらず、どんな曲をやったかもうろ覚え。知らない曲はあったと思う。
ホリエさんの振る舞いが相変わらずピアニストで美しい。ウエノさんが楽しそう。
細美は相変わらずのように見えた。
気づくと彼らのライブは終わり、転換。
前に行きたそうな人々に前方は譲り、着替えてThird Eye Blind待ち。TEBは白人ライクなリズムを響かすゴキゲンな感じのバンド。上手奥に横向きにドラムがいて、その手前にベース。下手離れた位置にゴールドトップ使いのギターさん、センターがギターボーカルな感じ。
ベースはかなりローが深い、ドラムは前述の通り白人系リズムなドラマーさん、ギターはワウやら使って特徴的なサウンドメイク。ギタボさんは普通。声は強いなあ。
うーん、普通。
ただ、クオリティは高い。そこらへん、さすがに本場モンだな、と。
アンコールでは細美を呼びこんでデュエット(というのか?)したり、ラストの曲ではHIATUSメンバー全員が入場していかにもアメリカン!なノリで肩を組んだり抱き合ったりしたあげく、客に歌わせたまま退場するという日本のノリだとちょっと暴挙くらいな感じ。
ちょっと笑えたけど、なかなか爽やかに感動的であった。
やっぱりちゃんとしたライブってクオリティ高いっす。
また行こう。

内容はと言えばいつも通りの彼らで、気になることなんてしきりがクリエイティブマンなぐらい。
客は完全にHIATUSの客だった様子。
zeppは横長のバーでブロックを仕切っているので、その一番前方から攻めるのは鉄則。
客電が落ちて、一斉に前に進む人々と、後ろ側に残る人の間を見極め、そのギャップを利用して中央付近まで移動、始まってから前に進むのが一番賢いやり方。
こんなもみくちゃになるようなライブはもう彼らのライブくらいしか行っていないけど、やり方は全部覚えている。
今回で1stメインのセットリストはラストらしく、そこメイン。とは言えワンマンよりは短いセットリストなので全部をやるというわけにも行かなかった様子。
細美氏は髪がのびていて、逆にマサ氏は短くなっていた。気がする。
ライブ中の事はあんまり覚えておらず、どんな曲をやったかもうろ覚え。知らない曲はあったと思う。
ホリエさんの振る舞いが相変わらずピアニストで美しい。ウエノさんが楽しそう。
細美は相変わらずのように見えた。
気づくと彼らのライブは終わり、転換。
前に行きたそうな人々に前方は譲り、着替えてThird Eye Blind待ち。TEBは白人ライクなリズムを響かすゴキゲンな感じのバンド。上手奥に横向きにドラムがいて、その手前にベース。下手離れた位置にゴールドトップ使いのギターさん、センターがギターボーカルな感じ。
ベースはかなりローが深い、ドラムは前述の通り白人系リズムなドラマーさん、ギターはワウやら使って特徴的なサウンドメイク。ギタボさんは普通。声は強いなあ。
うーん、普通。
ただ、クオリティは高い。そこらへん、さすがに本場モンだな、と。
アンコールでは細美を呼びこんでデュエット(というのか?)したり、ラストの曲ではHIATUSメンバー全員が入場していかにもアメリカン!なノリで肩を組んだり抱き合ったりしたあげく、客に歌わせたまま退場するという日本のノリだとちょっと暴挙くらいな感じ。
ちょっと笑えたけど、なかなか爽やかに感動的であった。
やっぱりちゃんとしたライブってクオリティ高いっす。
また行こう。
小沢健二@中野サンプラザ
2010年05月25日(火)
姉から聞かされた「LIFE」。
調べてみたところ、初めて聞いたのはおそらく小学生の頃。姉が中学の技術の時間に作ったと言うCDをジャケットごとしまえるケースに入れていたのを覚えているので、ほぼ間違いないだろう。
たしか透明でちょっと柄の入ったカセットテープに吹き込んで、横長のダブルカセットなラジカセで聞いていたように思う。
その当時、どんな思いで聞いていたのか、全く覚えていない。
ただ、子どもでも聞けるくらいポップなメロディラインのアルバムだったことは確かだろう。
その後、再びLIFEを手にとったのは高校の頃。おそらくHIPHOPというものが世間的に認知されだした時に、記憶に残っているラップミュージックが「ブギーバック」だった事がきっかけだったように思う。ゆったりとしたリズムに聞き覚えのあるメロディラインとラップ。その音楽に対する先見性(そしてヒットさせた事実)に驚きながら聞き入ったものだった。
その後は頻繁に聞くに至っていなかった「LIFE」。しかし、iPodを手に入れて以降、再び思い出しては聞くアルバムになっていた。
その頃には渋谷系なんて言葉はキレイに無くなっていて、小沢健二もほとんど活動らしい活動をしていなかった。
生で「LIFE」の音に接せられなかった事はジェネレーションの差として納得しつつ少し悔しかったけれど、06年に発売したアルバムがボーカルレスのアルバムだった事実もあり、仮に小沢健二が活動していても「LIFE」の曲はあまりやらないんじゃないかという思いも手伝ってある程度の納得は出来ていた。
そんな中、「LIFE」収録楽曲を中心とするコンサートツアー「ひふみよ」が驚きと共に発表。
これはジェネレーションの差を埋めるタイミングが来たとばかりに、チケット入手の幸運も手伝い、中野サンプラザへと行ってきたのであった。

迎える5月25日。多少の緊張を持ちながら中野サンプラザ、ホール内へ。
開演、完全に暗闇のホール内。歌声が響いて後、詩(?)の朗読が始まる。
停電のアメリカ東海岸。歌声でつながる人々。小沢健二がつぶやく詩には強いメッセージが感じられた。
セットリストは黄金。
新曲を交えつつ、大胆にリアレンジされたサウンドの裏に、この数年で小沢健二がインプットした膨大な世界を感じることが出来た。
途中、「ブギーバック」のラップ部分をお客さんがシンガロングした場面では、あまりのシュールさに少し笑ってしまった。
間に挟む詩では、だいたいにおいて象徴的な事象を身近な友人やその辺にいるだろう人々の声として紹介し、その意味を歌につなげるという趣旨。
まるで久しぶりなライブと感じさせないステージングを披露するオザケンだけど、客席は盛り上がりつつも多少乗り切れていないようにも見えた。
なんだろうなあ、なんとなく一体感を感じない。
そんな事を考えながらステージを見ていると、気づいた。
ああ。小沢健二っていうのは、声に感情が乗らない人なんだ、と。
小沢健二の歌声はとてもパーカッシブ。
独特の響く声、通る声を持ってはいるけれど、その上に彼の情緒は乗らず、全ての要素は彼の紡ぎだすメロディラインと言葉にのみ宿っているんだ、と。
つまり、小沢健二の歌声は小沢健二自体の熱量を伝えるものではなく、聴いている各々の心象風景を表層心理に強く引き出す作用をもった声なんだと言うこと。
暑苦しくなく、感情の発露でもない。理性的で確信的な言葉とメロディラインの上で、あくまでもナチュラルな歌声のまま感情を引き出されてしまう小沢健二の声が、“おしゃれ”なまま音楽に心乱されたい人々のニーズに合致したんだろう。
だからこそ、当時「渋谷系」ともてはやされ、いわゆる“おしゃれ”であることを好む人々に好かれたんだな、と。
それに気づいたときに、この空間がコンサートであるという事実にも気づいた。“ライブ”ではなく、“コンサート”という空間。
改めて回りを見渡すと、ライブの一体感とはまた違う、コンサート特有の幸福感がそこに生まれていた。
おそらく、みんな小沢健二の歌というフィルターを通して、自分の人生の幸せだった瞬間を思い出したり、すばらしかった青春時代を見返したりしていたのだろう。
時を越える、それもまた、音楽の力なんだろうか。
初めて見た小沢健二はアーティストとしても、シンガーとしても、特別なギフトは感じられなかった。
けれど、あそこまで理性的で確信的なまま素晴らしい音楽を発信できる小沢健二という人間こそが、意外と多くいるシンガー的ギフトをもった通り一辺の“アーティスト”達を軽く凌駕する、生粋の“音楽家”の姿なんだろう。
結局、ジェネレーションの差は埋まらなかったかなあ。
けれど、素晴らしい夜でした。
調べてみたところ、初めて聞いたのはおそらく小学生の頃。姉が中学の技術の時間に作ったと言うCDをジャケットごとしまえるケースに入れていたのを覚えているので、ほぼ間違いないだろう。
たしか透明でちょっと柄の入ったカセットテープに吹き込んで、横長のダブルカセットなラジカセで聞いていたように思う。
その当時、どんな思いで聞いていたのか、全く覚えていない。
ただ、子どもでも聞けるくらいポップなメロディラインのアルバムだったことは確かだろう。
その後、再びLIFEを手にとったのは高校の頃。おそらくHIPHOPというものが世間的に認知されだした時に、記憶に残っているラップミュージックが「ブギーバック」だった事がきっかけだったように思う。ゆったりとしたリズムに聞き覚えのあるメロディラインとラップ。その音楽に対する先見性(そしてヒットさせた事実)に驚きながら聞き入ったものだった。
その後は頻繁に聞くに至っていなかった「LIFE」。しかし、iPodを手に入れて以降、再び思い出しては聞くアルバムになっていた。
その頃には渋谷系なんて言葉はキレイに無くなっていて、小沢健二もほとんど活動らしい活動をしていなかった。
生で「LIFE」の音に接せられなかった事はジェネレーションの差として納得しつつ少し悔しかったけれど、06年に発売したアルバムがボーカルレスのアルバムだった事実もあり、仮に小沢健二が活動していても「LIFE」の曲はあまりやらないんじゃないかという思いも手伝ってある程度の納得は出来ていた。
そんな中、「LIFE」収録楽曲を中心とするコンサートツアー「ひふみよ」が驚きと共に発表。
これはジェネレーションの差を埋めるタイミングが来たとばかりに、チケット入手の幸運も手伝い、中野サンプラザへと行ってきたのであった。

迎える5月25日。多少の緊張を持ちながら中野サンプラザ、ホール内へ。
開演、完全に暗闇のホール内。歌声が響いて後、詩(?)の朗読が始まる。
停電のアメリカ東海岸。歌声でつながる人々。小沢健二がつぶやく詩には強いメッセージが感じられた。
セットリストは黄金。
新曲を交えつつ、大胆にリアレンジされたサウンドの裏に、この数年で小沢健二がインプットした膨大な世界を感じることが出来た。
途中、「ブギーバック」のラップ部分をお客さんがシンガロングした場面では、あまりのシュールさに少し笑ってしまった。
間に挟む詩では、だいたいにおいて象徴的な事象を身近な友人やその辺にいるだろう人々の声として紹介し、その意味を歌につなげるという趣旨。
まるで久しぶりなライブと感じさせないステージングを披露するオザケンだけど、客席は盛り上がりつつも多少乗り切れていないようにも見えた。
なんだろうなあ、なんとなく一体感を感じない。
そんな事を考えながらステージを見ていると、気づいた。
ああ。小沢健二っていうのは、声に感情が乗らない人なんだ、と。
小沢健二の歌声はとてもパーカッシブ。
独特の響く声、通る声を持ってはいるけれど、その上に彼の情緒は乗らず、全ての要素は彼の紡ぎだすメロディラインと言葉にのみ宿っているんだ、と。
つまり、小沢健二の歌声は小沢健二自体の熱量を伝えるものではなく、聴いている各々の心象風景を表層心理に強く引き出す作用をもった声なんだと言うこと。
暑苦しくなく、感情の発露でもない。理性的で確信的な言葉とメロディラインの上で、あくまでもナチュラルな歌声のまま感情を引き出されてしまう小沢健二の声が、“おしゃれ”なまま音楽に心乱されたい人々のニーズに合致したんだろう。
だからこそ、当時「渋谷系」ともてはやされ、いわゆる“おしゃれ”であることを好む人々に好かれたんだな、と。
それに気づいたときに、この空間がコンサートであるという事実にも気づいた。“ライブ”ではなく、“コンサート”という空間。
改めて回りを見渡すと、ライブの一体感とはまた違う、コンサート特有の幸福感がそこに生まれていた。
おそらく、みんな小沢健二の歌というフィルターを通して、自分の人生の幸せだった瞬間を思い出したり、すばらしかった青春時代を見返したりしていたのだろう。
時を越える、それもまた、音楽の力なんだろうか。
初めて見た小沢健二はアーティストとしても、シンガーとしても、特別なギフトは感じられなかった。
けれど、あそこまで理性的で確信的なまま素晴らしい音楽を発信できる小沢健二という人間こそが、意外と多くいるシンガー的ギフトをもった通り一辺の“アーティスト”達を軽く凌駕する、生粋の“音楽家”の姿なんだろう。
結局、ジェネレーションの差は埋まらなかったかなあ。
けれど、素晴らしい夜でした。
rain drops pianissimo@下北沢CLUB251
2010年05月21日(金)

割としばらくぶり(?)のrdp。
上手から見てみた。
今回はdrに注目してみる。
多少迷いが透けて見えるドラミング。なにか悩んでいるのだろうか。スタイルと公言していた身振りの大きいドラミングも心なしか小さい。
プレイとしては、エイトビート主体のリズムパターンが多く、フィル以外の場面でスネアワークが少ないのが気になる。
もう少し表情をつけたスネアワークを増やすと曲の表情も変わってくるんじゃないかね。16分的なハイハットを入れるとか。
まあ、ただただ疾走感が欲しい時とかはシンプルなスネアでもいいんだけど、さすがに一本調子過ぎるかなという気もする。
gtvoはジャズマスターに変えてしばらくたつし、音もそれなりにこなれてきている。
たまにハイがきつすぎるかなあ、という印象もあるけど総じて335よりはマッチ。
ボーカルもこの日は安定していたように見受けられたし、前よりもナチュラルにやっている印象。存在感も出てきた。
ギターでも魅せれるようになれば結構良い感じになりそう。
baはこの日ローが強め。
プレイ的には特に問題なかったのだけど、存在感をあまり感じない。なんでだろう?“やりそう”な空気が無いのよね。
さらっと弾いてるように見える。
gtは出音的にはいつも安定している印象。アンプのキャラクターを掴んでいるし、自分の出したい音をわかっているんだなと。
ただ、コーラスを多用するクリーントーンのスタイルがたまに気になる。これは俺の趣味の問題だと思うけどね。
ミストーンがもっと減ってくればいいなーと。
そんな感じで。
その後のEarls Courtというバンドが中々。
割と分かりやすい大衆性をもちつつ、バタ臭さはあまり感じない。好きなことをやっている感が良い感じ。
音の作りが上手いなあ、というのは感じた。
なかでも一番プレイアビリティを感じたベースさんがサポートだったというのはアレだけど、とは言え中々に良きバンドでした。
ラストはSemiHumanSize。人力ハウスバンド。
もう少しボーカルに強さ(というか“何か”)を感じれたら、もっと良いんだろうなとは思った。
まあしかし、ハウス的なバンドだからこそのサンプリング的ボーカルスタイルが逆にマッチするかもしれない。
ライブハウスで人力なハウスサウンドを聞けるのは楽しいんだけど、CDになると途端にむつかしくなるんだろうなあ。
だって、音源だと人力だろうがなかろうが関係なくなってしまうもんね。
ライブハウスという空間にどれだけハウス的サウンドが好きな人が集まるか、というのも中々難しいような気もする。かといってクラブとかでやるのも難しい。
まあ、クオリティが激しく高くなれば問題ないだろうけど。
そういう意味ではまた見てみたいかもしれん。
session@新宿LOFT bar
2010年05月17日(月)
LITEのドラムさんがLoftbarの一日店長な日。
barスペースでセッションをするとの噂を聞いたのでいってみた。
深夜1時から始まったセッションはツインドラム、1パーカッション、1キーボード、2ベース、1ピアニカ&パーカッション、1ギターという編成。
メンツは以下は感じだった様子。
shimoryo (the chef cooks me)
takuto (about-tess)
イワモーター (kuruucrew)
shingo maeda (birds melt sky)
aki miyazoe (birds melt sky)
takashiishiwata (camellia)
内海 絵里 (DARLING DARLING)
Jun Izawa (LITE)
Akinori Yamamoto (LITE)
なんかベースの人がゴリゴリいってんなと思ってよく見たらLITEのベースさんだった。ドラムはkuruucrewの人でなかなかパワフルかつ独特のグルーヴ感があった。
セッションてやはり楽しい。今度自分もホーン絡めたフリーセッションの予定があるので、そこに向けてモチベーションが上がったのであった。
帰り際、takutoさんと少し話す機会があり、ご挨拶。
barスペースでセッションをするとの噂を聞いたのでいってみた。
深夜1時から始まったセッションはツインドラム、1パーカッション、1キーボード、2ベース、1ピアニカ&パーカッション、1ギターという編成。
メンツは以下は感じだった様子。
shimoryo (the chef cooks me)
takuto (about-tess)
イワモーター (kuruucrew)
shingo maeda (birds melt sky)
aki miyazoe (birds melt sky)
takashiishiwata (camellia)
内海 絵里 (DARLING DARLING)
Jun Izawa (LITE)
Akinori Yamamoto (LITE)
なんかベースの人がゴリゴリいってんなと思ってよく見たらLITEのベースさんだった。ドラムはkuruucrewの人でなかなかパワフルかつ独特のグルーヴ感があった。
セッションてやはり楽しい。今度自分もホーン絡めたフリーセッションの予定があるので、そこに向けてモチベーションが上がったのであった。
帰り際、takutoさんと少し話す機会があり、ご挨拶。
奥田民生「ひとりカンタービレ」@渋谷AX
2010年05月08日(土)
3年半ぶり?くらいのAX。だって、見たいバンドはAXではほとんどやらないんですよ。

そんなわけで「ひとりカンタービレ」。
3時間半をかけてドラム、ベース、ギター等と録音して公開ひとりレコーディングやっちまおう、という実にOT的な企画。
まあバンドみたいなもんをやっているおかげでチケットをゲット出来たわけでして、行ってまいりました。
ご一緒した方のアレもあって少し遅れてはいると丁度ベースの録音中。なんだよ、ドラムみたかった…なんて思いながらもベースを凝視。
ベースはアンプとDIの2本とも録ってDAW上でミックスしている様子。
パンチインで部分的な修正など施しつつ、つつがなく録音が進む。さすがOTさん、うまいっす。
次はギター録音。
ギターはギブソンの「持ってる中で一番高いヤツ」というレスポールゴールドトップ。アンプはマーシャルがもってきたという小〜中型のアンプで、OT曰く「ミルキーな音がする」というアンプ。
たしかにそのとおりギブソン+マーシャルながら、丸みのある爽やかな音。
ギタープレイも中々秀逸。もたつきを作りながらもテンポ感を乱さないプレイ。リテイクも殆ど無く、ピンポイントの修正数カ所でサクサクとレコーディングが進む。
その次はアコギ。
こちらはSM57でマイキング。アルペジオなども使いつつ、どちらかというとピッキングノイズをうまく使ったパーカッシブなアコギの使い方がメイン。ミドルテンポの曲に推進力をプラスさせていた。
次のタンバリンと鈴で客の笑いを誘いつつ、曲中では風味を加える隠し味的なサウンドを吹き込む。これまたSM57で録音。
そんなこんなで一端休憩して歌録り…かと思いきやギターソロを取り忘れていたのでした。
ギターはかわらずギブソン。アンプは後ろから持ってきたアクリル製?透明の小型マーシャル。これが良い音していた。
ギターソロがこれまたカッコよく。ってかリテイク無しってどうよこれ。OTさんやっぱりギター上手い。
そしてお待ちかね歌入れ。
座りながら、アコギとパーカッションを入れたSM57に口をくっつけるようにして歌う。
客席も曲の輪郭がわかってきた段階での歌入れとあって盛り上がる。
一発目、すごい。OTサウンドがそのまま。当たり前なんだけどやっぱり民生は歌い手だな、と。
鉛筆書きの絵に魔法で色がついていくように、鮮やかに歌が出来上がっていく。圧巻の声。
だけど、一発目はさすがにテストだったらしい。
本番の歌入れ。ダブルでやるらしく、フェイクとかは殆どいれずにしっかりと歌うOT。
さすがにダブルだと一発というのは難しいらしく、2回目は箇所箇所でリテイクを入れていた。それにしても驚異的なスピード。どんだけ上手いんだよ、ってかどんだけ歌入れ慣れてんだよ、という感じで。
当たり前なんだけどね、プロですもの…。だけど改めて目の当たりにすると新鮮な感動を覚える。
コーラスやハモリもほとんど滞り無く進み、あっという間(といっても3時間後)にレコーディング終了。
休憩を挟んで質疑応答。その後、とりあえずラフミックスした曲を流してライブ終了。
その後ミックス作業に入り、1時頃に配信開始するとのこと。なかなかのスピード感。
見ていて思ったのは、当たり前のことだけどプリプロを徹底してやっているなあ、ということ。
サウンドセッティング、ミキシングセッティング、下手したら(というか多分)ミックスダウンエフェクトまでリハで設定済みでもう本当に音入れだけすればOKな状況になっているな、と言うこと。
そしてOTさん楽器うまいっす、パねえっす、ということ。
そしてやはり歌に一番こだわっていたこと。
ギターソロの時も会場含め空気が変わったけど、やっぱり歌入れが一番緊張感があったし、一番感動的だった。
やはりライターとして、プロデューサーとして、シンガーとして第一線で長年やってきている人は違いますね…
ヤル気なさげでバイタリティある、OTという人にはやはり憧れてしまいます。

そんなわけで「ひとりカンタービレ」。
3時間半をかけてドラム、ベース、ギター等と録音して公開ひとりレコーディングやっちまおう、という実にOT的な企画。
まあバンドみたいなもんをやっているおかげでチケットをゲット出来たわけでして、行ってまいりました。
ご一緒した方のアレもあって少し遅れてはいると丁度ベースの録音中。なんだよ、ドラムみたかった…なんて思いながらもベースを凝視。
ベースはアンプとDIの2本とも録ってDAW上でミックスしている様子。
パンチインで部分的な修正など施しつつ、つつがなく録音が進む。さすがOTさん、うまいっす。
次はギター録音。
ギターはギブソンの「持ってる中で一番高いヤツ」というレスポールゴールドトップ。アンプはマーシャルがもってきたという小〜中型のアンプで、OT曰く「ミルキーな音がする」というアンプ。
たしかにそのとおりギブソン+マーシャルながら、丸みのある爽やかな音。
ギタープレイも中々秀逸。もたつきを作りながらもテンポ感を乱さないプレイ。リテイクも殆ど無く、ピンポイントの修正数カ所でサクサクとレコーディングが進む。
その次はアコギ。
こちらはSM57でマイキング。アルペジオなども使いつつ、どちらかというとピッキングノイズをうまく使ったパーカッシブなアコギの使い方がメイン。ミドルテンポの曲に推進力をプラスさせていた。
次のタンバリンと鈴で客の笑いを誘いつつ、曲中では風味を加える隠し味的なサウンドを吹き込む。これまたSM57で録音。
そんなこんなで一端休憩して歌録り…かと思いきやギターソロを取り忘れていたのでした。
ギターはかわらずギブソン。アンプは後ろから持ってきたアクリル製?透明の小型マーシャル。これが良い音していた。
ギターソロがこれまたカッコよく。ってかリテイク無しってどうよこれ。OTさんやっぱりギター上手い。
そしてお待ちかね歌入れ。
座りながら、アコギとパーカッションを入れたSM57に口をくっつけるようにして歌う。
客席も曲の輪郭がわかってきた段階での歌入れとあって盛り上がる。
一発目、すごい。OTサウンドがそのまま。当たり前なんだけどやっぱり民生は歌い手だな、と。
鉛筆書きの絵に魔法で色がついていくように、鮮やかに歌が出来上がっていく。圧巻の声。
だけど、一発目はさすがにテストだったらしい。
本番の歌入れ。ダブルでやるらしく、フェイクとかは殆どいれずにしっかりと歌うOT。
さすがにダブルだと一発というのは難しいらしく、2回目は箇所箇所でリテイクを入れていた。それにしても驚異的なスピード。どんだけ上手いんだよ、ってかどんだけ歌入れ慣れてんだよ、という感じで。
当たり前なんだけどね、プロですもの…。だけど改めて目の当たりにすると新鮮な感動を覚える。
コーラスやハモリもほとんど滞り無く進み、あっという間(といっても3時間後)にレコーディング終了。
休憩を挟んで質疑応答。その後、とりあえずラフミックスした曲を流してライブ終了。
その後ミックス作業に入り、1時頃に配信開始するとのこと。なかなかのスピード感。
見ていて思ったのは、当たり前のことだけどプリプロを徹底してやっているなあ、ということ。
サウンドセッティング、ミキシングセッティング、下手したら(というか多分)ミックスダウンエフェクトまでリハで設定済みでもう本当に音入れだけすればOKな状況になっているな、と言うこと。
そしてOTさん楽器うまいっす、パねえっす、ということ。
そしてやはり歌に一番こだわっていたこと。
ギターソロの時も会場含め空気が変わったけど、やっぱり歌入れが一番緊張感があったし、一番感動的だった。
やはりライターとして、プロデューサーとして、シンガーとして第一線で長年やってきている人は違いますね…
ヤル気なさげでバイタリティある、OTという人にはやはり憧れてしまいます。
MIRROR/LITE@渋谷CLUB QUATTRO
2010年05月01日(土)
LITE率いるParabolicaと9dw率いるcatuneのスプリットツアー「ParaboliCatune」だそうな。
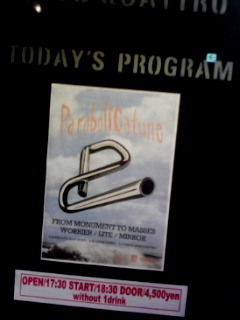
そんな感じで個人的な新世代ジャパニーズ2大インストバンドであるLITEとMIRRORが対バンだなんて絶対行くしか無いぜ、ってことで行ってきました。
入るとMIRRORなセッティング。心配していた人のいりも結構入っていて、SOLDとかでは無いにせよ採算は全然取れてそうな雰囲気。
そんな感じで開演時間ちょい押しでMIRRORスタート。撮影スタッフの邪魔くさい事この上なかったりしつつ。
下手ギターさんのアンプはBLUES CUBEに戻っていた。クアトロレベルの大きめなステージだと、中音をメインで聞くことになる最前付近はBLUES CUBEだと音量的にちょいと厳しかった。まあ時間がたつにつれ耳が慣れてきたのか良い感じはなってきたけど。
バンドサウンドはいつも通りの華やかな感じ。ロックなリズム感で、跳ねた感じの踊れるインスト・ロック。非常にメロディックなギターのライン。相変わらず素晴らしい。
上手ギターさんのMCはいつもの飄々としたスタイルとは違ってまったりとした雰囲気。総勢4バンドで回ったショートツアーの余韻残るMCでした。
そんなこんなで大体35分くらいのセット。
お次はLITE。おいおい、日本勢が先に2発くるのかよ、と。
MIRRORとは打って変わって、シリアスで重いトーン。下手ベースさんは痩せすぎだろうってくらい痩せていて、もうちょいホコっとしてた方が柔和な印象でいいのになあ、なんて思いながら見ていた。
サウンドはソリッドかつヘヴィ。一聴して日本のバンドっぽくない。それにしても初見の時と比べると段違いにスケールが大きくなっていて、毎回新鮮な驚きを感じる。
turns redの曲はやらず、それ以前の数曲と新曲だという2曲(これまたプログレッシブを感じさせる出来で、かっこよかった)、ラストはrecollection。キメだけじゃなく、雰囲気を作る曲もLITEの味が出てて良い。初期はむしろキメよりも雰囲気感の方が強く出ていたような気もするし。
いやー、大いに満足。
残りのバンドはサラッと見て、帰宅。
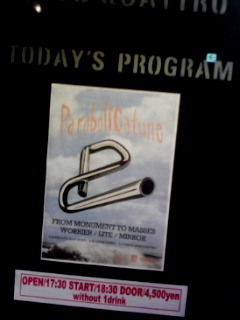
そんな感じで個人的な新世代ジャパニーズ2大インストバンドであるLITEとMIRRORが対バンだなんて絶対行くしか無いぜ、ってことで行ってきました。
入るとMIRRORなセッティング。心配していた人のいりも結構入っていて、SOLDとかでは無いにせよ採算は全然取れてそうな雰囲気。
そんな感じで開演時間ちょい押しでMIRRORスタート。撮影スタッフの邪魔くさい事この上なかったりしつつ。
下手ギターさんのアンプはBLUES CUBEに戻っていた。クアトロレベルの大きめなステージだと、中音をメインで聞くことになる最前付近はBLUES CUBEだと音量的にちょいと厳しかった。まあ時間がたつにつれ耳が慣れてきたのか良い感じはなってきたけど。
バンドサウンドはいつも通りの華やかな感じ。ロックなリズム感で、跳ねた感じの踊れるインスト・ロック。非常にメロディックなギターのライン。相変わらず素晴らしい。
上手ギターさんのMCはいつもの飄々としたスタイルとは違ってまったりとした雰囲気。総勢4バンドで回ったショートツアーの余韻残るMCでした。
そんなこんなで大体35分くらいのセット。
お次はLITE。おいおい、日本勢が先に2発くるのかよ、と。
MIRRORとは打って変わって、シリアスで重いトーン。下手ベースさんは痩せすぎだろうってくらい痩せていて、もうちょいホコっとしてた方が柔和な印象でいいのになあ、なんて思いながら見ていた。
サウンドはソリッドかつヘヴィ。一聴して日本のバンドっぽくない。それにしても初見の時と比べると段違いにスケールが大きくなっていて、毎回新鮮な驚きを感じる。
turns redの曲はやらず、それ以前の数曲と新曲だという2曲(これまたプログレッシブを感じさせる出来で、かっこよかった)、ラストはrecollection。キメだけじゃなく、雰囲気を作る曲もLITEの味が出てて良い。初期はむしろキメよりも雰囲気感の方が強く出ていたような気もするし。
いやー、大いに満足。
残りのバンドはサラッと見て、帰宅。