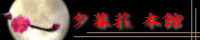時を忘れてものを書くのに没頭したりする私は、決してプロではないのだけど、きっと同じように、ワープロやら原稿用紙に向かったことのある人なら、1度くらいは「ことばの無力さ」みたいなものを感じたことがあるのではなかろうか、と、最近頓に思うようになった。
そういうジレンマを越えたところに言霊というものが待っていて、書き手を救うかのような幸せを少しだけ落としていってくれる。
ところで。
前にものの本で、こういうくだりを見たことがある。
「自分のことについて文章を書かせたり話をさせたりすると、ある特定のことばが何度も何度もくり返し出てくることがある。それは得てして、そのことばが今、その本人にないことのほうが多い。」
例えば、口では 「俺は自由だから」 「自由に生きるんだ」 「俺の自由を邪魔しないでくれ」 と言う人に現実、自由はない・・・・という具合。
まぁ・・・・一理ある。
で、ついこの間、ある人のHPを見ていた時に、「幸福」とか「幸せ」とかいうことばがふんだんに散りばめられた章を見つけてしまい、少し哀しかった。上記の例を鵜呑みにするわけではないが、それでもその文を読むと、幸せの主張だとかそういうことが書いてあるはずなのに、ひしひしと薄幸感が漂ってきている。ご本人はきっと無為自然に思いを綴られたのだろう。それでもこんな色としてこちらに伝わってしまうというこの現実・・・・不思議なものです。
舞台の稽古をしていても、ことばの無力さにぶつかることは多い。
演出家によっては、こちらが発した微妙な音のニュアンスからきっちりと感情を読み取る人もいて、同じシーンで何度も何度も同じダメを出される(当たり前なんだけど(笑))。そういうことを繰り返しているうちに、今自分がどんなことを言わなければならないのかということまで麻痺してきて、何が何だかわからなくなってしまうなんていうのもよくある話(爆)。私だけだったりして( ̄∇ ̄;)
文字として書き表してしまえば、確実な1つの意味をもつ。同音異義語なんていうのもあるが、文章になっていれば、前後の流れでだいたいの察しはつく。が、それを音として発すると今度は確実な色がつく。絵の具でいうなら、筆からたった一滴水をたらしたか否かの違いだけで、ことばの印象も随分違ってくるようだ。これもまた不思議。
私なんかは、たった一言「こんにちは」というシーンで、全く違うニュアンスでを20パターンくらい要求され、挙句に「あ・・・・8回目のやつ」などと言われ、混乱してました。・・・・だったら8回目のときに指摘してくれよ、みたいな(爆)。
そんなこんなでつい最近・・・・。
まさに「ことばの無力さ」を痛感させられることがあった。何を言おうにも、相手には「音」としか識別できないのだろう、ということに気づいた時の怖さといったらなかった。その時、会話の相手は電話のむこうで、顔も見えなければ側に寄り添っているわけでもない。いくら気持ちをこめようとも、どんな美辞麗句を並べようとも、このときばかりは無意味だと思い、絶句してしまうしかなかった。
感情はそこに確かにあるのに、音がなくなり、伝えるすべを失ったとき、私は自分の無力さを思った。
ドラマや映画、小説なんかでも音(ことば)のないシーンというのは沢山でてくる。それを、色んな手法を駆使して、感情の交錯みたいなものを表現するのだ。ことば(音)で表現しきれないと、作り手が認めてしまった結果だ。
私も、自分のHPをはじめ、数々の手法を用いて、ことばでの表現を続けてきた。あるいは音で、あるいは活字で、あるいは肉筆で。そのたびに評価を下す人が周囲にいて、そのおかげで私も微々たる進歩を続けているわけだ。
が・・・・・・。
ことばに魂が宿るなど、そうそう容易に起こり得るものではない。ことば全てに魂が宿ると考えるやり方は、思いあがりなような気もする。響く「音」にするためには、少なくとも真摯さが必要だということかもしれない。
身を削り、心を削り、少なくともどこかで「痛み」のようなものを感じながら、何かを込めないことには「ことば」として成立しないものだから、必死になる。
「こんにちは」と一言申し述べるために、2時間かけた演出家のこだわりはここにある。
私は無力です。
ことばを並べるだけなら、誰にだってできるのです。
そのことばが魂をもつ・・・・・なんてことは望んでません。
ただ、せめて。
四肢をもち、意志をもつものになればいいなと思うのです。
|