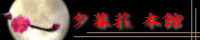| 2001年10月17日(水)
|
実りの季節 〜頭を垂れる稲穂たちの昨今の事情〜 |
最近、みそひともじをサボっていました。
そんなわけでさっそく1首。
この間、病院からの帰り道。
表の国道は通らずに、自宅から直線距離に近い道ばかりを選んで帰ったところ
見事に秋の色をたたえた田んぼやら畑やら・・・・
あと、柿の木とか。
大垣名産・柿羊羹(某K嬢には献上いたした)は
文字通り、柿から出来ている羊羹で、
小豆では出せない、小粋な甘さがなかなかいかしている。
街では有名な「T」という御菓子屋(主に和菓子)の倉庫の前を通ると
この時期、いっせいに干し柿作りの作業が始まる。
干し柿は言わずもがな、渋柿から作るので
この街には、甘い富有柿が乱立しているなどという夢の世界は存在しない。
柿の木を見つけて
あ♪ 柿やぁ♪ ( ̄¬ ̄*) 〜♪
と、心をときめかすと
それは必ずといっていいほど渋柿で、枝に重いほどの実をたたえていても
誰も手をつけない。
観賞用としては最高だ。
京都の落柿舎の柿も確か渋柿・・・・。
ものの雅や侘び寂びには、甘い柿よりも
枝に残りやすい渋柿のほうがよろしいのであろう。
幼少のみぎり、「柿どろぼー」は縁遠かったが
この時期になると
某御菓子屋(T)のお屋敷から枝が伸びているざくろや
某工場裏手にある大きな無花果の木からその実を盗んだのを思い出す。
果物屋で売っているのを見かけても、
絶対に買うことのない、ざくろや無花果。
どうしてそんなに執着していたかというと、
やっぱり「盗む」というスリルを楽しむこと、
そのものに面白味を見出していた感がある。
ただ、ざくろにしても無花果にしても
幹が細く、柔らかいので、木によじ登るには子供にとっても危なっかしい。
当然、大人になったら「スリル」だけのためにやる遊びではなくなってしまった。
あたくしの自宅からすぐ西に行ったところには梨畑もある。
畑のど真ん中にある某工業高校の生徒たちは、
ココの畑で盗みを働くことで喉を潤していたと、
当時付き合っていた、その某工業高校のオトコに教わった。
都会ではなかなか味わえないスリリングでかわいらしい遊びだと思う。
**************************************************************
実るほど頭を垂れる稲穂かな
これは、有名な句です。
作者は何でか不明です(笑)。<色々調べたんですけどね
ことわざ的な要素をもっているようですね。
びっくりするのは、朝鮮にも同じような諺が存在するということ。
己が満ち満ちていけばいくほど、傲慢になるのではなく
頭を下げることができるような稲穂のような人間におなりなさい、
と小学校の頃に洗脳されたことを覚えております。
・・・・失礼(爆)。洗脳ではなく躾ですね。
同じようなことばで
草うつむいて百を知る
なんてのもあります。
頭を下げることによって、色々な事を知るのだという・・・・
まぁ、慣用句的な諺ですな。
今回は、そんなところからお題を拝借いたして
現代流にアレンジしてみたわけです。
事実、道に飛び出して頭を垂れていた稲穂たち、
彼らのこうべの数ミリ下には、土の香りのする畦道ではなく
アスファルトがあったわけで。
それでも頭を垂れ続ける稲穂は、
一体何を知ったのだろうか。
アスファルトも、空気の色や季節の変わり目を
稲穂たちにきちんと教えていてくれるのだろうか。
人間は色んな情報網を駆使し、
天気予報を入手して季節を知るようになってしまった。
ツバメが低く飛ぶこと、雲の形、太陽に輪がかかる・・・・
昔は、原始的でも美しく神秘的で、そして自然をこよなく尊敬したカタチで以って
人間は稲穂のように空気と時の流れを感じていたのだ。
実に健気だ。
そして、今日も頭を垂れ続ける稲穂たち。
|