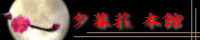山の動く日来る。
かく云えども人われを信ぜじ。
山は姑く眠りしのみ。
その昔に於て
山は皆火に燃えて動きしものを。
されど、そは信ぜずともよし。
人よ、ああ、唯これを信ぜよ。
すべて眠りし女今ぞ目覚めて動くなる。
これは、「そぞろごと」と題され、与謝野晶子という有名なオンナが、
平塚らいてうというまだうら若きオンナに依頼され(唆され)、
「青鞜」という同人誌の創刊を飾った巻頭言である。
因みに「青鞜」というのは、「青い靴下を履く女」・・・・つまるところ、
「変わったことをする女たち」という意味で、
まだ憲法で「表現の自由」というのが確立されていなかった頃に
官の目を気にしながら、モノを書いていた人々の希望の星とも言えた。
この頃、与謝野晶子が書くものといえば、何でも金になった。
このオンナ、元は妻子あるオトコにいれあげ、
挙句、横取りしてしまった強烈なオンナである。
おまけに子供を8人だか9人だか産んで、
自分の書く著作の原稿料で食わせていた、とんでもない経歴の持ち主である。
更に、その横恋慕したダンナをフランスに留学させるために
「百首屏風」(小倉百人一首を1首ずつ色紙に書き、屏風にしたものだったと思う)
という反則ワザまでやってのけ、
自分は育児と執筆しかしなかったのである(爆)。
現代、このようなオンナはもういない。
そこまで相手にいれあげるような「燃えるような恋」をしたとしても
オトコが退いてしまえば途端「ストーカー」扱いされてしまうし、
果たして、そこまでいれあげることができるような才知に長けたオトコが
そういるかというと、それも怪しいものである。
少子化の影響で、年々、オンナは子供を産まなくなってきているし、
何せ、育児には金がかかる。
そして、「書けば何でも売れるオンナ」というのは
妙な知恵がついてしまって、子供を産むということそのものに
興味を示さなくなってしまっているのが現状だ。
さて。
この強烈なオンナにいれあげられたオトコ。
それが、与謝野鉄幹である。
彼こそ、同人の先駆者とも言うべき、歌人(詩人)であった。
その昔は、鮮烈な歌を創り上げ、言えば誰もがその名を知る門下生も沢山いた。
が、彼はそのパワーの全てを、妻の晶子に吸い取られてしまった、
可哀想なオトコなのである。
かつての栄光も、妻の蔵書の前ではくすんでしまう。
古本屋ですら、晶子の蔵書であれば彼の著作の数倍の値をつけるとまで言うのである。
嗚呼。可哀想な鉄幹。
それでも、フランスの新しくて鮮烈な詩を読みたくて
彼は自分の妻の蔵書を古本屋に売りつけ、仏和辞典を手に入れようとする。
新しい風を、新しい文学を、
自分も身をもって感じたい・・・・そんな文学者の健気で真っ直ぐな欲求は
主が「男」でなければならなかった時代の中で
儚く、苦しい、「カタチ」となって襲い掛かるのである。
要するに、「金」が要るのである。
そんな鉄幹のキモチが、痛いほどわかる今日この頃・・・・。
お金がなければ、本が買えない。
至極、当たり前の事のように思えるが、
IT、ITと叫ばれる昨今、情報はPCをつなげば湯水のように溢れてくる。
しかし、その情報が本当に確かなものかどうか
その保証はない、というのも、1つの現実である。
自分の目で、その情報が確かか否かを見極めるためには
もっと沢山の情報と知識が要る。
その為に、沢山の人の目を掻い潜って、ようやく活字化されて出版にこぎついて
店頭で販売される「著書」というのは、やっぱり必要なのである。
あの面白そうな短歌の入門書が欲しい・・・・
という私の気持ちと
フランスの新しい詩の世界に触れたい・・・・
という鉄幹の気持ちは相通ずると信じたい。
そんな本日、ダーリンが図書券を携えて、私の許を訪れた。
まるで、晶子が鉄幹(の才能)のために、身を削ったかのような現実の再現。
私には、モノを書くためにまだまだ沢山の資料が必要なのだ。
晶子は鉄幹の熱い才知に惚れこんで、書きたくもない「青鞜」の巻頭言を書いた。
ダーリンは、私が「モノを書く」という行為に対して、
惚れこんでくれているのだろうか。
私が「演じる」という行為の為に、沢山の欲求を満たしにかかることに対して、
惚れこんでくれているのだろうか。
鉄幹が晶子の力によって、最後まで「男の歌」を詠んだこと、
そして、私がダーリンの力によって、ある一定の処にまで登りつめようと努力すること、
一見、違うように思えるが、
根底は同じような気がする。
「申し訳ないなぁ・・・・・。」
そう思いながら、本日、私が本屋で抱えた著書は、
先日、この日記にも書いた短歌の入門書ともう1冊、
「知られざる刑務所(ムショ)のオキテ」
これが、一体、今後の私の作品に
どのように反映されるのかという疑問をお持ちの方もいらっしゃるだろう。
私が今までに手に入れた蔵書には、凡そがノンジャンルである。
一、戦場で実際に使用されている、兵器や銃の解説図解(写真入り)、
一、薬物の作用と副作用についての解説書、
一、虐待がもたらす家庭崩壊の実例ばかりを集めたルポ、
一、当時6歳の子供が書いたという、ミリオンセラーを記録した童話、
一、姓名判断や、誕生花の辞典、
一、幸徳秋水の伝記、
一、邦画が花盛りだった頃の有名女優を特集したグラフ誌、
等々、言い出したらキリがない。
どれとどれがどう結びつくのか、それはその時次第である。
そして、これも言っておこう。
私は決して読書量が多いほうではない。
小説など、ほとんど読まないし、
話題になっているモノにすぐに飛びついては読み漁る・・・・という性分でもない。
ただ、自分が、「コレだ!!」と思った情報源に関しては
不気味なほどに執着する帰来があるかもしれない。
そう。出版物には、インターネットで流出される情報とは
比べ物にならないくらいの魅力がある。
昨今、出版業界が危うくなっている中、
幻冬舎だけは、なぜか元気だ。
装丁も凝っているし、美しい。
著作もなかなかのお歴々である。
面白い本を手に入れるのは難しいが、
面白い本を作るのはもっと難しく、そして冒険が必要になってくる。
この魅力にとり憑かれた者が、今の出版業界をようやく支えているのかもしれない。
面白い芝居を作るのには
まず面白い本と、面白い素材・・・つまりは役者が必要になってくる。
更に言うなら、こちらも冒険が不可欠なのである。
両方の世界に足を突っ込んでしまった私は
もがけばもがくほど、泥沼に填まっている、最悪の状況に居るのかもしれないが
幸い、食べるのだけには困らないでいるし、
雨露を凌ぐ家もある。幸せなことだ。
道楽にかまけているように人は見るかもしれない。
だけど、その道楽を極めんとする人間がいてもいいと私は思いたい。
即ち、
芸術とは斯くあるもの。
鉄幹の時代も、私たちが生きている時代も
その点だけは変わらないようだ。
都合の良い事ばかりを言っているように聞こえるかもしれないが、
私はやっぱりそう信じたいのである。
|