更新履歴 キキ
[home]
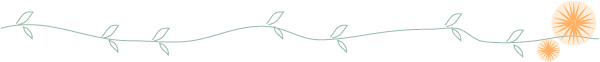
2009年02月20日(金)
■波照の舞う展 http://www.misuzudo-b.com/gallery_2009_1.html 言葉の展示にはあまり興味がない。言葉の最上の表現方法は、言葉そのものでしかありえないと思うからだ。が、いただいたDMの陶器の佇まいのよさに惹かれて、いそいそと出かけた。前年ポエケットで今回の展示の一部を手にしたときの消化不良がなんとなく心に残っていたこともある。 風の強い昼下がり。湯島聖堂のすぐ傍にある美篶堂は文房具屋とギャラリーなどが併設されている、何だか不思議な場所である。小ぢんまりしているが、美しさというか、気持ちよさ、の詰まった空間だった。 構成は以下。 詩:白井明大、陶器:須藤拓也、活版印刷:高岡昌生(嘉瑞工房) 白井さんの沖縄の詩を活版印刷し、展示。 詩からイメージ得た陶器の展示。 筆で書かれた詩も川の流れをイメージさせるような形で展示。 活版も展示(これは興味深い) 沖縄民謡が流れている ※このような構成のインスタレーション型の展示であった。 ポエケットで活版印刷された詩を手にしたとき、印刷の見事さにはうなったものの、人ごみの中でパラパラ流し見しても、うまく受け取れるはずもなく、そのように伝えてすぐにお返しした。展示なら、とそのようなことも言った記憶があり、なんとなく責任を感じて出かけたのだった。 思った以上に、展示としての形が素晴らしく、とても贅沢で上質な空間に仕上がっていた。ひとつのイメージがきちんと空間に満ちている。この空間で、この詩はいい。ゆったりとした空間では心に入ってくるだろう。だが、都会の雑多な空間や電車の中のちょっとの隙間などにはうまく嵌らないだろうとも思う。良し悪しなどとはまったく別の次元で、詩とはそういうものだし、それが詩のよさでもあるとも思っている。 詩を書く人間としてどうしても考えてしまうのは、陶を手にしたときのその重さだ。形、そして重さがあるということの、その確実な手ごたえに対して、言葉というのはすごく儚く頼りないもののように思える。わが身を振り返り、急に茫漠とした気持ちになったのも確かだ。さらに逆説的に、だからこそ、希望もある。 それにしても。須藤さんの器でお茶をいただいたのだが、くちびるをつけたときの感触、これは正直心を持っていかれた。 * 感情的になることではなく、感覚的になることは、結構難しい。ずっと覚えていたいけれど、たいてい感情よりうんと早く忘れてしまう。きっと身体のどこかに蓄積されているはず、と思いたいけれど。 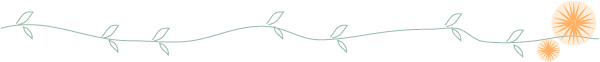
|