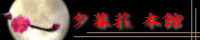| 2002年08月03日(土)
|
リスペクトみそひともじ Oh Yeah♪ |
あははははははは♪
ちなみに、詠んだ歌のテーマは暗いけど、本日のあたくしは超元気だから、心配御無用♪ 本日も、あたくし流健康食をがっつり食って、快眠快便よ♪
そうよ、そうなのよ!
元々、こういうサイト(日記)だったのよ、うちは(爆)。
文芸人として文芸を嗜み、<50%
嗜好の古今を問わず、常に新しきものを追求し、<30%
たまに弱音を吐いて、<10%
テレビの番組批評なんかもやってみたりもして、<5%
遂には他人様まで扱き下ろし( ̄∇ ̄;)、<3%
そいで、本当に書けない時は、敗北宣言か業務連絡(爆)<2%
このくらいの割合での運営が望ましいと、思っていたのに実現せず( ̄∇ ̄;)
放置しておいたら、
弱音70%、番組批評20%、文芸らしいこと10%くらいになってしまっていた。
いけません。
巻頭歌は別に、「今、自傷行為に走りたい♪」とかそう思って作った歌じゃなくて、前に発作を起こした時に、本当にボーッとしていた感じを、何とか思い出して作った歌です。ついでに言ってしまえばインスタントです。だから、数時間後には、この歌のことなんか忘れてしまいます( ̄∇ ̄;)
そういう作品のことを「駄作」というのだそうです。
じゃあ、どういうのが「傑作」かというと、とあるプロ歌人にいわせると、
作った本人も、そしてその歌を見た人も
後々まで、暗誦できるような歌
なんだそうです。
丁寧に言葉を選んで推敲するというのも、やっぱり歌作りには必要みたいで、それでご飯を食べていこうとするには、役者より大変そうなので、あたくしは、そういう七面倒臭い作業は真っ平御免です。いっつもインスピレーションだけに頼っているので、詠めない時は、半年も1年も詠めないままです。それでいいと思っています。
上の御意見なんかはね、歌集1冊丸々傑作なんてありえないような定義だぜ?
現代短歌の歌壇にいらっしゃる、大先生方も、自作のそんな歌集はきっと1冊も持ってらっしゃらないでしょう。皮肉じゃなくて、本当に。
ぷよ2が前に、あたくしの作った歌で、誉めてくれたのがありました。多分、言った本人も忘れているだろうと思うけれど、「瞬間的傑作」になった歌もあるにはあります。
とりあえずご紹介。
初夏の桜を詠ったものです。昨年の4月の末、もう散り終わってしまい、葉桜になった近所の大樹が、ざわわざわわと風に靡いていたので、思わず文芸人としての血が騒いで、30秒くらいで作った歌ですが、今見ても、何となく「いいな♪」と自画自賛してしまえる作品なので。
でも、推敲の余地はあたくし本人が見ても沢山あると思うので、結局「傑作」ではないのだけど。わかりやすく絵画に喩えて言うなら、デッサンだけはすっげー巧くいった・・・・色も空気も、質感やそのときの感情も、これが残っていればかなりいい絵になるぞ♪という自信。写真でその風景を撮ってきた以上の五感の記憶・・・・かな。
この元歌を見るたびに、あの「ざわわざわわ」が聞こえてきて、それまでは誰もが足を止めて見上げられていた立派な桜が、あれよあれよという間に素通りされてしまう可哀想な春の終わりがきちんと思い出せます。
「2000年の夏」でご紹介した夏の花の歌もついでにご紹介しましょう。
推敲してありますが、「傑作」になるかどうか(笑)。
カッコつけて、桜にせよ朝顔にせよ、花の名前を出さないところがキザなんですよね・・・・。自分でもわかっているんですけど、こういう比喩表現をどうしても使いたい時ってあるんです。
有名な句がありますよね。千代女の。
朝顔やつるべとられてもらい水
なんか、こういう芭蕉っぽい直球的な句が苦手な時期もあってですね。無論、千代女にせよ、芭蕉にせよ、いい句をいっぱい詠んでいるんですけど、あちらは俳句。こっちは短歌(・・・・っていうか、みそひともじ?)。14音余分に音が使えるのであれば、字余り覚悟でそれに挑戦♪っていう方があたくしは好きでして。
それに、俳句にはもっと難しいルール「季語」というのがあって、「歳時記」という分厚い俳句用の辞典があるくらいなんです。それに則って、春の句とか秋の句とか決められちゃいます。だから、四季の季語がごちゃ混ぜになって入っている俳句は論外で、そういうのは川柳にいってやってくれぃ・・・・なんていう俳壇もございます。
その点、短歌は素敵です。
古今を問わず、季語など一切無用です。
無論、季節を美しく詠み込んだ歌というのも数多くありますが、それ以外にも、老いや病に対する不安や、離れてしまった友や地への寂寞感、何より多いのが恋心を切実に美しく詠いあげることが出来るのが、俳句にはない、残りの「7・7」のおかげなのです。
遡れば、奈良時代にはもうこういった形態の歌があった模様で、平安時代に栄えに栄え、今も尚、ちゃんとした歌壇があるくらい。おまけにあたくしを代表とするエセ歌人というか、もう「みそひともじ」あれば句切れがどこだっていいじゃん!みたいな逆ギレ系も出現する有様( ̄∇ ̄;) 江戸時代には川柳に並んで、狂歌なんて呼ばれた「現代流短歌」もございます。それを一纏めにして「今様」という言葉が存在します。これは「現代風」「今風」という意味で、まぁ、平成のこのご時世、7・5句の四部構成ばかりが「今様」と呼ぶには相応しくないかもしれません。大概の場合、7・5句の四部構成の歌を「今様」と言います。
まぁ調べてみると、平安時代の狂歌・・・・つまり5・7・5・7・7系の遊び歌も「今様」と呼ばれていたみたいなので、とにかく、その時代に即した歌は全部「今様」と呼んでもいいってわけですな。
最近、「一行詩」とか「五行詩」とかいうのも流行ってるみたいですね。
ネットでもよく見かけます。
あれも、いわゆる「今様」なのかもしれません。
あたくしは、平安時代から後に栄えた「今様」をリスペクトしているので、自分で詠む時は、基本的に7・5句の四部構成(字余り、字足らずは許容範囲)でやるようにしています。何でそんなに拘るかというと、我が故郷、ここ大垣がその形態の発祥の地だと謂われているからです。
さて。
こうやって、講釈させておくといつまでも終わらないあたくしですので、
今様でも一首ひねって、とりあえず、本日のところは文芸人らしく終わりたいと思います。

久々に詠んだか・・・・恋の歌(爆)。2・4・8の踏韻で自己満足、Oh Yeah♪
半年以上もほったらかしで、投稿者は怒り心頭ではなかろうか( ̄∇ ̄;)
以後気をつけます・・・・が、鑑賞・披講できないときは出来ないんです( ̄^ ̄)
(最終的逆ギレモード)
|