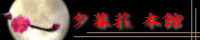| 2005年09月29日(木)
|
あの9月28日へ(3) |
あの日以来、あたくしとシンは律儀すぎるほど、正直すぎるほどに「今までどおり」だった。
ただ、これまでと少し違うのは、彼を目で追ったり、ちょっとしたことで顔をあわせた時に
彼に対して笑いかけても、誰も咎めなくなったという環境の変化の方だった。
生来、ベタベタするようなつきあいは、男性に限らず女性に対しても好きではなかったので、
あくまでも自分のスタンスでいけたら・・・・そんなふうに柔らかな秋の中、あたくしは幸せを感じながら
過ごしていた。
一方。生徒会のほうは、これはきっと詐欺にでも遭ったに違いない(笑)目の回るような忙しさで、
本来、後期にはない渉外みたいなものもたまにあったりした。
前任の教育長が亡くなられたことで、市レベルの段階の抜本的な校則改正の動きが通達され、
あたくしたちは連日連夜、それこそ大忙しだった。
議会や生徒総会の回数が例年の何倍にも増え、その下準備に毎日のように追われ、
そうでなくても夏をピークに成績は下がり始めていたのに、ますます勉強が出来なくなる一方だった。
(時間が取れない、集中できない等々)
後期に生徒会が動く大きな行事といえば、文化祭くらいだったので、そのくらいなら・・・・と
安請け合いしたのが、そもそも甘かったのかもしれない。
そんな折、まず1回目のヨシオとのおかしなニアミスがあった。
生徒総会を開くにあたっての議事進行の確認をしながら、実際にどのようにオペレートしていくべきかの
全体的な話し合いを執行部会で行っていた時のことである。
顧問に、職員室からOHP用の生シートと下書き用原稿を取ってくるように言い付かり、
あたくしは1人で部屋を出た。
いくら量が多いかもしれない・・・・といっても1度にそんなに使用するわけがなく、
そして、職員室常連のあたくしが白紙の原稿を探し出すのにそんなに時間がかかるものでもなく、
加えて、見つけ出した所用のブツは片手で十分に持っていけるくらいに、軽く、嵩もなかった。
なのに、追いかけるようにして、職員室までヨシオがやってきたのである。
「手伝うよ。」
「手伝うって・・・・(笑) 持ってくの、コレだけだよ?」
あたくしは所用の分を見せて、さっさと職員室を出た。
「なぁ・・・・。」
「なに?」
「お前さぁ、誰かに告白したろ?」
「・・・・!! だ、だから?」
「相手、誰だよ?」
「教えない〜♪」
あれは確かに、2人だけの秘密の出来事。
親友にならともかく、昨日今日ちょくちょく話すようになったこの彼に、容易く言うべきことではない。
「教えてよ〜。」
「やだね〜♪」
と、何回も繰り返しながら、もう校内を走り回る必要のなくなったあたくしは静かに歩いた。
こういうふざけあいも悪くないかな・・・・内心ではそんなことを感じながら。
シンに告白する前までは、それこそ、男の子とこういう話はできなかった。
多分、あたくしの恋心を知っていた少年はトモくんくらいかも。
そのトモくんとさえ、学校の廊下で軽々しくこんな話はしなかった。
サラリサラリと、彼の言葉をかわして、元の部屋の前まで来た時、扉に手をかけたあたくしを
少し荒っぽくヨシオが制した。ドアに手をかけて開かなくしたのである。
「ねぇ・・・・誰?」
「・・・・・・・・。」
「教えてよ。」
「・・・・・・・・。バカなことやってないで、早く開けて。」
「教えてくれたら、開けたげる。」
シンですらまだ入ってきたことのない間合いに、ヨシオはズカズカと入り込んできた。
あたくしの手から、所用の原稿を奪い取って尚、彼は頑として扉を開けることを許してくれない。
そして、顔が物凄く近づいた。
生徒はほとんど帰ってしまった後だったけれど、先生はまだ沢山残っている。
そして、ここが「学校の中」である限り、あたくしの理性もまだ沢山残っているのだった。
彼から奪われた原稿を奪い返し、彼の顔を睨みつけて、これ見よがしに部屋の扉をノックした。
「失礼します。取ってきました。」
本来、ノックの必要などない。
「会議中」と書かれた札が外に出ているので、関係者以外は絶対にここには来ない。
あたくしがあまりに平然とこういうことをするものだから、ヨシオは反射的にドアから手を離した。
・・・・この時はまだ、あたくしの方が彼よりも一枚も二枚も上手だったのだ。
「かわす術」を知っていたという段階なら、それこそ義務教育の間にみっちりと培っておいたから。
必要でなかったノックと、ドアを開けた時に恐らくあたくしの後ろで少し慌てふためいていたはずの
ヨシオを見て、同士・カズコだけは何が起きようとしていたのか把握してしまったらしい。
あとあと、ケラケラと笑っていたし(笑)。
(あたくしにとっては、この時はまだ、決して笑い事で済まされることじゃなかったけれど)
文化祭の準備と並行して、校則改正の原案を議会に掛け、総会の準備もせねばならず、
そして自分のクラスでも毎日のように(文化祭用芝居の)稽古があったから、
明るいうちに帰れたためしがない(苦笑)。・・・・受験生だというのにさぁ(爆)。
でも、丁度この頃が、一番楽しかった。
自分の出ていないシーンの小返しとなると廊下に出て、
小さく蹲りながらひとりで長い長いせりふを入れることに没頭する。
そこへシンがたまさか通りかかったりすると、ちゃんと声をかけていってくれる。
「どう? 調子は(笑)」
「う〜ん・・・・例年に比べると今ひとつ(苦笑)」
「昨年のがあるからなぁ・・・・みんな期待しちゃってるよ。主演でしょ?」
「誰から聞いた!? ・・・・あ、そか。『弟』か(爆)」
うちのクラスには、彼の双子の弟がいるのであった。
「いや。キミのクラスの女の子たちから聞いたよ。」
・・・・お節介だなぁ。
「難しい顔してるなぁ(笑)。」
「今までの中で一番難しいかも(苦笑)。
主演じゃないだけ、昨年の方が良かったよぉ・・・・。」
「頑張れよ♪ 照明プランくらいは覗かせてもらうかも〜♪」
彼も、彼の弟も、クラスの照明係を担当していたのだった。・・・・双子の神秘性??(笑)
「今までどおり」の範疇に、こういうのも入るんだなぁ♪ と単純に嬉しかったりして。
一方通行だった矢印から、きちんとしたリアクションがくるようになって、
それが毎日じゃなくても、今までの数倍、自分の生活が華やいだ気分になった。
どんなに忙しくても、あの9月28日から晩秋にかけての約2ヶ月間は、
あたくしがあの厳しい中学の中で、心底「楽しい!」と思える、そんなスパンだった。
隣のクラスではヨシオが主演を、そしてシンのクラスではリエが準主演を務めたこの文化祭。
うちのクラスの結果は惨憺たるものだったが、自分の波長が上向き志向だったので、
今でも「あの時に出会った本は、いい戯曲ばっかりだなぁ」なんてふうに思う。
さて、いざ祭も終わると、執行部の仕事のほうに本腰を入れなければならなくなった。
シンと偶然を装ってほんの少しのおしゃべりをすることも徐々に減っていった。
その代わり、執行部の連中とばかり一緒にいることが多くなった。
最終的には、執行部会や議会のない放課後や、土曜の午後も、誰かの家に集まって勉強会と称し、
一緒にいるのが普通になってしまった。
この頃にもなると、もうさすがに隠し立てもできなくなって、あたくしの恋の相手が誰であるのかは
ヨシオにも知られるところとなっていた。
それなのに、その事実が明らかになって尚、彼の行動はどんどんエスカレートしていった。
学校の外にいて、この4人(執行部のうち2人が2年)が一緒にいる時は、
いつも彼があたくしの隣を歩き、臆面もなくあたくしの手をとったりすることもあった。
あたくしも振り払えばよかったのかもしれないが、4人の均衡があまりに心地好かったものだから、
どんどん彼のペースにはまっていった。
4人で宿題をやっている時に、先に疲れた彼にあたくしの膝を占領されてしまったこともあった。
無碍に起こすのもアレだと思ったので、あたくしはこの時も1人静かに、本を読んだり、
その姿勢をなるべく崩さないまま、課題をこなしたりしていた。
ある日。2度目のニアミスが起きた。
ヨシオの家に4人で集まって勉強していた時のこと。
同士・カズコが先に帰ると言い出し、会長であるもう1人の少年が彼女を送るといって、
事実上、彼のプライベートルームに2人きりにされてしまったのである。
自分も一緒に帰るわ、と、立ち上がったのだけど、カズコの意味深な笑みで以ってそれは制され、
あたくしは、彼の部屋に残らざるを得なくなった。
・・・・疎さを装い続けたさすがのあたくしも、もう何が起きてもおかしくない状況なんだ、そう悟った。
カズコたちがすっかりこのあたりにいなくなったのを見計らって、あたくしも帰ろう。
こんな状況になれば、きっとヨシオだっていくらか気まずいだろうと思うし。
「帰るね。」と言ったあたくしを止めたのは、ヨシオの方だった。
「もう少し・・・・。」そう言って、立ち上がったあたくしの手を引き、座らせた。
彼は横になり、座り込んだあたくしの膝に自分の頭を預け、そしてその後しばらく何も喋らなかった。
気付きたくないことを気付かなければならない瞬間が、すぐそこにやってきている気がした。
この沈黙の間、あたくしの方も何もできずにただ呆然としていた。
・・・・どうして止めたの? 理由を突き詰めれば答えはすぐそこにありそうでもあり。
・・・・じゃあ自分は、どうして逃げずにここにいる? その答えも同じようなところで不安定に揺れていた。
近くにいすぎたことを今更悔いても遅いのであった。もう、きっとなるようにしかならない。
案の定、というか何というか、彼はあたくしの膝にいながらあたくしの首に手を回し、抱き寄せようとした。
寸でのところであたくしにブレーキがかかり、とても微妙な距離を保ったまま、
あたくしたちはその姿勢のまましばらく止まっていた。
・・・・目を閉じてはいけない! 瞬間的にそんなことを思った。
彼に引導を渡してしまったら、その瞬間、全ての均衡が破綻する。・・・・そんなことを考えていた。
少しずつ伸ばし始めた髪が、あたくしと彼の間の距離を丁度覆い隠すようにして、小さな影を作る。
次に彼が何をするのか、それを彼に任せてしまってはいけない。
あたくしは瞬きも最小限で、この少年のことをじっと見つめていた。
・・・・・・・・!!
ついこの間、経験したばかりの息の詰まりそうな感覚がした。
次の瞬間、あたくしと彼は並んで横たわっている状態になり、彼の顔もすぐ近くに見えた。
ダメだ・・・・もうこれ以上、自分の間合いに彼を入れるわけにはいかない。
あたくしはすぐに急いで起き上がった。その手を引かれそうになったが、
「・・・・嫌。」
と、小さく意志表明をした。もうこれ以上彼のペースに押し流される自分のことも嫌。
きちんと「嫌」と言い切れない自分のことさえも嫌。
一瞬でもヨシオの言いなりになりそうだった自分が・・・・嫌だった。
「・・・・帰るね。もう、暗い。」
「送るよ。」
今度こそ本当に立ち上がり、そして外に出た。
学区の一番東の端っこにある彼の家。そしてあたくしの家は、学区の一番西の方。
さっきまでのことをお互い忘れようとするかのように、自転車を走らせた。
色々と別の話をした気もする。けれど、この道程のおおよそのことは忘れてしまった。
ただ、シンよりも先に、物凄いスピードで自分の間合いに入り込もうとするこの少年のことが
とても不思議な存在になっていった。
実際のところ、本当に求めていたのは何だったのか・・・・というのも、今となってはもうわからない。
あの頃のあたくしも、少々鈍感すぎた。自分の気持ちだけで手一杯。
彼と一緒にいる時間の長さそのものが、どれだけシンを傷つけるかなど、考えも及ばなかった。
ベールに包まれるような温かさと、ナイフのように残虐な鋭さを両天秤にかけて、
あたくしは「ナイフ」を選んでしまった。強いものへの憧憬の権化だった。
そのナイフが、ベールを引き裂き、やがては自分をも傷つけることになるとは、この時は考えもしないで。
(4へつづく)
|