夜明け前からにわか雨が降っていたようだ。
音もせずあまりにも静かな雨だったので全く気がつかず
杖を付きながらやっとの思いで洗濯物を玄関まで運んだ。
庭の物干し台まで運ぶのはいつも夫が手を貸してくれるので
声を掛けたら茶の間からすぐに出て来てくれる。
そうして外に出るなり「見てみろ!」と叫ぶのだった。
まるで霧のような雨が降っていた。
「だから今日は干すなと言ったじゃないか」
決して怒っている訳ではないのだがしゅんとせずにはいられない。
夫は直ぐに重い洗濯籠を提げて乾燥機まで運んでくれたのだ。
そんな何でもないようなことが嬉しくてならなかった朝のことである。
幸せってきっとささやかなことなのだ。ただ気づかずにいることが多い。
私がもし「当たり前のこと」だと思ったら幸せは消えてしまっただろう。
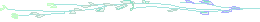
今日は職場に昔好きだった人が来てくれた。
年甲斐もなく胸がドキドキして照れくさくてならない。
私より2歳年上なので今年70歳になるのだけれど
とてもそんな歳には見えない。すらりと伸びた長い脚は昔のままだ。
私はと云えば杖を付いた白髪のお婆さんである。
穴があれば入りたいくらいだったが生憎穴が見当たらなかった。
なんと恥さらしなこと。これでは千年の恋も台無しである。
長い髪をなびかせながら見つめ合った日のことを思い出す。
片思いではあったが彼は確かに私の気持ちを知っていたのだと思う。
既に付き合っている彼女が居たのだ。私はおじゃま虫であった。
どれほど涙を流したことだろう。叶わない恋ほど切ないものはない。
記憶は遠ければ遠いほど鮮やかに光り続ける。
こんな私でも若さで輝いていた頃があったのだ。
長靴を履いた彼は軽トラックに乗って颯爽と去って行った。
|