 |
 |
■■■
■■
■ perfume<parfums>.com
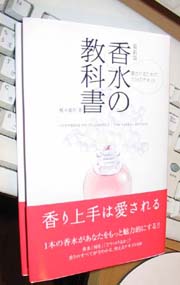
先日 学研から本が届いた。
このあたりは、出版日から1週間以上経たないと
本屋さんに並ばない、注文しても 1週間は待たされる
文化僻地(おこらないで!)なので、本はよく出版社に
注文するのだが、学研には 心当たりがない。
K宛なので、なんだろう と開けてみると、上の写真の本。
やったね!ついに 雄作ちゃんが 出版したんだ
何十年かまえに 文芸春秋のコラムに執筆しているのを
見つけて以来、いつかは と思っていた。
雄作ちゃん 道をきわめたね。すごいことだね。
ここで、雄作ちゃんについて 少し。
彼とは 和歌山の中学の同級生。クラスは同じじゃなかった。
Kの親友の親友として 知り合った。
おもしろくて、頭がよくて、生徒会長をやってて、
お習字がうまくて、絵がうまくて、仏語を発音させると
rでうがい状態になって、咳き込む。<今でもそうですか?>
大学時代は 歌っていた。
とにかく 昔から個性的というか、マニアックというか、
感覚人間というか、ひと味もふた味も 人と違っていた。
さて、肝心の本について。
まず ”香水の教科書”等と みもふたもないタイトルに
した訳 をよんで なるほど、だけど 副題の”愛される
ための109のテキスト”のほうが かたくなくていいな、
などと 余分なことを考えながら、目次を見る。
ここで、独特のすてきな表現語(?)に気づく。
「香り上手」「香りの立ち方」など。
一番先に読んだのが 「コンサートを数倍楽しむために」
なぜか というと、コンサート(クラシックであれ
ロックであれ)を聴きに行ったときに、近くの人が
香水の香りをさせているのが、とても気になったことが
あったから。香りとコンサート自体が 結びつく(変な
表現だが)ような 気がして。
同じ事が レストランでもあった。
食べ物の香りを楽しみたいのに、香水の香りに邪魔される、
みたいな。
コンサート・・の項で、彼は 聞く音楽や見る映像にあった、
又は その感動を高める香りを 自分で選びなさい
といっている。近くの人から 漂ってくる香りが
自分の好みじゃない、とか この香りをながくかいでると
頭痛がしてくる などと いってないで。
香水が好きな方、ぜひこの本を読んで、自分で楽しんで
下さい、人にかがせるのでなく。
あたりに 遠慮会釈無く香りをふりまく人は、これみよがしに
装飾品をジャラジャラつけているのと 変わらないと
私は思うのだが。
「過ぎたるは 及ばざるがごとし」
自分が好きな香りを きらいな人もいるのだ、ということを
いつも 頭においてほしい。
雄作ちゃん、私の香水の知識 香りに対する感覚なんて
そんなもの なんですよ。
これからも 小学生用、中学生用、高校生用、といろんな
教科書を書いて 啓蒙して下さい。
この前 会った時に 「シャネルのNO.19が好き」
といったら、小さな声で「若向きだ・・」と のたまったよね。
「なにぃ?」「いや、なんでもない」
「私は柑橘系がすきなんだ」と きいたふうな口をきいたら、
次にあったときに「これ」って、Jean CouturierのMarjolaine
を 持ってきてくれた。
専門家が選んでくれたものだから、ありがたく
楽しませてもらっている。
日本では 同じ物が 見つけられなかったので、
マカオで香水専門店に飛び込んで化粧箱をみせたら、
ありましたね これが。
(なんで化粧箱を持っていったか、というと なにをかくそう
読めないんですよ。ジャン クチュリエの マジョレヌ?)
お徳用みたいな でっかいのもあったが、なんか
ありがたみがないような気がして、品良く「小さいほうを」
と1.7ozのを買った。教科書によると、愛用する香水は
でっかい方を買いなさい、とのこと。
その方が安いし(と、ここでいきなり 鍋釜感覚)
持ち歩き用の容器に移し替えられる、とのこと。
なるほど。小さいスプレーつきの香水瓶は
持ち歩きにかさばる。
確かに 私も 旅行の時は ちゃちなスプレー容器に
移し替えて持って歩いている。
ざっと 読んだだけなので、内容を詳しく書けないが、
(あんまり引用してしまうと、著作権にひっかかるかも)
「香水なんて 外国人が体臭をごまかすために 発明
したものさ」などと うそぶく前に、ぜひこの本を
一読することを おすすめしますよ、みなさん。
http://www.e-parfums.com/ が
香りのスペシャリスト 榎本雄作 のHPです。
なお 本は オンラインでも購入できるそうです。
2004年04月18日(日)
|
|
 |