| 2005年08月02日(火) |
三村一族と備中兵乱7 |
五、船岡山
三村宗親は足利義稙に供奉して上洛したとき、船岡山の戦い(1511)で華々しい活躍をして、荘 元資、石川久次らと共に備中武者の名を高めた。船岡山の合戦は堀越公方足利政知の子義澄を擁立する細川澄元、細川政賢らの軍勢と足利義稙を推戴する細川高国、大内義興ら西国諸将の連合軍が京都北郊船岡山で激突し義稙軍が勝った戦である。この戦では尼子経久、大内義興が先陣を争ったが細川高国の斡旋で先陣大内、二陣尼子と決定し大内義興は先陣の名に相応しい働きをして面目を施した。即ち義興は船岡山の合戦の殊勲者として永正九年(1512)従三位に叙せられて田舎武士としては破格ともいえる公卿の座に列することができた。
一方大内の後塵を浴びることとなった尼子経久はこれを不服として戦に参加せずさっさっと兵を纏めて領国の出雲へ帰国してしまった。中国制覇の準備を始めるためである。
この戦には毛利元就の兄毛利興元も参戦しているが目だった働きはしていない。それにひきかえ三村宗親の働きは目覚ましいものがあり、義稙の近侍上野民部大輔信孝の目にとまるところとなった。
将軍に復帰し船岡山の合戦で細川政賢・澄元軍に大勝した義稙は幕府の威権を示すために永正九年三月(1511)全国の国主を集め年来の軍忠を讃え行賞を行った。このとき備中国に対しては近侍の二階堂大蔵小輔政行、上野民部大輔信孝、伊勢左京亮貞信を派遣することにし、備中の国侍達を懐柔し味方につけることが使命として与えられた。
将軍近侍の使者達が用いた懐柔策は官位を斡旋することと戦乱の都を嫌って西国へ都落しようとする公家達の子女との縁組みを仲介することであった。官位や身分の高い公家の子女と縁組みできるという餌は田舎の国侍達には魅力的であった。備中の国人達は競って彼等に誼を通じようとした。
上野民部大輔信孝は下道郡下原郷の鬼邑山(現岡山県総社市下原)に、伊勢左京亮貞信は小田郡江原村の高越山(現井原市西江原)に、二階堂大蔵少輔政行は浅口郡片島(現倉敷市、片島)の城に入り近隣の国人を従え領国に善政を敷いた。
上野民部大輔信孝はかねて宗親に注目し好意を抱いていたので備中鬼邑山へ入ると自分の妹「須磨」を都から呼び寄せて宗親の正室として娶らせるよう工作した。律儀者の宗親に異存のある筈もなく、家格が上がると喜んだ。
丁度この頃備中では北には出雲の尼子氏が西方には周防の大内氏が、東には播磨の赤松氏、南からは四国の細川氏と三好氏がそれぞれに勢力を蓄え領土を狙っていたので、備中の国人達は或いは尼子の旗下に加わり、或るものは赤松氏の麾下にはいり、細川や三好と誼を通じるものもあって国中が乱れていた。 上野民部大輔信孝は鬼邑山に砦を築いた後民心の収攬を図るため、年貢を少なくし、貧者や身寄りのない者を救済する方法として寺を活用し実効をあげていた。この頃中央においては管領細川政元の勢威が衰え大内義興が幕政を牛耳ったので、その命により上野氏は間もなく松山城へ移ることになった。信孝の嫡男上野頼久は備中の安国寺を改修して善政を敷いた。
  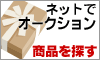
|