| 2005年08月03日(水) |
三村一族と備中兵乱8 |
余談ながらこの寺は城主上野頼久の遺徳を讃え安国頼久寺と改称された。その後、慶長五年(1600)小堀新助政次が備中国に一万石余を領し、没後一子遠州が遺領を継ぎ、禅院式蓬莱庭園を作庭し国指定の名勝になっている。
京都への遠征から帰国した宗親は席の温まる間もなく伯州へ、或いは美作へと遠征してその度に武威を高めていた。この間三村一族の所領である川上郡成羽郷で正妻「須磨」の方との間にもうけたのが嫡子家親である。幼名を虎丸といった。一年遅れて弟親頼が生まれ犬丸と称したが、彼は庶子であり、母は京都から連れて帰って側室とした刀鍛冶の娘奈々である。
「母上、お父上は何時、帰られるんじゃろうか」
と虎丸が母の須磨に聞いた。
「お父上は伯耆の国の不動嶽のお城で戦をしておられるのじゃ」
「虎丸もお父上の所へ行って戦がしてぇな」
「子供が行ってもお邪魔なだけじゃ。それよりも、早う大きゅうなることじゃ」
「どうすれば早よう大きくなれるんじゃろかなぁ」
「好き嫌いを言わずになんでも食べることじゃ」と偏食の虎丸を諭すように言った。
「でも、人参はよう食べんが」
「犬丸をご覧なさい、人参だって美味しいと言ってよく食べますよ。貴方は嫡男じゃけぇ犬丸に負けてはおえんのじゃが」
と須磨の方が言う。嫁いできたときは、都言葉を使っていた須磨の方であったが、鄙びたところで都風を押し通すことには、さまざまな摩擦があっていつしか、備中言葉も身についてきていた。
「負けりゃぁせんが。何時も泣かしているもん」
と虎丸が抗議した。
「よろしい。侍の子は強いことが一番じゃ、じゃがのう、人の道に外れるようなことをしてはなりませぬぞ」
「人の道とはなんじゃろうか」
「忠と孝と礼と信じゃ。そなたも志を大きく持って、やがては都へ出て活躍せねばなりませぬ。そのためには礼儀作法というものが必要になりますぞ。そなたの伯父の信孝殿は将軍近侍で室町礼法を心得られたお方じゃ。伯父上にお願いしてあげますからよく習われるがよかろう」
と須磨の方は幼い家親の躾けには都風で臨むのであった。松山城から室町礼式に詳しい者を招き寄せて養育にあたらせた。
一方側室奈々はこれまた虎丸に負けない子を育てようと犬丸の養育に当たった。
「犬丸よ。乱世に生きるには強くなければなりませぬえ。親子、兄弟といえども敵として戦わねばならない時があるんですよ」
と奈々は明らかに虎丸と喧嘩して負けて帰ってきた犬丸を見る度に切なくなるのである。体は大きくて力もあるので、子供同志の喧嘩ではけっして負けることがないのに、虎丸に対してだけはいつも立ち向かっていこうとせずに勝ちをあっさり譲ってしまうのである。側室の子の立場を弁えて行動する犬丸の心情がいとおしくなる奈々である。
親兄弟、甥伯父という肉親が相争い殺戮しあうことは悲しいことである。できれば我が子にはそのような悲しい思いをさせたくないという思いは強い。
自分自身が混乱の都にあって、目の前で賊に父親を斬殺されるという地獄を見てきている。父の野辺の送りを一人寂しくひっそりと済ませてから、宗親が手配してくれた、備中へ帰る荷駄の隊列の中に加えて貰って成羽の鶴首城へ辿りついた。鶴首城では食客として遇されている兄の甫一にも再会することができたし、自分の身は雑役係ではあるが鶴首城へ置いて貰うことができた。これはひとえに宗親の人間味溢れる思いやりの深く優しい人柄のなせるところであった。
  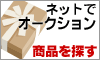
|