先輩、今日ちょっと頭痛で……。
「バカ野郎。そんなもんグラウンド走れば治る! 気合いが足んねえんだよ、気合いが」
監督、歯が痛くてですね、今日の練習は……。
「なに根性ねえこと言ってんだ。走って来い! そうすりゃ歯なんてすぐ治る」
昭和の運動部では、とかくグラウンドは「総合病院」だった。気合いや根性は、さしずめ「魔法の薬」といったところか。それさえあれば、すべての問題は解決される。練習中に水を飲むことはままならず、うさぎ跳びで神社の階段を登らされる――。そんな光景は、昭和の日本ではスタンダードだった。
その後スポーツの世界でも近代化は進み、そういった「根性練」は科学的に否定されることになる。うさぎ跳びのやりすぎは疲労性骨障害を引き起こすというし、水分を補給せずに長時間運動を続けることは、パフォーマンスが低下するだけでなく、熱中症の危険性もある。
この「非科学的トレーニング」は悪だと多くの人が気づき、指摘した。確かにその通りだ。だがここで注目したいのは、「根性」や「気合い」も一緒くたに悪だと決めつけられてしまったことだ。
「スマートなトレーニング」を取り入れた日本のスポーツ界は、不振に陥った。体格や筋力といったフィジカル面に加え、技術や戦略も「頭よく」向上したというのに。
そんななかで再び注目され始めたのが、やはり「気合い」や「根性」だった。ただ、言葉自体は「メンタル」という今風のものに置き換わってはいるのだが。
集中力、闘争心、忍耐力、自己発奮、自主性、持続する意志――。この古臭い言葉には、前向きな精神性を表す多くの意味が含まれている。それは時代が変わっても、評価が廃れることはなかった。
ただ一人、「気合いの復権」を予見していた男がいることをここで紹介しておきたい。彼はその言葉を言い続けていた。
「オラオラそうだ、心の炎を燃やせ。燃えろ、燃えろ、んんんー、気合いだぁ」
そう、アニマル浜口氏である。
2004年04月01日(木)
| 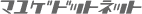 diary/column “mayuge の視点”
diary/column “mayuge の視点”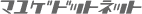 diary/column “mayuge の視点”
diary/column “mayuge の視点”